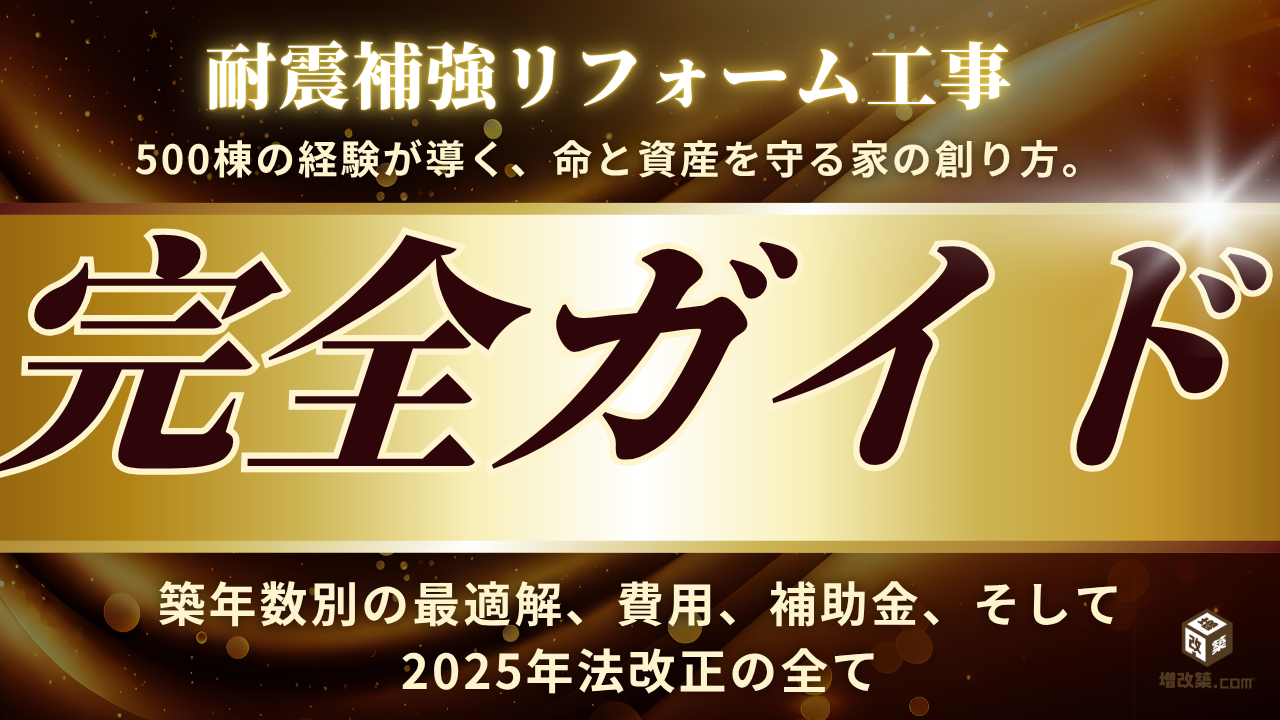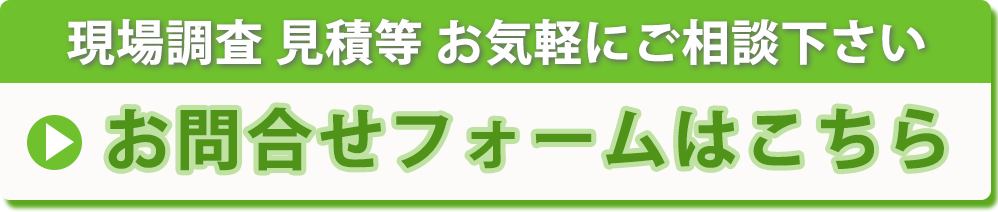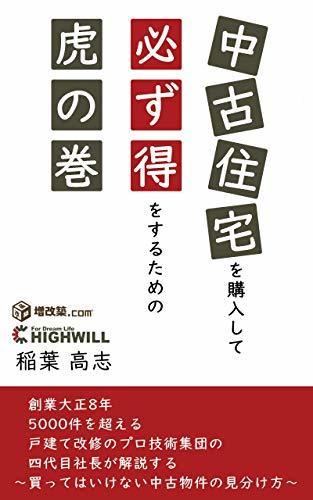戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP> お役立ち情報 > 制震ダンパーの商品徹底比較
2022年06月20日
制震ダンパーの商品徹底比較
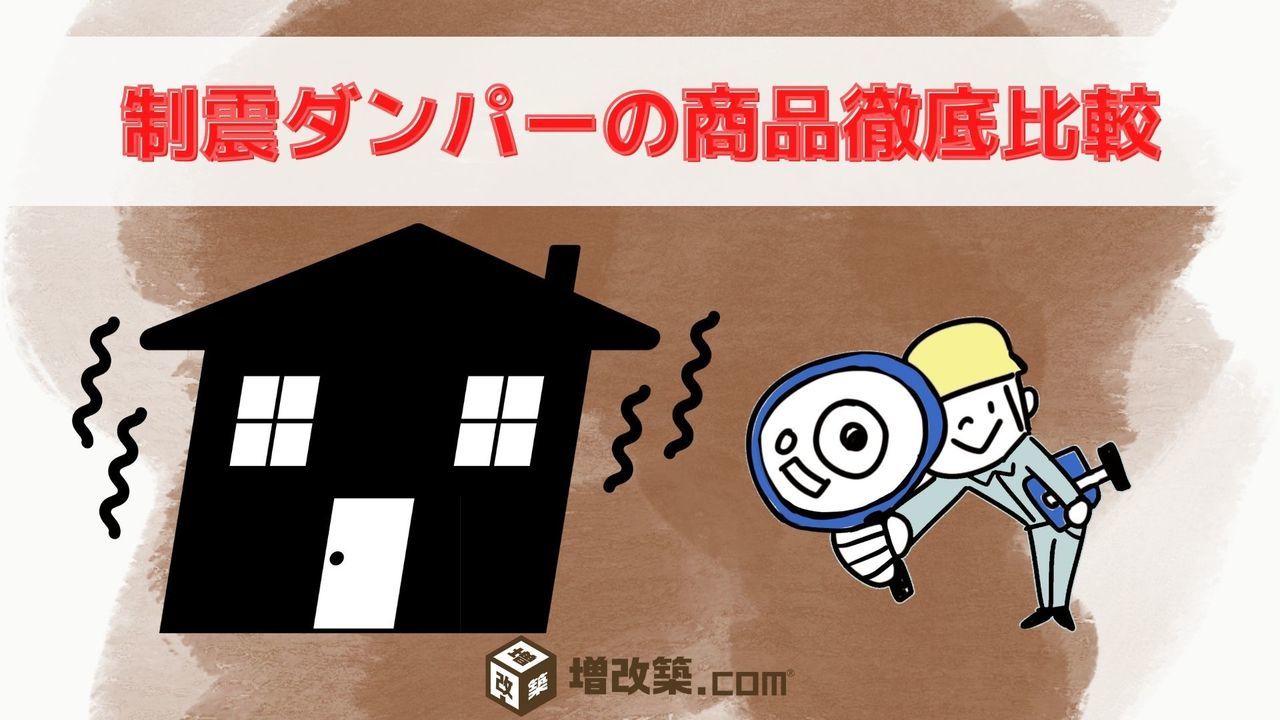
1回大きな地震が起きれば、余震が発生しやすく建物へのダメージが蓄積されやすいのが日本の地震の特徴で、耐震構造だけでは、繰り返しの地震に対しては不安が残ります。
そこで登場するのが制震ダンパーです。
制震ダンパーの採用には、現在の建物がどのような耐震構造になってるのかによって、使い方が変わってくるので、実績のある会社への相談が必須となります。
制震ダンパーにはオイル、鋼材、粘弾性と様々な材質があり、それぞれに特徴があります。そのため、同じ制震ダンパーでも商品の比較を行うと、色々な違いが見えてきます。
今回はオイル、鋼材、粘弾性それぞれの制震ダンパーの特徴や代表となる商品、実際にその制震ダンパーの使用例などを余すことなくご紹介します。

冒頭でもご紹介した通り、制震ダンパーの材質はオイル、鋼材、粘弾性に分けられます。
まず材質別の一般的な特徴やメリット・デメリットをセットでご紹介します。
材質別の特徴1:オイルダンパー
オイルダンパーは小さな穴のあいたピストンと決してパンパンに入っていないオイルで構成されています。
揺れでピストンが動くとオイルは何もない空間の方へ。
すると圧力が高まるため、圧力から逃げようとオイルが再び移動しようとし、その時、小さな穴を通ります。
この時の抵抗でエネルギーを減らし、最終的に揺れが減っていくのがオイルダンパーの簡単なシステムです。
これを「バイリニア特性」といいますが、最大の特徴は小さな揺れの領域から大きな減衰カを発揮しつつも、大きな揺れの領域でも大きな減衰力をそのまま維持することができます。耐震構造で計画された建物へは相性が良いと言えます。耐震構造で倒壊を防止し、オイルダンパーでは倒壊に至るまでの破損を防ぐことができます。
小さな揺れでも対応できるほか、地震の揺れだけでなく強風の影響にも対応できます。
一方で、設置の際に、限界耐力計算が必須になり配置の調整を要するほか、費用的に高く、設置にコストがかかるのがデメリット。
揺れへの柔軟性が高いですが、あとは費用との折り合いです。
材質別の特徴2:鋼材ダンパー
鋼材ダンパーは金属の曲がる力を利用しており、揺れによって金属が曲がると熱エネルギーが生じます。
この時にエネルギーを吸収し揺れを抑えるのが特徴です。
構造自体は難しいものではなく、設置自体も場所をさほどとらないために簡単に行えるのがメリットとされています。
また、オイルダンパーと比べれば安くなりやすいため、コスト的に設置しやすい部分も大きいです。
しかし、熱エネルギーが生じる揺れは結構大きなものでないといけないため、風で揺れる程度の揺れでは制震ダンパーとしての機能を果たしにくい傾向にあります。
そのため、大きな地震に備えるために用いられるのが鋼材ダンパーですが、度重なる揺れで金属疲労を起こしかねないのがデメリットです。
材質別の特徴3:粘弾性ダンパー
粘弾性ダンパーはゴムなどが用いられているので、揺れで変形する時にエネルギーの吸収を行います。
このため、高層ビルなどで用いられることが多く、強風対策や地震対策がセットで行えることから、オイルダンパーと一緒に検討されるのが特徴的です。
古い建物にも設置しやすく、建物の構造に合わせて設置できるほか、オイルダンパーと比べてメンテナンスが必要ないのもメリットとされています。
一方で気温の変化に対応しにくいのが粘弾性ダンパーのデメリットであり、寒い地域では効果を発揮しにくい可能性も。
粘弾性ダンパーで用いる素材は無数にあるため、組み合わせ次第では寒い地域でも一定の効果を出せるようになるものの、コストがかかりやすいのが粘弾性ダンパーのデメリットです。
またどうしてもサイズが大きくなるため、設置場所も考慮しなければなりません。
オイル、鋼材、粘弾性それぞれの特徴をご紹介しましたが、お次はそれぞれの材質における代表的な制震ダンパーについてです。
それぞれの材質のメリットをいかに活用し、デメリットを補っているのかをご紹介します。
オイルダンパーを代表する商品

CRMC-30

減震くんスマート

evoltz
まず紹介したいのが「CRMC-30ダンパー」です。
サイズは小さめで、複数の場所で設置して制震の効果を高めていきます。
小さくて軽い分、取り付けが比較的簡単で、工事の影響が小さいのが特徴的です。
1本あたり1万円ほどで、これを面積に合わせて設置していきます。
国道など車の通りが激しいところでは車の振動が家にまで伝わることがありますが、その揺れを防げるので地震以外にも効果的です。
日立のオイルダンパー「減震くんスマート」は、新幹線や自動車でも用いられるオイルダンパーを改良して作られており、阪神淡路大震災レベルの揺れで、揺れ幅を7割ほど減らしています。
東日本大震災の際には減震くんスマートと同じ工法で作られた「Hiダイナミック制震工法」と呼ばれるオイルダンパーを使っていた住居が、地震翌日でも住める状態になっており、効果の高さをうかがい知ることができます。
オイルダンパーでは海外メーカーが作ったevoltz(エヴォルツ)も人気です。自動車のオイルダンパーとして用いられたものを改良しており、揺れたその瞬間に稼働するのがポイントです。
本来のオイルダンパーが揺れが大きくなって効果を実感できるのですが、evoltzは揺れたらすぐに効果を発揮。
実に100万回の耐久試験を受け、効果が持続し、様々な温度にも対応する柔軟性も見せます。
他にもオイルダンパーの製品が多く、日本や海外それぞれのメーカーがしのぎを削る分野であることは明らかです。
鋼材ダンパーを代表する商品

ディーエスダンパー

EQ GUARD
木造住宅でも利用できる鋼材ダンパーとして注目を集めるのが「ディーエスダンパー」です。
「ディーエスダンパー」は、重さが10キロで厚さも3センチ程度と鋼材ダンパーとしては薄く、比較的設置がしやすい鋼材ダンパーです。
1つの壁に2つ設置が行えるので、揺れをしっかりと吸収するほか、地震が何回も襲い掛かっても耐えられるのが魅力的です。
京商住宅と呼ばれるようなところでも設置できるので、スペースをとらないのが大きなポイントになります。
なんといっても、設置にたった10分しかかからないのがディーエスダンパー。
用いる部品もシンプルそのもので、1人が作業すれば設置が完了するぐらいの手軽さがあります。
住居へのダメージを最小限にしてくれるので、大きな地震にも安心です。
他にはBXカネシンが出している「EQ GUARD」もあります。
鉄が用いられており、鉄の柔軟性を利用して揺れを吸収するのが特徴的です。
揺れでたわみすぎないような構造になっているほか、阪神淡路大震災の揺れを10回与えてもその効果はそのまま。
繰り返し使うと効果を失いやすい鋼材ダンパーのデメリットを補った製品です。
粘弾性ダンパーを代表する商品

ミライエ

Ⅴ-RECS〈SG〉

TRCダンパー
住居用に用いられる粘弾性ダンパーの中で売れているのが住友ゴム工業が販売する「ミライエ」です。
ミライエが人気なのは、ゴムメーカーが作り出した粘弾性ダンパーなので、設置に関する制約がない点。ハウスメーカー独自の制震ダンパーを使わなくても、ミライエを使えば地元のメーカーに建設を依頼してもうまく活用できるのでおすすめです。
強度が硬く、温度変化の影響を受けにくく、しっかりとエネルギーを吸収してくれるのがメリットとなっています。
鋼材ダンパーでも出てきたBKカネシンは高減衰ゴムを用いた「V-RECS〈SG〉」も販売しています。
温度変化が少なく、60年間ほどは劣化が起こりにくく、軽量でコンパクトになっている分、設置が簡単に。しかも、費用面で安くすることができ、粘弾性ダンパーのデメリットを払拭したダンパーになっています。
もう1つご紹介したいのが「TRCダンパー」です。
住友理工が作った制震ダンパーで、強い揺れが何回も襲い掛かったとしても影響を最小限に食い止めます。
しかも設置に時間がかからず、工具も特別なものが必要なく、1か所30分程度で施工できるのも特徴的です。
住友理工はビル用の制震ダンパーや鉄道、自動車などでも存在感を見せ、国内シェア、世界シェアはトップクラス。その安心感が魅力的です。

3種類の材質の中で代表される制震ダンパーを各種紹介しましたが、紹介した中での徹底比較を行い、何が優れているのか、ランキングにまとめました。
第3位:EQ GUARD

第3位は鋼材ダンパーの「EQ GUARD」です。
BXカネシンは文化シャッターのグループ企業であり、大企業が携わるブランドでもあります。
しなやかに揺れる鉄によってその揺れを1割ほどにしてくれるのが特徴的。
部材自体もわずか3つと非常に少なく、大変シンプルな構造であることも魅力的な要素と言えます。
BXカネシン自身が、実に50年以上木造建築に関する研究を行い、建築で用いる金物に関する技術を高めてきました。
その技術の高さがEQ GUARDのような制震ダンパーにも用いられており、木造住宅でも高い制震効果が出せるように設計されています。
配送システムも独自で考案し、最短で発送できるような仕組みも作られ、すぐに利用できるような形になっているのもポイントにつながっている部分です。
第2位:TRCダンパー

第2位は「TRCダンパー」です。
TRCダンパーで用いられているゴムはタイヤに用いられているような材質で、住友理工が独自に配合を行って作られています。
住友理工のホームページでは100年経過しても劣化は起こりにくいと説明がなされており、長い時間をかけて利用し続けることが可能です。
TRCダンパーを実際に用いてほしい場合、TRCダンパーを扱っていない工務店だった場合など、住友理工に問い合わせを行えば、住友理工が工務店に連絡をして取り扱いができるようになります。
取り扱いがない場合を考慮して導入の流れに関するページを用意するなど、そのあたりの配慮もポイントが高いです。
第1位:減震くんスマート

立派な制震ダンパーが多くある中で1位にしたのは「減震くんスマート」です。
減震くんスマートを活用した「Hiダイナミック制震工法」は新築でもリフォームでも効果を発揮し、内壁タイプ、外壁タイプなど色々と用意されています。
劣化促進試験では60年を考慮して実験が行われ、性能に変化がなくオイル交換も必要がなかったことが証明されるなど、安心して長い間利用し続けられます。
どこに制震ダンパーを用いればいいかは事前にシミュレーションを行ってくれるので、どこに設置すればいいか、本数は何本かという提案までやってくれます。
どのハウスメーカーでも利用できるようなものなので、新築物件で利用したい場合や将来的にリフォームを検討している際に用いてみてはいかがでしょうか。

オイルダンパー、鋼材ダンパー、粘弾性ダンパーとそれぞれに優れた製品があることが明らかですが、実際に制震ダンパーを選ぶ際に気を付けるべき点があるのかどうか、その注意点をまとめました。
注意点1:防ぐのは倒壊か損傷かで大違い
制震ダンパーは揺れを抑える特徴があります。
しかし、制震ダンパーによっては、その真の目的が家屋の倒壊を防ぐこと、もしくは家屋への損傷を抑えることと違う目的を持っているケースも。
この違いは大きな違いです。
倒壊を防ぐ場合はあくまでも倒壊防止なので、相当揺れてから機能し始めるため、家屋へのダメージは大きく、揺れに耐えられなくなるケースが生じます。
一方、損傷防止は少しの揺れで効果を発揮するため、震度7クラスの地震が発生しても周囲は致命的な損傷を受けていながら、自分の家だけは全く問題がないということも起こりえるのです。
耐震だけでは不十分とされるのは、耐震自体が倒壊防止がメインであり、1回の揺れに耐えられれば設計上は建築基準法をクリアします。
しかし、熊本地震など震度7クラスの地震が何度も襲い掛かれば耐震だけでは不十分。
そこに損傷防止の制震ダンパーが加わることで複数回の大きな地震に耐えられるわけです。
ですので、制震ダンパーがもたらす効果の違いは必ずチェックしなければなりません。
注意点2:ハウスメーカー次第で特定の制震ダンパーが使えないことも
新築物件で制震ダンパーを活用する際に注意したいのが、ハウスメーカーが独自で耐震や制震を取り入れており、制震ダンパーの必要性がない場合や制震ダンパーをつけることを渋られるケースなどが生じる点です。
建物の構造的に耐震と制震を兼ねるようなフレームを採用し、フレームを活用する分、壁の量を減らすことに成功したケースもあり、この場合だとわざわざたくさんの制震ダンパーは必要ありません。
制震と耐震に対して日本のハウスメーカーはそれぞれが独自に開発し、改良を重ねており、いわばセットになっていて「いいとこどり」ができない状況です。
海外メーカーのダンパーを使いたいなど、特定の要望に対し、その必要はないと突っぱねられる可能性も。
もちろんダンパーなしで制震ができるのは大変すばらしいことではありますが、不安感がぬぐい切れないかもしれません。
もちろん制震ダンパーを付けない状態で家を建ててもらい、その後制震ダンパーをつけるのであれば、ハウスメーカーはさほど関係ありません。
しかし、二度手間であるとともに、費用的に余計な出費になる恐れも。
できれば新築工事の段階で制震ダンパーを取り付けるのが理想的です。
そのため、大手のハウスメーカーではないところに依頼をするなど、ハウスメーカーの影響がない制震ダンパーを使うことも想定していくべきです。
注意点3:コストと補助金のタイミング
制震ダンパーを取り付けるとなると、面積によって異なりますが、数十万円は覚悟し、場合によっては100万円を超えるような費用がかかります。
ダンパーの材質で費用に変化が生じるほか、規模によっては人件費も結構かかるため、相応な出費となるでしょう。
もちろん地震で全壊もしくは半壊となれば、制震ダンパーのコストの比ではない出費となるので、一定のコストはやむを得ないという考え方もあります。
少しでも費用負担を減らすために活用すべきなのが自治体からの補助金です。
工事費用の半分までを負担してもらえるケースや一定額が支給されるケースなど自治体によってバラバラ。
しかも、木造建築が対象となっているケースもあれば、耐震診断で一定の評価以下でないと対象にならないケースもあり、実際に補助金を利用できるかどうかは自治体次第です。
しかも、補助金や助成金には年間の予算があるため、タイミング次第では募集を締め切ってしまうことも。
そのため、制震ダンパーを活用した工事を行う場合には自治体が発表する要件のほか、補助金のタイミングなどをしっかりとチェックすることが求められます。

海外メーカーの制震ダンパーから日本の有名企業が開発した制震ダンパーまで様々な種類があります。
ここで気になるのは、業者に制震ダンパーを決めてもらった方がいいのか、それとも素人である家主が選べるものなのかという点です。
新築物件の場合は基本的にハウスメーカーが制震ダンパーを決めていきます。
標準装備という形で採用をしており、「自分はその制震ダンパーは気に入らない」と別の制震ダンパーを求めることはあまり考えにくい状況です。
ハウスメーカーも立派なプロなので、どの制震ダンパーを使えばいいかなどの知識は持ち合わせています。
また制震ダンパーの情報は素人からすると分かりにくく、建築を勉強している人でないと理解しにくい部分も。
もし素人である家主側が選べるとすれば、工務店など個人経営のメーカーや耐震リフォームをする場合など。
この時は家主側に予算の都合があるため、予算の中で制震ダンパーをつける際、コストを下げつつ効果があるものを利用できます。
理想はプロに任せるのがいいですが、制震ダンパーに関心を持つことで、コスト削減や本当に効果のある制震ダンパーが利用できるようになるでしょう。

昨今は築年数が経過した物件を安く購入して自分たちで魅力的な住居にする、リノベーションが注目され、DIY人気の根強さを感じさせます。
このDIYの一環で制震ダンパーを業者に頼らず、DIYを趣味とする素人が装着できるものなのか、とても気になるところです。
制震ダンパー自体は楽天市場などで購入できるため、DIY目的で制震ダンパーを購入すること自体は可能です。
しかも、制震ダンパーによっては簡単に装着できるものもあるため、手先が器用である程度DIYの経験がある人であれば建築業に携わっていない素人であっても装着することも問題ないでしょう。
しかし、耐震や制震に関してはそれなりの知識が必要であり、装着自体はできるとしても、実際に地震が発生して求めていた効果がそのまま発揮されるかどうかは微妙です。
制震だけでは意味がなく、耐震までして初めて成立するものなので、リノベーションの際には耐震と制震を一緒に考慮しなければならず、いくらDIYが得意でもかなり繊細な部分。
あくまでも「装着そのものが可能」ということであり、制震ダンパーの効果を最大限に発揮するように装着させるにはプロ、業者に任せるのが確実であり、それがおすすめです。
実際に制震ダンパーはどのように用いられているのか、今回ご紹介した制震ダンパーの商品を実際に使っているケースをご紹介します。
減震くんスマートを用いているケース

減震くんスマートはオイルダンパーでありながら、壁の中で用いるタイプのオイルダンパーなので、一般的なオイルダンパーよりも使用する数が少ないのが特徴的です。
木造住宅でも利用できるほか、ある程度狭い住宅でも用いることができ、数十万円程度の予算で装着することが可能です。

出典:株式会社三協
また既存の住宅に設置する場合は1階部分に数か所設置するだけで十分な効果をもたらします。
もちろん費用面も新築の時と変わらず、安いコストで安心できる効果を発揮することが可能です。
オイルダンパーでありながらメンテナンスフリーが魅力的で、オイル漏れの心配もないのが特徴的。
日立ブランドという点も全国のハウスメーカーで利用されやすい状況を生み出しています。
TRCダンパーを用いているケース

出典:ほそ川建設株式会社
TRCダンパーは筋交いに設置を行うタイプの制震ダンパーなので、技術的な差が生じにくいタイプとなっています。
そのため、新築工事の時に用いることで簡単に制震性能を高められるほか、時間がかからないので制震性能を高めるために何日がかりも必要になる事態は避けられます。
TRCダンパーに関してもメンテナンスフリーであり、温度の影響を受けにくいのが特徴的。
ですので、寒い地域であっても問題なく利用できます。また住友理工のホームページでは無料制震シミュレーションを受け付けており、細かなデータまで出してくれます。
TRCダンパーを使ったらどのような効果をもたらすかが一目瞭然になるのも安心できる材料であり、大いに参考になるでしょう。
耐震で失敗しない為の
『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』
500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!
耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!
耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。
読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。
※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。
【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】
第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う
診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。
記事(全6本):
➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」
➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か
➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方
➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか
➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている
第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術
治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。
記事(全11本):
➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか
➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画
➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠
➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事
➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実
➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値
➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌
第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術
計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。
記事(全5本):
➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較
➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”
➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強
➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技
➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値
第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術
計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。
記事(全4本):
➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術
➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解
➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術
➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル
第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない
実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。
記事(全5本):
➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択
➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは
➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画
➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事
➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化
第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択
最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。
記事(全4本):
➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか
➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実
➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください
➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ
終章:エピローグ ~100年先も、この家で~
終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。
記事(全1本):
➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。
< 著者情報 >
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。
戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・
- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。
耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。
補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)
ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新
※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。
営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)