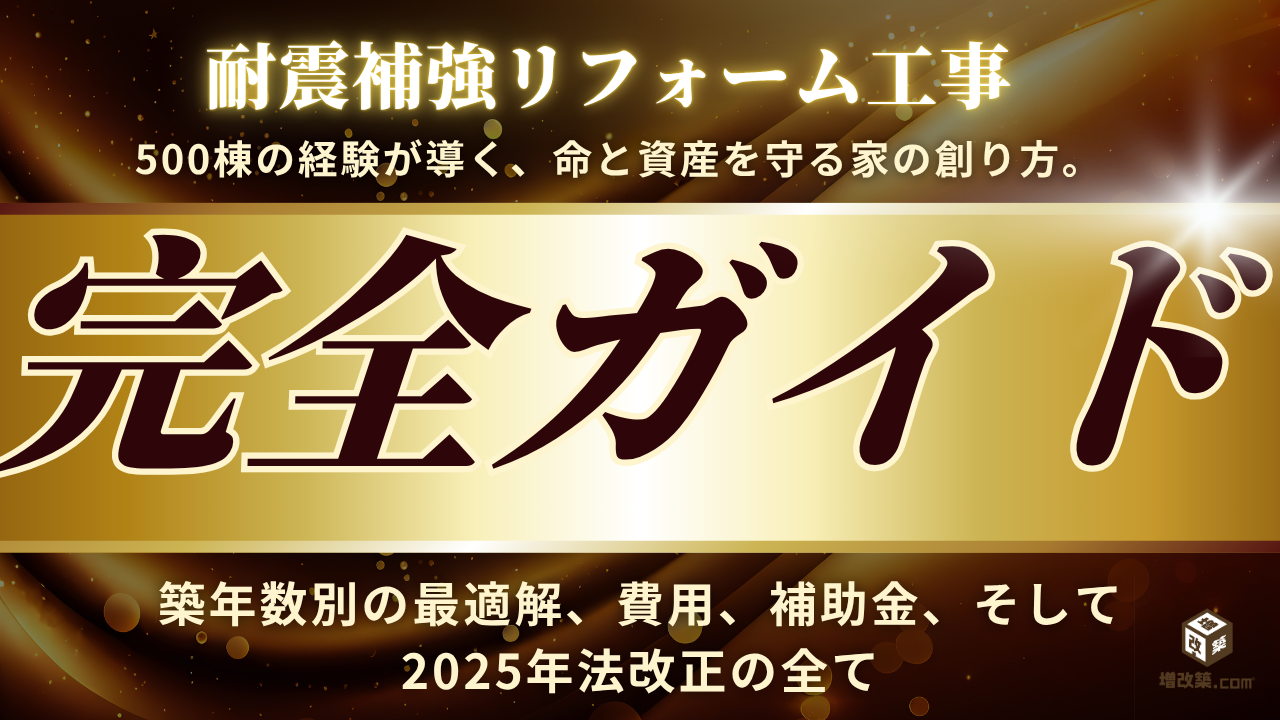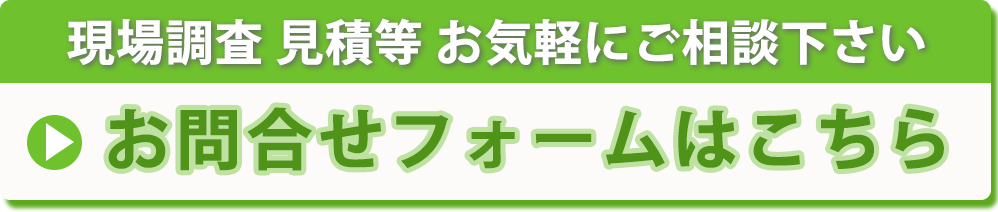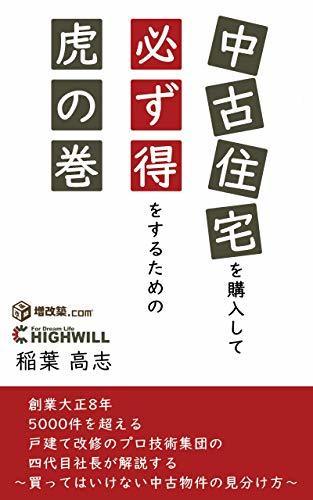戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP> お役立ち情報 > 制震ダンパーの気になる費用価格は?種類や費用価格、選び方の注意点について解説
2024年09月10日
制震ダンパーの気になる費用価格は? 種類や費用価格、選び方の注意点について解説します

地震大国である日本。ローンを組んでまで作った夢のマイホームが、1回の地震で台無しになることは避けなければなりません。
そのため、多くの住宅では何かしらの地震対策が施されており、その中に「制震」があります。その制震で用いられる器具が制震ダンパーです。
耐震や免震との違い、制震ダンパーの材質の違い、そして制震ダンパーの費用価格や材質ごとの費用の違いなどをまとめました。
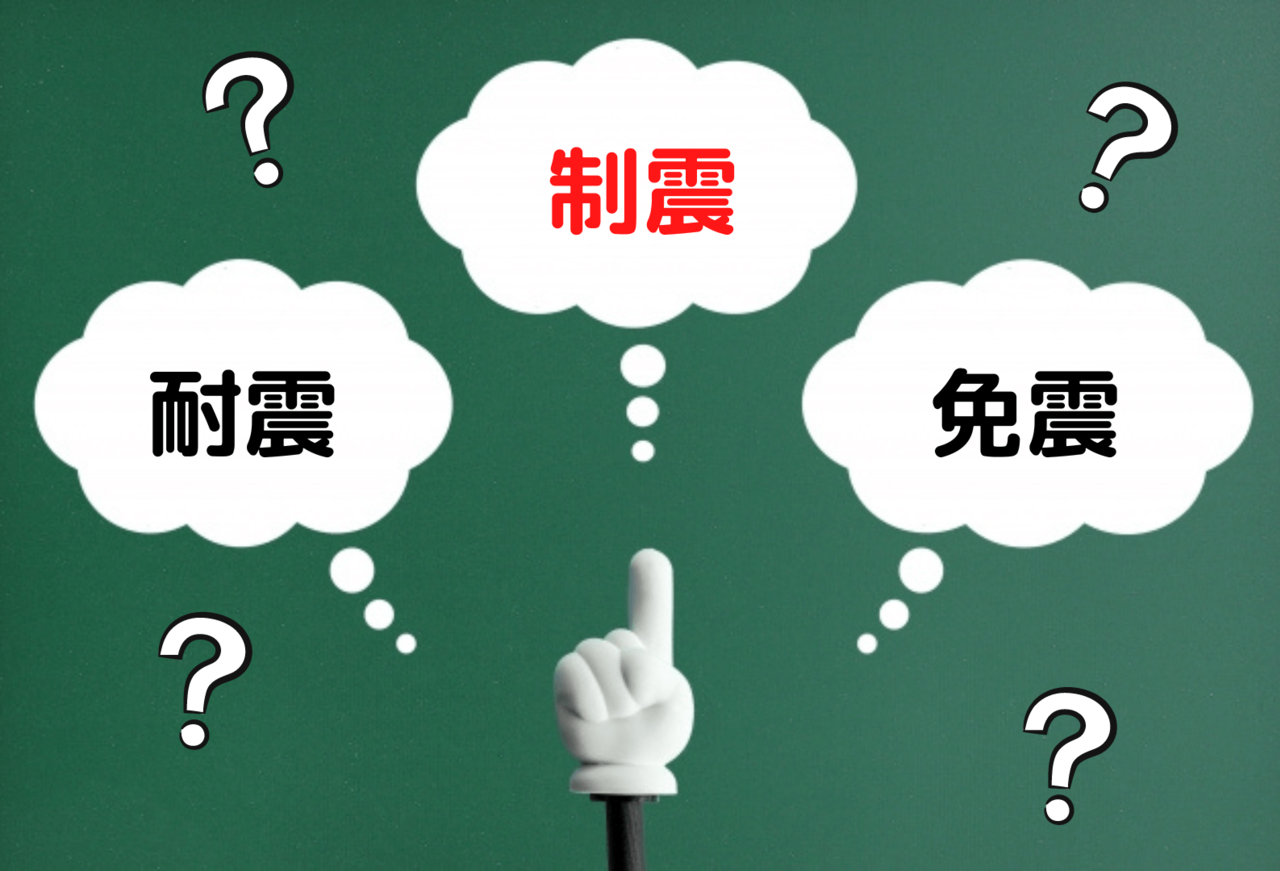
地震対策の1つである制震。果たして耐震や免震と何が違うのか、様々な観点からご紹介します。
1-1. 制震は建物内でダンパー装置を取りつければOK
耐震の場合、耐力壁を増やす、壁の倍率を上げるといった、大きな揺れに対する耐久性を高めるのが特徴的です。
そのため、性能向上リノベーションの現場では、最初から耐震性能の向上を想定した建物として構造計算をして工事をするため、コストが普通の住宅リフォームよりもかかります。
免震は、基礎に免震装置を設置することで地震の揺れを逃がし、建物に大きな揺れを与えないようにさせます。
効果は大きいですが、基礎に免震装置を設置する分、手間がかかるほか、地盤が弱いとその効果は高くありません。
対して、制震は建物内にダンパーなどの装置を取り付け、その装置が地震の揺れを吸収します。
制震ダンパーを建物内に設置するだけなので、普通の住宅に地震対策を施したい場合にもすぐ対応可能。
制震ダンパーをつけるだけで地震に強い家になるという手軽さは相当なアドバンテージです。
1-2. 制震は繰り返しの地震に強い!
地震大国の日本。1回大きな地震があったらそれで安全とはいきません。余震などが何回も襲い掛かるほか、倒壊するほどではないにしてもそれなりに大きな地震が襲い掛かります。
繰り返しの地震に弱いのが耐震で、1回は耐えても、余震がボディーブローのように効いてくる可能性は否めません。
例えば東日本大震災のように、あれだけの大きな地震が1回起きると10年先まで大きな地震が襲い掛かり、いまだに東日本大震災の余震であることに驚かされる人もいらっしゃるでしょう。
熊本での地震のように、本震レベルの地震が発生してダメージが十分かかった中で本震が襲い掛かり、多くの家屋が倒壊したケースもあります。
そもそも現状の建築基準法における耐震等級1レベルは、阪神淡路大震災級の地震が1回起きても強度が保てていればいいという基準【倒壊防止】になっており、あくまで生命を守るのが目的であって、家が損傷しないという基準ではないということです。
耐震等級を決める時点で1回の大きな地震しか想定しておらず、2回目3回目のことは考慮されていません。これでは不安です。
先の熊本地震では耐震等級2(1.25倍)の建物が繰り返しの地震で倒壊しました。国の最低基準は耐震等級1となっていますが、
そのために耐震等級3、つまり等級1の1.5倍の耐力を最低ラインとしたいところです。
耐震自体が揺れに耐える目的となっていますので、この耐震構造に、地震力を逃がす(吸収する)制震ダンパーを配置することが結果として、繰り返しの地震に強いことがいえます。免震に関しても繰り返しの地震に強いですが、やはりコスト面を考えると制震の方が圧倒的です。

出典:BUNGY JAPAN
耐震と制震はバンジージャンプを例にとるとわかりやすいです。
ジャンプをする人の身体を「建物」、ジャンプし落ちきった際の身体への衝撃を「建物に与える地震力」と置き換えて考えてみましょう。
パンジージャンプの際に「頑丈な縄のロープ」でジャンプをするのが耐震のイメージとして考えてみましょう。
確かに丈夫なロープですから丈夫なロープであればあるほど切れる心配はありませんね。縄は丈夫なだけ良いということになります。
では、ゴム製のロープで飛んだらどうでしょうか。この「ゴム製のロープ」を制震と考えてみてください。確かに切れる心配はないと思います。
しかし、身体(建物)への衝撃はどうでしょうか?丈夫な縄のロープとゴム製のロープではどちらが身体(建物)に与える衝撃は大きいでしょうか。縄のロープでイメージをした耐震になるのがわかると思います。とはいえ、ゴムだけで良いのか?ゴムだけでは切れてしまえば身体は下へ落下してしまいますよね。これも本末転倒です。
では、一番身体(建物)に最も衝撃なないのはどのような形でしょうか?
ジャンプをして縄ロープで衝撃を受ける前に、ゴムが落下スピードを吸収してくれることですよね。ゴムのロープがスピードを吸収して、伸びきったとこで縄のロープが効く形が最も身体(建物)に優しいということがお分かりいただけるのではないでしょうか?
バンジージャンプのイメージでお分かりの通り、「耐震」も「制震」も両方必要であるということです。
耐震を縄のロープに例えましたが、縄のロープ1本で飛ぶのが耐震等級1、縄のロープ2本で飛ぶのが耐震等級2、縄のロープ3本で飛ぶのが耐震等級3と考えるとさらにリアルにイメージができるのではないでしょうか?※正確には1.25倍と1.5倍です。
制震と一緒に耐震を考えた方が良いのはわかりましたが、縄ロープは1本(耐震等級1)でよいですか?といった考え方です。
縄は3本でゴムロープも一緒にジャンプするのが最も安全であることがイメージできるのではないでしょうか?
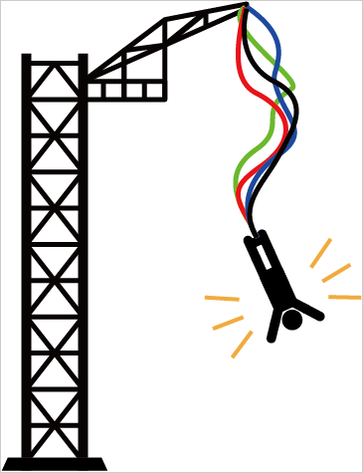
1-3. 制震はコスト面でかなり違う!
耐震の場合、新築物件を購入する際には既に耐震の費用が組み込まれていますが、性能向上リノベーションにおいて、耐震改修となるとだいたい150万円ほどはかかると言われています。
免震は既存の住宅とは別に必要なので、耐震よりもその費用は高め。250万円前後と耐震よりもかなり大きく、後から免震を導入しようと思えば、かなり難しい工事になるでしょう。
加えて、免震の場合は地盤が弱いと効果が落ちてしまうため、地盤を補強する工事を行ってから免震の設備を設置するので、その費用も加味すれば、それなりの値段になります。
その点、制震は制震ダンパーを活用することで、材質などにもよりますが、一般的な40坪ほどの家ならば装置やダンパーのみの費用で50万程度が平均相場となっております。手間やコストの面からも、免震よりは圧倒的に制震でしょう。
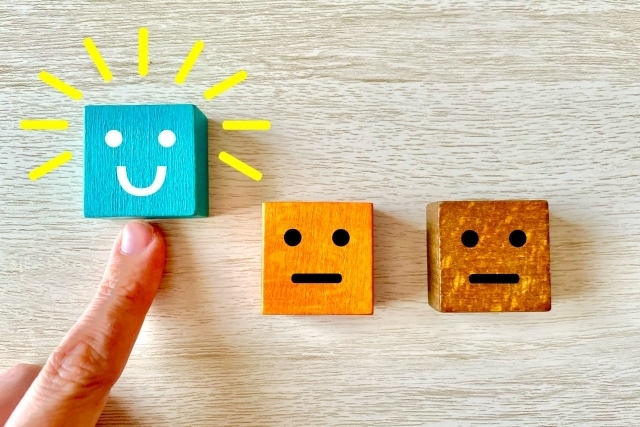

地震の揺れを吸収してくれる制震ダンパー。ここでは制震ダンパーの材質的な違いについて解説します。
制震ダンパーの種類①:オイルダンパー
油圧式の制震ダンパーは、内部がシリンダとピストンで構成され、その中にオイルが入っています。
圧力がかかった場合、その圧力でピストンが動き、シリンダの内部にあるオイルが押されます。この時、オイルが抵抗することで衝撃が吸収されます。
一般的なところでは車や新幹線の衝撃吸収に用いられるなど、実は身近でも体感できるようなものと同じような仕組みです。
普通の電車だとレールのつなぎ目でガタンガタンとそれなりに揺れを感じますが、新幹線はレールのつなぎ目が少ないといっても、あれだけのスピードで走っているのにそこまで大きな揺れではありません。
細かな揺れに対応できるのもオイルダンパーのいいところで、強風による揺れなど揺れ全般をフォローできるのもメリットの1つです。
建物でいうと、線路沿いの建物での電車の通過時や大通り沿いの建物で大型トラックなどが通過する際の振動を吸収する効果もあります。
そのため、大きな揺れで対応する特性はなく、小さな揺れの段階で効果を発揮するタイプといえます。建物の倒壊防止ではなく損傷防止目的といえます。
制震ダンパーの種類②:鋼材ダンパー
鋼材ダンパーは文字通り鋼材が、衝撃を軽減してくれます。一般的な鋼材もあれば特殊合金を使うケースもあるなど、種類は豊富です。
衝撃が加わると金属が曲がり、その時のエネルギーが熱エネルギーに変化して衝撃が吸収されるというメカニズム。
揺れが大きいほど効果を発揮しやすく、手っ取り早く大地震に備えることを考えた際、選択肢の1つとして有力です。
裏を返せば、オイルダンパーと違って小さな揺れには対応していないことを意味します。これは小さな揺れにまで対応してしまうとダンパーにダメージが蓄積されてしまうからです。
そのため、小さな揺れに関してはエネルギーを吸収せず、大きな揺れで対応するような状態になっています。
揺れが大きい段階で効くことから、建物の倒壊防止目的といえます。
制震ダンパーの種類③:粘弾性ダンパー
粘弾性ダンパーはシリコンやゴムなど粘りがあるようなもので作られた制震ダンパーです。
鋼材ダンパーのいいところとオイルダンパーのいいところを足して2で割ったような性質を持っており、用いられる材質の数はかなり多めです。
意外と奥が深いダンパーとして知られ、どの素材をどのように使えばより効果が増すかという組み合わせは無数。粘弾性ダンパーの完成形はまだないものの、その効果は大きめです。
揺れに関しては中程度の揺れから大きな揺れまでの対応することからオイルダンパーのいいところが幾分盛り込まれていると言えますが、メリハリがないと言えばそうなってしまいます。
温度の影響があるのが粘弾性ダンパーのデメリットで、夏と冬の違いでエネルギーを吸収するパワーがかなり異なるため、冬場に地震が発生した際、思った効果が得られない可能性も想定できます。
組み合わせは無数、効果は無限大だからこそ、今後オイルダンパーや鋼材ダンパーのいいところだけを吸収し、デメリットは極力排除された粘弾性ダンパーが登場する余地も残されています。

制震ダンパーだけでもかなりの種類がありますが、種類が違うことでどれくらい費用面で違いがみられるのか、解説します。
3-1. オイルダンパーの費用
木造住宅にも利用できるオイルダンパーですが、1人で簡単に施工が行えるケースもあり、設置に関する費用はだいたい50万円~です。
取り付け自体はさほど難しくなく、家屋の内側もしくは外側から選べ、設置が簡単な分、費用的には十分安く収まりやすいです。あとは家屋全体に何本設置するかなど、設置本数に費用が左右されます。
オイルダンパー1本あたりの値段はバラバラですが、だいたい3万~5万円ほど。
3-2. 鋼材ダンパーの費用
鋼材ダンパーの費用ですが、コスト的にはオイルダンパーよりもややかかる傾向にあります。オイルダンパーは1人で作業ができるのに対し、鋼材ダンパーは複数人が施行に携わらないと設置できません。
それもそのはず、鋼材ダンパー1本で数十キロもあるため、これを何本も運んで施工するとなれば、費用はそれなりにかかってしまいます。
鋼材ダンパーの費用は1本あたり5万円から10万円程度と高め。ただし設置する場所はオイルダンパーほど多くはありません。そのため、最終的な費用はオイルダンパーと同じぐらいになりやすいです。
3-3. 粘弾性ダンパーの費用
粘弾性ダンパーの価格は材質によって異なりますが、主流の粘弾性ダンパーであれば、1本あたり10万円はかかります。鋼材ダンパーよりも高くなりやすいです。
ただし、粘弾性ダンパーは10坪につき1本の割合で使えば十分とされるため、40坪だったとすれば4本で済みます。
これを単純に計算すれば40万円となるので、実はオイルダンパーよりも安く抑えられる可能性も。
今回ご紹介したものは足場を組むなどの想定をしていないので、もし足場を組むなどの作業が発生すれば、より費用が高くなることが想定されます。

制震ダンパーの費用はおよそ50万円とされていますが、材質別の費用の違いでもご紹介した通り、その費用は制震ダンパーの材質と本数で決まります。
つまり、1本あたりの価格が違ったとしても、トータルで必要となる費用に大きな差はありません。40坪あればだいたい50万円程度の費用がかかると思っていいでしょう。
オイルダンパーは1本あたりの費用が安い代わりに、面積に応じて本数が増えていきます。
粘弾性ダンパーは1本あたりの費用が高い代わりに、本数は少なくても問題ありません。
何本の制震ダンパーが必要なのかは、東海地震などを想定して算出されており、マニュアルにしている会社もあるほど。
仮に耐震補強をしていたとしても、耐震では補え切れない部分をカバーできるのが制震ダンパーなので、制震ダンパーで補いたい箇所だけ追加する手もあります。

ここからは制震ダンパーについて注意すべき点について解説します。
注意点①:性能の良し悪しは正しい構造計画と構造計算で決まる!
さまざまな、制震の種類をお話してきましたが、どの制震ダンパーを使用しても、建物全体の構造計画が間違っていれば、その耐震は絵に描いた餅となります。制震を採用するにあたり、最も重要な要素が配置計画となります。
新築であらかじめ机上の計算で計画を立てることが可能ですが、既存の建物に制震ダンパーを配置する際には、しっかりとした計画が必要になります。既存の耐力がどのレベルの建物であるのか。築年数が経過した建物では、そもそも耐震性能が圧倒的に低い現状があります。
ここで制震ダンパー頼みの計画をしてしまうことは本末転倒です。
バンジージャンプの例を思い出してください。
耐震性能が現行基準の50%の耐力の耐震性能であれば、縄のロープは1本分の半分の細さのロープということになります。そこにいくらゴム製のロープ(制震ダンパー)をつけても、安心できるものではないということがイメージできるのではないでしょうか?
制震ダンパーのメーカーでは、よくリフォームでの簡易構造計算をサービスするところがあります。
メーカーの視点でみるとダンパーの台数を増やすことで、見た目の数値だけは向上しますので安心を売ることができるわけですが、
ここに注意が必要なのです。あくまでも耐震性能を現行基準の1.5倍レベルまでの耐震補強があって然るべきで、ベースとなる構造計算(壁量計算・N値計算等)が必要です。その補強計画を補う形で、制震ダンパーの配置を検討するのが正しい制震ダンパーの利用の仕方になります。
制震ダンパーでの構造計算は「限界耐力計算」という計算が別途必要になります。
注意点②:建物の面積の問題
制震ダンパーの費用は建物の面積によって比例するように高くなります。これは免震と違う部分かもしれません。
一方で、あまりに狭いと制震ダンパーが利用できないというデメリットもあります。後付けが可能なのが制震ダンパーのいいところですが、部屋が狭いと効果的な制震ダンパーが使えない可能性も。
また足場が組めないようなところだと内側からしか作業ができないので、場合によっては数日も工事のためにホテルなどを借りるような生活を余儀なくされるケースが出てきます。
築年数など状況次第では設置の効果が得られにくいなどもあるので、その際は制震ダンパーだけでなく家のリフォームも想定した計画を立てなければなりません。
広すぎれば費用が掛かり、狭すぎれば設置しにくくなるという問題を抱えるほか、最低限の耐震補強が必要になるケースが多いことから、一度壁を壊して制震ダンパーをつけて再び壁をつけるという、リフォームのような大がかりになる可能性も考えられます。
注意点③:制震ダンパーだけでは不十分なケースも
制震ダンパーも十分地震を吸収する効果がありますが、吸収するといっても限度があります。バンジージャンプの例を思い出してください。
そのため、耐震+制震ではじめて安心ができるということです。耐震での倒壊防止をギリギリまで食い止める損傷防止目的として制震を利用し、お互いを補うのが確実となります。
耐震は揺れに強いものの、繰り返しの地震には弱い側面があり、蓄積されたダメージによってそこまで大きくない地震で壊れてしまう可能性が想定されます。
制震ダンパーは揺れを吸収し、繰り返しの地震に強いので、ダメージを家屋に与えず、何回も地震に耐えるので、より壊れにくくなります。
つまり、耐震性能の向上を前提とした建物であれば、揺れの初期に効くオイルダンパーが最も補完性が高くなることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
注意点④:高性能な制震ダンパーは値段が張る
制震ダンパーの材質にはオイルや鋼材、粘弾性材質などがあります。例えば粘弾性材質は温度変化に弱いとされ、粘弾性ダンパーは寒さで粘弾性が下がって硬くなって耐震性が落ちると言われてきました。
近年は粘弾性を落とさないようなダンパーが開発され、寒さに強いものも出てきましたが、値段的には通常の粘弾性ダンパーより高くなってしまいます。
高機能なものほど高くなりやすく、多く設置して費用が嵩むケースも。
耐震性はもちろんのこと、費用面との折り合いをしっかりとつけておくことが非常に重要です。
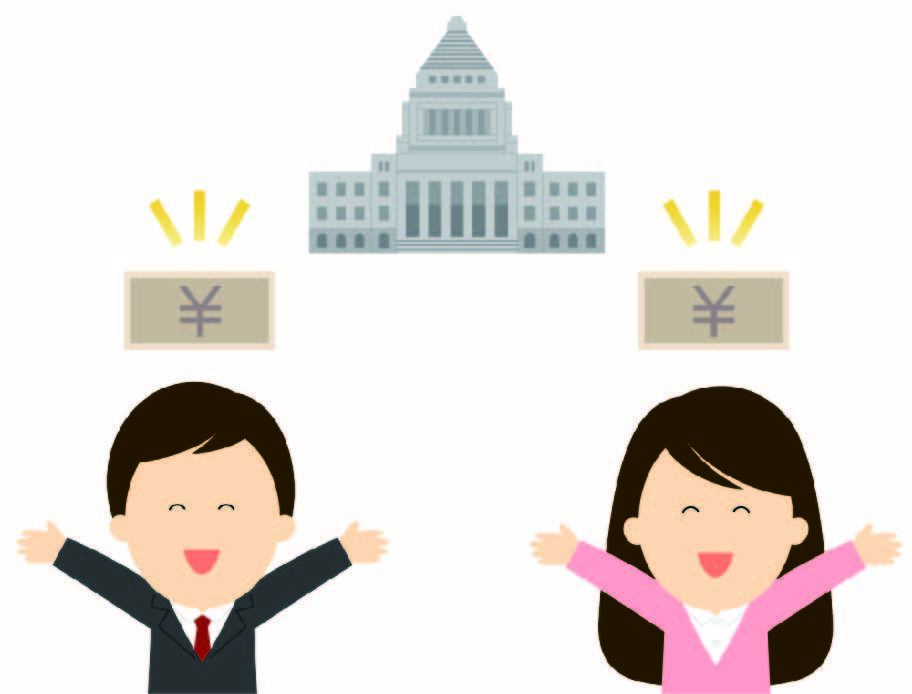
耐震補強に関して、補助金がもらえるケースがあります。この補助金は自治体によって支給される、されないがあるので注意です。
築年数が古い木造住宅が想定された補助金で、耐震診断を行い、耐震性が不十分と判断され、耐震補強を行って十分な耐震性と判断された場合に補助金がもらえます。
その金額は自治体によって違いがありますが、最大100万円を限度に支給されるなど、費用の多くが軽減されるケースも。
近年リノベーションをしようと築年数が経過した木造住宅を安く購入する方が増え、思い思いにリノベーションを行っています。
こうした物件に制震ダンパーなどを付けた場合、その費用の大部分が補助され、実際支払う費用がかなり軽減。
耐震の補助が、日本建築防災協会の耐震改修のガイドラインに沿った補強を推奨していることから、制震ダンパーに対しての補助を出す自治体はかなり少ないので調べる必要があります。
耐震についての補助金については自治体により条件は異なるほか、木造住宅や築年数など関係なく利用できることもあるため、お住まいの自治体の補助金に関する情報は入手しておきましょう。

最初から制震ダンパーをつける事例もある一方、制震の魅力は後付けができる点です。
ここでは制震ダンパーを後付けした事例についてご紹介します。
施工事例①:家の中から後付けを行う場合
家の中で制震ダンパーの後付けを行う場合は、壁を取り外すことから始めます。ダンパーを取り付けてしまえば、あとは元通りにするだけ。
さほど大掛かりにならないことや雨でも関係なく作業ができること、人手がかからないことが特徴的で、費用もそれなりの値段に抑えられます。
もちろん壁を剥がすなどの行為が入るため、再び壁を張るなどの作業は必要で、エアコンの真裏が設置スペースだった場合は一旦エアコンを外すという作業も。
結果的には大掛かりになってしまうこともありますが、何週間もかかるような大工事というわけではないので、安全を手に入れるための我慢のしどころです。
施工事例①:家の外から後付けを行う場合
外側から後付けを行う際には、外壁を取り外していきます。先ほどは内側で多少影響が出る施工方法でしたが、こちらは内側にほとんど影響を与えず、エアコンも外さなくて済みます。
工事中はわざわざと外に出かけるなどのことをしなくても、家に居ながらにして後付けの作業を見守れるほど、影響は少ないです。
外側で作業をする分、足場の問題がある一方、雨の日は作業ができません。加えて足場などの費用が掛かるため、内側での後付けよりも値段がかかりやすくなります。
ただ生活に支障が出にくいことなどを考慮すると、後付けの方がいい場合もあります。内側もしくは外側、それぞれにメリットやデメリットがあることを考慮しましょう。

本記事では、制震ダンパーの費用や選び方、そして制震の役割について詳しく解説しました。制震は「耐震=倒壊防止」「制震=損傷防止(倒壊までの時間稼ぎ)」という役割分担のもと、建物の耐震性能をさらに向上させる重要な装置です。耐震だけでは繰り返しの揺れに対応しきれないため、制震ダンパーを併用することで、建物の損傷を防ぎ、倒壊までのリスクを大幅に減らすことが可能です。
制震ダンパーのポイント:揺れを吸収し、損傷を防ぐ
制震ダンパーは、地震時に発生する揺れのエネルギーを吸収することで、建物への衝撃を和らげ、内部の損傷を防ぐ役割を果たします。これにより、繰り返し発生する余震にも効果的に対応できるため、制震は非常に実用的な地震対策といえます。ただし、制震はあくまで損傷を防ぐものであり、倒壊防止を目的とする耐震の補完的な役割であることを理解し、適切な使い方をすることが最大のポイントです。
制震ダンパーの種類と選び方:変位依存型と速度依存型
制震ダンパーには、大きく分けて変位依存型と速度依存型の2種類があります。
-
変位依存型:ダンパーの変形量に応じてエネルギーを吸収します。主に鋼材ダンパーや摩擦系ダンパーが該当し、大きな変位に対して効果を発揮するため、建物が大きく揺れる状況で有効です。
-
速度依存型:ダンパーの変形速度に応じてエネルギーを吸収します。代表的なものにオイルダンパーがあり、揺れの速さに関係なく効率的にエネルギーを吸収することができるため、小さな揺れから大きな揺れまで幅広く対応できます。
-
ゴム系ダンパー:変位依存型と速度依存型を組み合わせたような特性を持ち、様々な地震の揺れに対応できる柔軟性がありますが、温度変化に弱いことが課題です。
小さな揺れから効き始めるダンパーがベスト
結論として、どの制震ダンパーが最適かというと、小さな揺れから効き始めるものが良いとされています。それが「オイルダンパー」です。オイルダンパーは、速度依存型であるため、揺れの速さによって吸収力が変わらず、繰り返しの揺れにも耐久性を持っています。また、早い揺れからゆっくりした揺れまで幅広く対応することができるため、建物の損傷を防ぐという目的には非常に適しています。
速度依存しにくいオイルダンパーを選ぶことが重要
制震ダンパーの中でも、特に速度依存しにくい設計のオイルダンパーを選ぶことで、揺れの種類に関係なく安定した効果を発揮します。ピストンの動きが速くても遅くても一定の抵抗力を持つダンパーであれば、予測が難しい地震の揺れにも対応でき、安心感が高まります。
耐震と制震の2段階構造計画が必要
制震ダンパーの設置を検討する際には、まず既存の建物の耐震性を正確に評価することが不可欠です。その上で、必要に応じて耐震補強を行い、補強された建物に制震ダンパーを設置するという2段階の構造計画が求められます。これにより、耐震が倒壊防止、制震が損傷防止として効果を発揮し、地震から建物を守る理想的な対策が実現します。
専門家に相談して最適な対策を
今後、耐震リフォームや新築を検討する方は、「耐震+制震」の考え方を基本に据え、信頼できる専門家に相談してしっかりとした構造計算を行うことが重要です。耐震等級の向上と制震装置の適切な配置が、繰り返される地震にも耐えられる住まいづくりの鍵となります。
さらに詳しいコンテンツはこちら
➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値
➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較
➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”
耐震で失敗しない為の
『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』
500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!
耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!
耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。
読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。
※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。
【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】
第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う
診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。
記事(全6本):
➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」
➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か
➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方
➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか
➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている
第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術
治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。
記事(全11本):
➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか
➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画
➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠
➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事
➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実
➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値
➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌
第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術
計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。
記事(全5本):
➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較
➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”
➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強
➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技
➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値
第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術
計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。
記事(全4本):
➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術
➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解
➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術
➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル
第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない
実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。
記事(全5本):
➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択
➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは
➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画
➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事
➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化
第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択
最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。
記事(全4本):
➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか
➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実
➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください
➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ
終章:エピローグ ~100年先も、この家で~
終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。
記事(全1本):
➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。
< 著者情報 >
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。
戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・
- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。
耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。
補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)
ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新
※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。
営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)