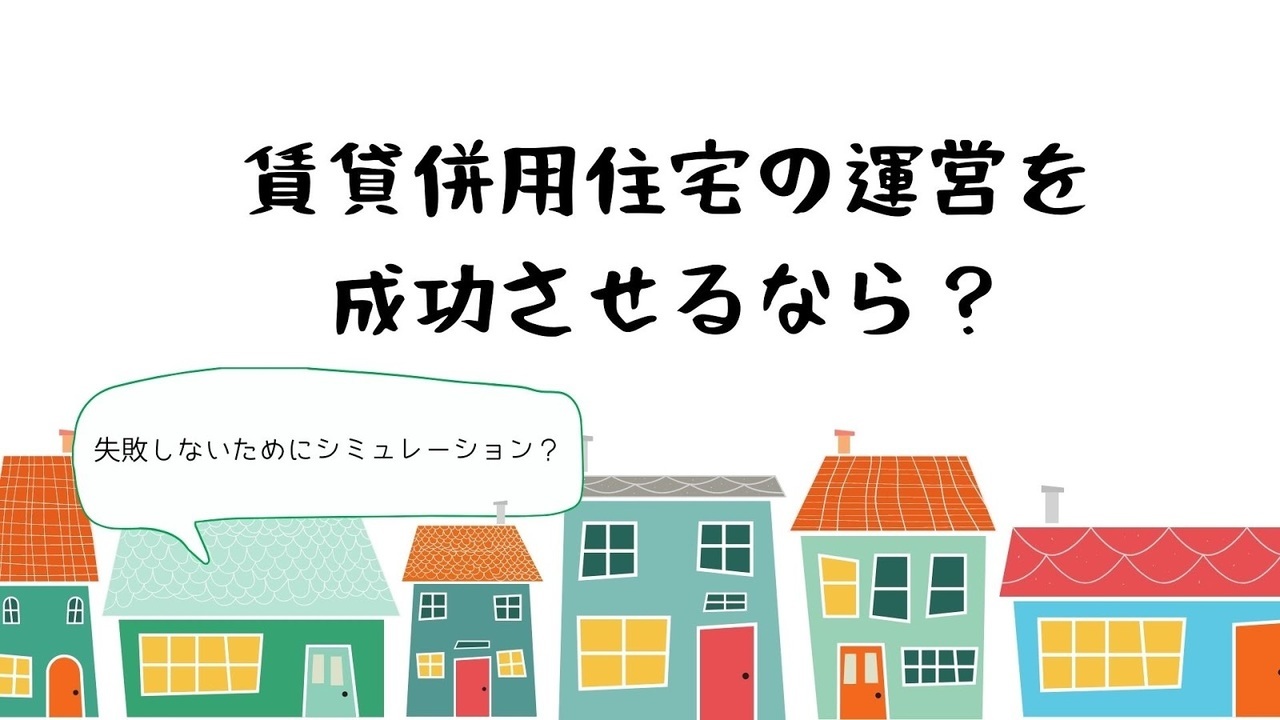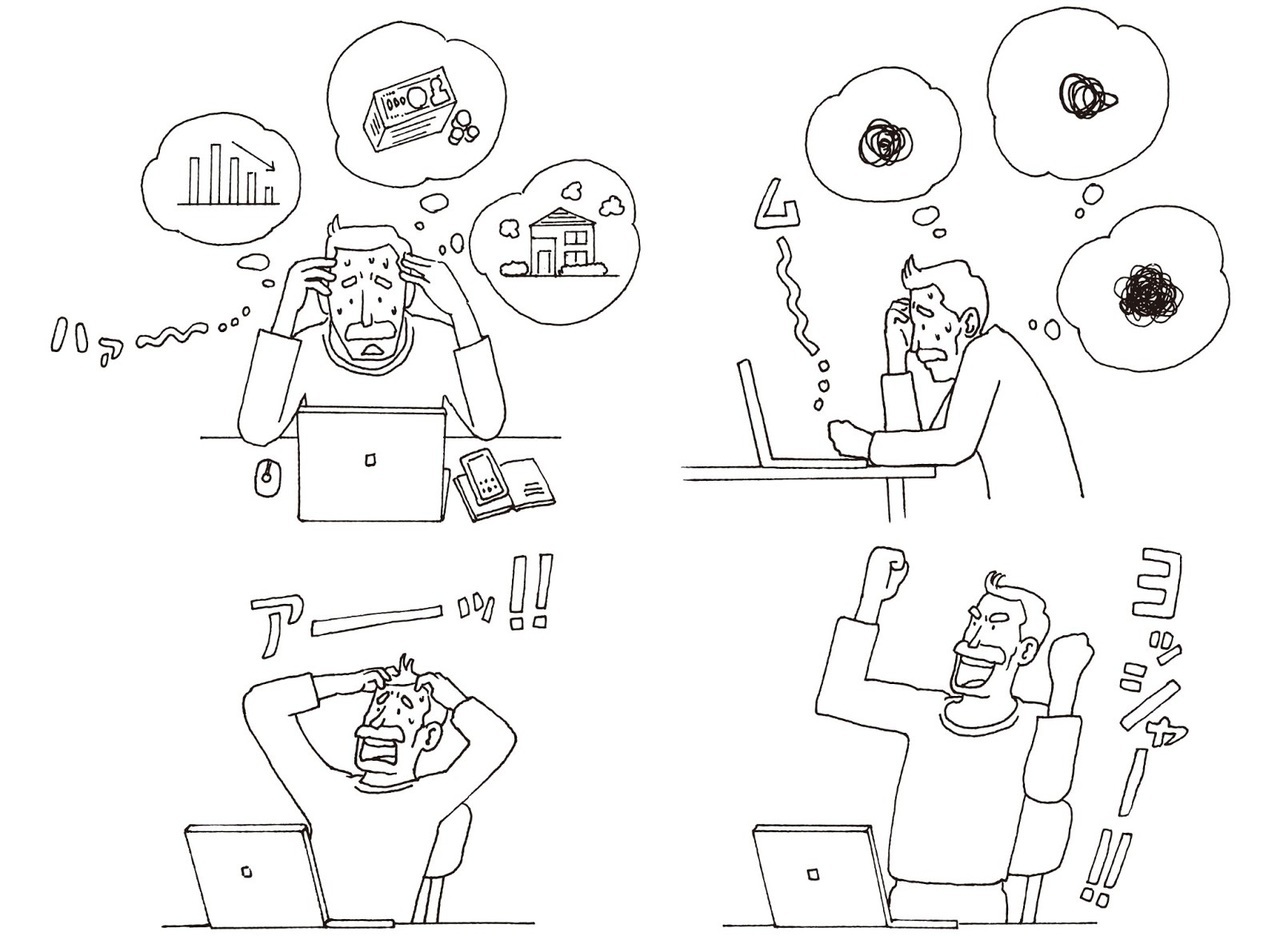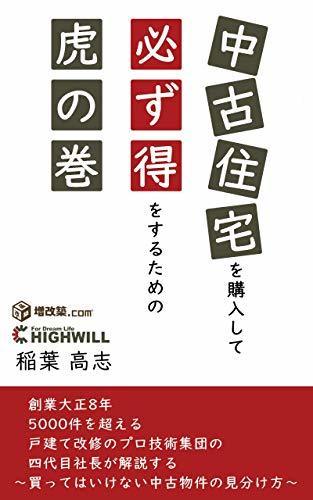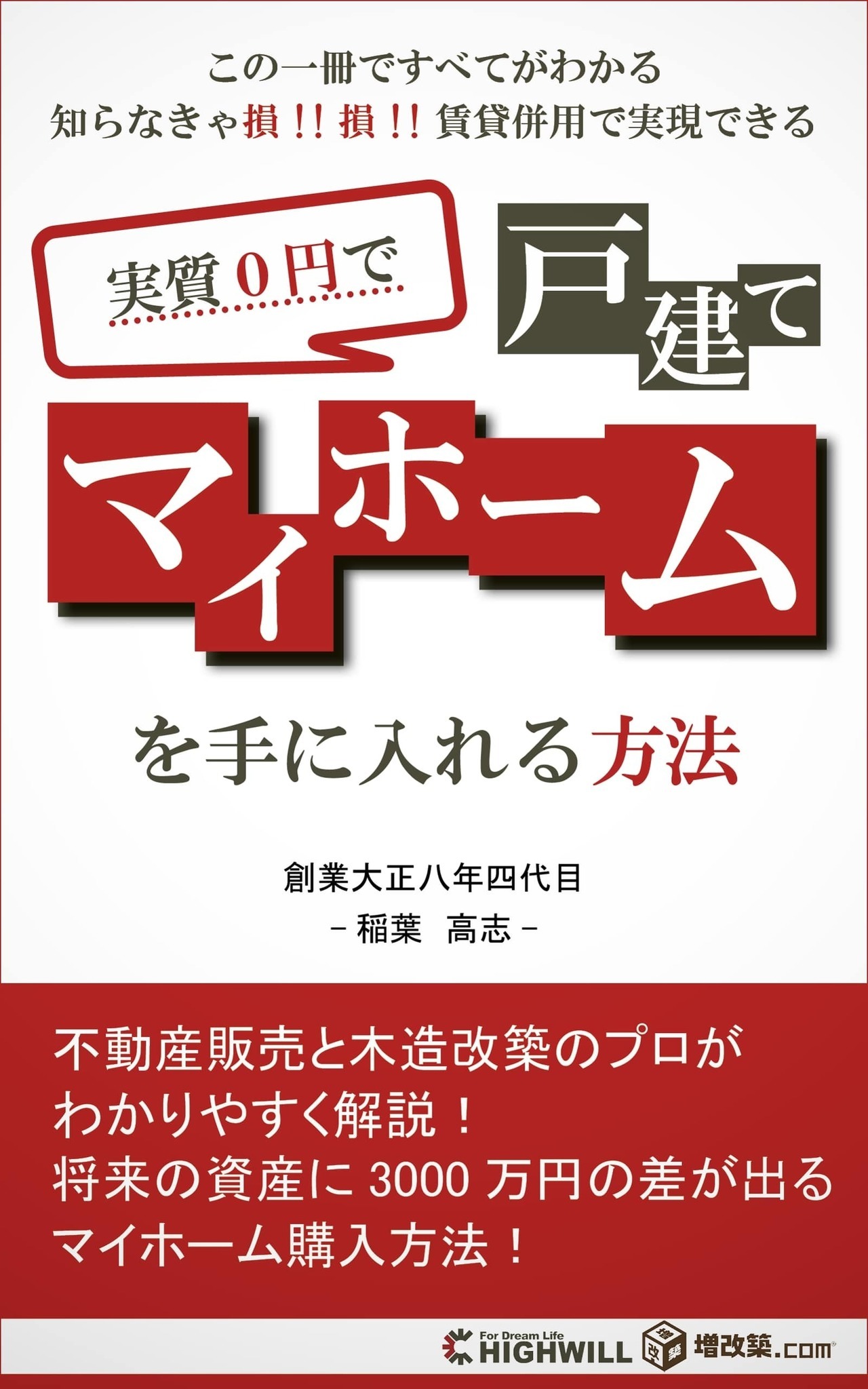更新日:2021-06-26
戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > お役立ち情報>賃貸併用住宅のメリット・デメリット・ローン・間取りについて完全解説>賃貸併用住宅で失敗や後悔しないための方法・成功例を解説

賃貸併用住宅を建築したいけど、失敗したときが怖い!そう考えると手も足も出なくなりますよね。中には失敗した事例や後悔した事例から学ぶこともあるのですが、今回は成功事例を中心に賃貸併用住宅にを建てたオーナーの事例をまとめています。これから賃貸併用住宅を建ててみたいけど失敗や後悔ではなく、成功事例を読みたい!という方は必見の内容となります。
ここまでのお話を聞いただけでは、賃貸併用住宅は、「自宅に住みながら家賃収入を選られて実質タダで家に住める!」というようなメリットのみ!と見えますが、そんなこともありません。
戸建て賃貸併用住宅はオーナーになるという事でもあります。大家として賃貸併用住宅を経営することになりますので戸建て賃貸併用住宅の建築をする前に計画(シミュレーション)をある程度正確に行うようにしておきましょう。
不動産投資としてのシミュレーションとは?
賃貸併用住宅は、厳密にいえば、不動産事業です。住宅ローンを利用しながら、家賃収入を得ることができ、そのままローンに充当できるというような仕組みですが、住宅ローンを利用できない、つまり50%以上が賃貸部分になるような賃貸併用タイプでは住宅ローンの利用はできず、事業用ローンを組み合わせる必要があります。このようなケースでは、いつでもローンを支払える分の収入が得られのかどうかを考えなければなりません。
シミュレーションする項目は主に次の通りです。
●家賃収入とローン返済の収支が見合うか
●賃貸の部屋が空室となった場合のローン返済の可否
●現在ではなく数十年後のローン返済
賃貸併用住宅は自宅の面積を50%以上にすることで住宅ローンを利用できます。そのため、住宅のローンになりますから、基本的に金融機関は、借りられる方の現在の収入などで、返済可能な金額までしか融資を行うことはありません。事業用融資のように、家賃収入を加味した融資はしませんので、基本的には、現在の収入が続く限りは返済できる金額となります。しかし、賃貸経営がうまくいくのかといったシミュレーションを実際にしておくことで、今後のご家族のライフプランも検討しつつ考えることが必要です。
賃貸併用住宅を建てた成功例が実際どんなことなのかを今回は3つピックアップ。どんなことがあげられるのでしょうか。
①賃貸収入だけでローンの返済ができて経済的余裕が生まれた
普段私たちが住んでいる「家」は、家賃ありきでの住宅であり、毎月決まった額の負担があります。家を賃貸併用住宅という形に変更して、家賃での負担を軽減させることが出来るのです。
つまり、毎月12万円分(平均的にファミリー世帯の家賃ですが、)支払っていた家賃を賃貸併用住宅に引っ越したおかげで、家賃収入を得ることが出来、ローンを家賃収入から充当、家賃分は負担がなくなるため、実質0円で衣食住を確保できています。
といった成功例となりますが、月12万円を12か月分支払うとなると、12か月×12万円で、単純な計算ではありますが、144万円分の経済的余裕が生まれます。この144万円分は貯蓄にまわすなど、お子様の教育資金に充てる、レジャーで活用したり、少しでも良い生活を送っていくための資金に回すこともできるため成功事例のひとつでしょう。
②実際に建築を始める前に『不動産投資としてのシミュレーション』を徹底した
この成功事例は、実際に賃貸併用住宅を建築する前に、細かいところまでシミュレーションしたタイプの事例です。
既述にもあるように、シミュレートはある程度明確にしておくべきということは話しましたが、今回のシミュレートでは「ローンなどの金銭シミュレーション」だけでなく、建築をする場所(地域)のシミュレーションもしたことにより、安心して賃貸経営ができるようになったのだとか。
都内や、東京近郊であればある程度人の出入りはあるものの、それ以外のところはイマイチ予想が出来ないということはあるでしょう。そういったときは、それぞれの立地にどれくらいの人が出入りをして、建築をする地域の駅やコンビニなどの利用率を調べてみて下さい。
利用率を調べるときは、関東であればJR東日本や、それぞれの公的機関のサイトに掲載されているデータを確認してみましょう。
3.利用時刻別にみた鉄道利用者数の推計 第II編 (国土交通省より引用)
③周辺にはないような戸建て賃貸併用住宅を建て家賃も周辺相場以上に(神奈川県厚木市M様)
Mさまは、結婚をして1LDKの賃貸住宅に二人で住んでいましたが、このまま家賃を払い続けるだけで資産の残らない賃貸住宅に住み続けることに不毛さを感じたことがきっかけでした。ただ、持ち家となると大きなローンを抱えることになり、35年間も払い続けることができるか不安がありました。さらに将来的に子供が欲しいという希望もあり、出産や子育てで共働きが難しく世帯収入が減った時に生活費がまかなえるか、転勤になった時に自宅はどうなるのかなど、具体的に考えるほど、多くの不安が出てきました。
そこで、メゾネットタイプのデザイン性の高い戸建て賃貸併用住宅を専門としている会社に相談し、建築をしました。過去の空室率等も調査し、優秀であったことが決め手となり、戸建て賃貸併用住宅を選択しました。
<M様プロフィール>
- 夫:28歳 電機メーカー勤務 年収480万円
- 妻:26歳 電機メーカー勤務 年収300万円
- 子ども:なし
<M様の賃貸併用住宅建築データ>
- 土地購入費約50坪/2,500万円
- 建築費(諸費用込み)3,500万円
- 自己資金1,000万円(うち、両親援助700万円)
- 住宅ローン借入額5,000万円
- 金利0.725%(8大疾病付き団体信用保険料含む)
- 返済期間35年
- 毎月のローン返済額13.5万円
- 毎月の家賃収入額14万円
- 実質支払額(毎月のローン返済額-毎月の家賃収入額)5,000円プラス
では、逆に失敗や後悔をしないためにはどうすればよいのでしょうか?
ひとつずつ解説していきます。
①距離の近さが仇に!入居者との関係トラブル
賃貸併用住宅は、賃貸と併用している住宅だからこそ、入居者と大家としての関係が近くなってしまうことはメリットでもありデメリットにもなってしまいます。
アパートやマンションの場合は、大家が近くではあるものの、同じ敷地内ではなかったり、少し遠いところに住んでいるからこそある程度心の距離があります。お互いの干渉もなく、心地よい住まいとなるのですが、賃貸併用住宅は必ず大家も入居者の家が間近という形。
オーナーや大家から、隣人や友人という形に昇格したいという思いも少なからずあるかもしれませんが、そこは抑えておかなければならない距離感なのです。
距離感はある程度開いているからこそ、心地よい関係となり、住まいも心地よいものとなります。しかし、詰めてしまうと途端に「相手の住居が気になる」や「最初はそんなになかったのに、関係を許したらクレームが多くなった」など、あらゆる面で入居者との関係トラブルに発展してしまうのです。
最も、入居者とのトラブル発展につながることのないように、距離感を測れなくなったら、友人に発展するということがあったら、引っ越しをしてもらうなど距離感にまつわる、ある程度の決まり事を作っておくと今後のためになることも考えられるでしょう。
その為、賃貸併用住宅にもさまざまな間取りがあります。このような距離感をうまく保つ配置が出来ているプランを提案できる会社に相談しましょう。
②二世帯住宅に近い大きさだからこそ借入額が大きくなってしまう
賃貸併用住宅は、賃貸併用での住宅であるからこそ世帯が複数(最低2世帯)住んでいる住宅となるため、二世帯住宅に近い要素になるので、建物自体もその分大きくなります。設備機器なども2世帯分必要になってきます。
これは、ローンの借入額が大きくなる直接的な理由とも言えます。
住宅ローンを借り入れる際も、収入が少ないとローンの審査が通らない可能性もあるため、要注意です。ローンの利用が出来ない場合は、家や土地がない限り、賃貸経営そのものが出来ないので、計画の時点で倒れ込む可能性も出てきます。
リスクとして充分に注意しましょう。
③保険に加入は必須!火災保険に入っていなかったことも失敗のもと
住宅の保険に加入はしますか?出来る限り労災などには入るようにして下さい。
家賃併用住宅のオーナーはあなたであり、住宅の保険に入るかどうかの決定権もあなたにあります。
費用の節約を考えて入らないことも、方法のひとつではありますが、住宅としてのリスクを考えるならば、火災保険などの住宅保険には入るようにしておきましょう。ここは重要なポイントです。
賃貸併用住宅で他人と一つ屋根の下でも快適な暮らしをするならば、保険でカバーできるところは、カバーし、リスクの回避を明確に考えることが大切なのです。
賃貸併用住宅を建築する上で後悔しないように気を付けていくポイントは大きく分けて3つです。
一つずつ解説します。
①入居希望者を見つけやすい住宅にすること
賃貸住宅と併用で建築した家は、そもそもの「どんな世帯をターゲットにしているか」が決め手となります。
賃貸併用住宅を建てる際、戸建て賃貸併用住宅であれば、平均が120㎡程度となりマンションやアパートに比べると比較的広く、ファミリ層がターゲットとなります。戸建て賃貸住宅は、賃貸として1世帯を貸す事業でもあります。借りる立場で建物を見てみてください。
チープで住みにくい間取りの建物にあなたは家賃を払って住みたいと思いますか?
自分が住みたいと思える建物であることが戸建て賃貸併用住宅での最大のポイントとなるのです。
あなたが住みたいような間取り、内装、設備を最低限満たしている仕様であることが重要です。
つまり、ファミリー層に受け入れられる間取り、デザイン仕様で建築することが入居希望者を見つけやすいポイントになるのです。
特に次の項目に注意して、どんな世帯に住んでほしいのかを明確にしておきましょう。
-
どの世帯に住みやすい広さか
-
どの地域に建築をしているのか(ファミリー世帯に需要のある施設が近辺にあるのか、単身世帯に需要がある地域なのか等)
②クレームが直接入りやすいからこそ管理はプロにお任せ!
既述にもあるように、賃貸併用住宅は距離感を掴むことが難しいからこそプライベート部分と共用部分は明確に分けなくてはなりませんし、それらの区分けはなかなか難しいことでもあります。
また、オーナーや大家がひとりで家全体を管理するということも難しいことが少なくはありません。
そこでおすすめな方法が、管理はプロに任せるということです。
プロだからこそ、管理をすべきところがイマイチわからなくなってしまって、実は共用部分を超えていた!ということはないので、入居者も安心して管理をお任せできるというわけです。
もし今後クレームが発生する可能性が少しでもあると考えるならば、プロにお任せするのが正攻法となります。
③戸建てタイプの賃貸併用住宅は売る際に、買い手が住宅ローンが使えるのがポイント!
賃貸併用住宅の経営を辞めて、別のところに引っ越したい!と思ってしまうことが出てくる可能性は充分に今後あり得ます。
もちろん、転勤や親の介護などさまざまな要因がありますよね。
そういったときは、住宅を売ればいいと考えている方も少なくはないでしょう。
しかし、賃貸スペースが50%を超えるアパート型の賃貸住宅やマンション型の賃貸併用住宅では、売却の際に買い手が住宅ローンを使えません。
つまり事業用ローンとなりますので売り対象が投資家になってしまうという事です。その為、売却はなかなか難しいことを知っていますか?
戸建て賃貸型の賃貸併用住宅であれば、50%以上が自宅であるため、買われる方も住宅ローンが利用可能となります。しかも賃貸中であれば、購入後すぐに賃料を受け取ることができますので、住宅ローン返済に家賃収入を充当することがスタート段階から可能になるということです。
賃貸併用住宅について9ページにわたって解説しています。
すべてお読みになると賃貸併用住宅についてのさまざまな知識が手に入ります!
▼持ち家のリスクを解消する賃貸併用住宅パーフェクトガイド すべてのコンテンツ▼

< 著者情報 >
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。
創業大正8年5,000件を超える戸建て改修のプロ技術集団が解説する
~賃貸併用住宅で将来資産に3000万の差が出るマイホーム購入方法~
マイホームに住みながら一部の部屋を賃貸用にして、人に貸す。そしてそこから得られる家賃収入を住宅ローンの返済に充てる新しいマイホームの購入方法を解説します。プランニング次第では住宅ローンの返済を毎月ゼロに抑えることも可能です。そして住宅ローン完済後の家賃収入はそのまま収入に。将来3000万以上の差が出るこれからの家の買い方を伝授します。
本書では、賃貸併用住宅の「正しい建て方」「価格相場」「成功例と失敗例」「効果的な間取り」「中古住宅の賃貸併用化方法」「どこに頼むのが最良なのか?」「ローンの組み方」など賃貸併用住宅のあらゆる観点から解説し確実に資産とするためのポイントを解説しています。「このまま家賃を払い続けるのがよいのか…」「賃貸と持ち家はどちらが得なのか?」「マイホームなんて無理…」と考えている、または「住宅ローンを長期間組むことに躊躇してしまう」と思われている共働き夫婦の方、マイホーム購入におけるリスクを払拭する第3の選択肢をご紹介します。
これさえ読めば大丈夫!中古住宅を購入する前に必ず知っておくべき知識
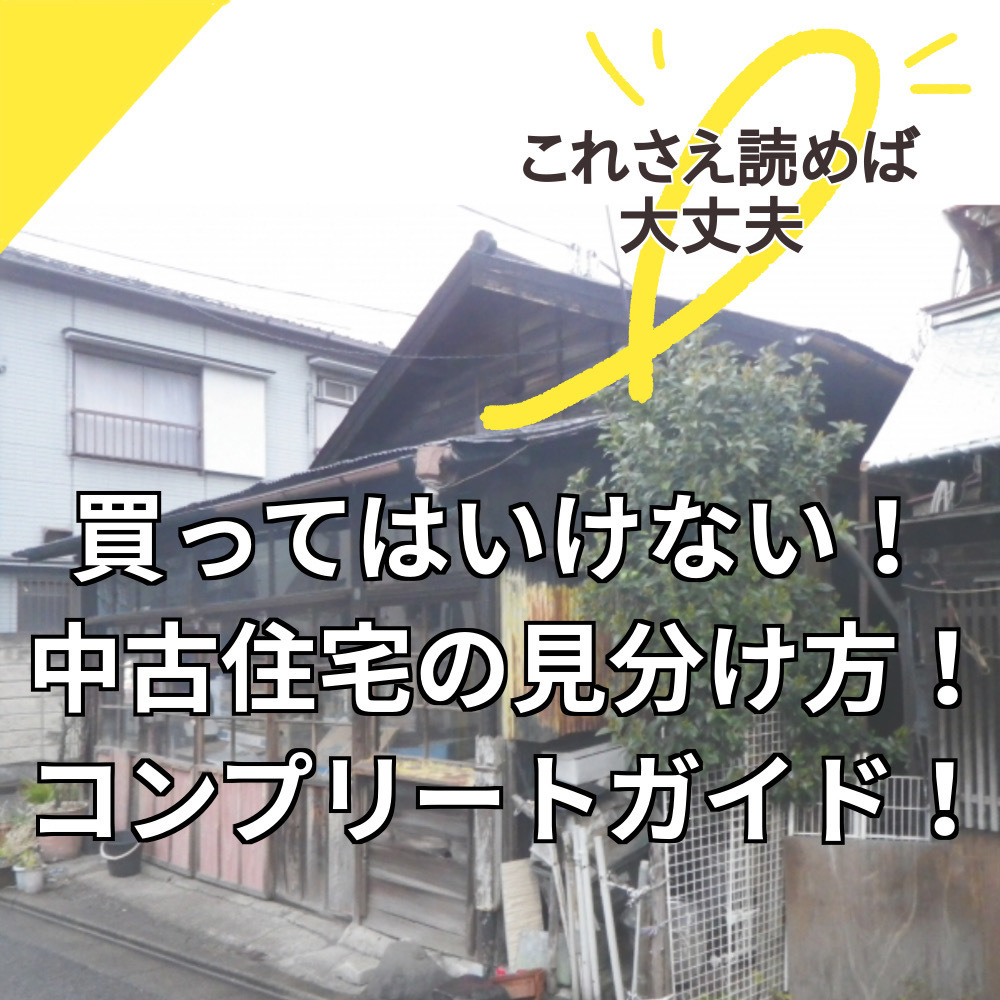
大正八年創業以来「戸建てリノベーション」実績5000件を超える『増改築.com』運営会社であるハイウィル株式会社が中古を買って失敗、後悔しない方法を徹底解説!中古を買う前に必ず読んで欲しい内容をまとめました。
戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・
- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。
耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。
補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)
ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新
※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。
営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)