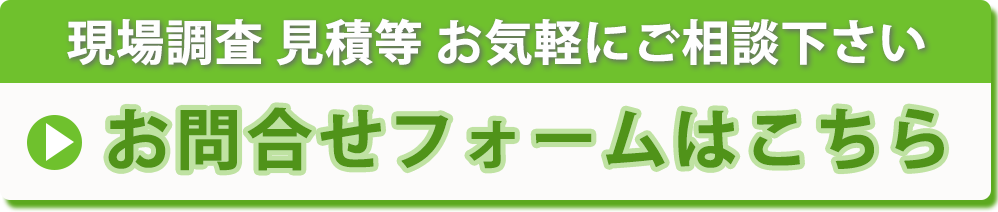戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 断熱改修工事の費用や工期、工事内容について > 外断熱リフォームの費用・効果・施工方法|メリット・デメリット・トラブル対策まで徹底解説
公開日:2024/9/18
外断熱リフォームの費用・効果・施工方法|メリット・デメリット・トラブル対策まで徹底解説

補助金活用で外断熱リフォームのコストパフォーマンスが大幅改善!成功のカギは専門業者選び
ここ数年、外断熱リフォームはかつてコストが高く、導入のハードルが高いとされていました。しかし、政府が提供する次世代省エネ建材支援事業(断熱リフォーム補助金)の活用により、費用負担が大幅に軽減され、今ではコストパフォーマンスの高いリフォームが実現可能になっています。
この補助金制度を上手に利用することで、外断熱リフォームの初期費用を抑えつつ、高い断熱性能と省エネ効果を得ることができます。特に、断熱改修は長期的な光熱費削減や住環境の快適さを大きく向上させるため、経済的にも大きなメリットがあります。
補助金活用のタイミングが重要
外断熱リフォームを行う際は、補助金の申請期間や制度内容をしっかり確認し、適切なタイミングで計画を立てることが重要です。補助金制度には申請期間や条件が定められており、年度ごとに予算枠が設定されています。そのため、タイミングを逃さずに準備を進めることが、コスト削減の大きなポイントになります。
専門業者の選定が成功のカギ
外断熱リフォームを成功させるためには、施工する業者選びが非常に重要です。断熱性能を最大限に引き出すためには、断熱改修に特化した経験豊富な業者や、気密工事の精度が高い会社を選ぶことが推奨されます。特に、外断熱リフォームの経験値が高い業者は、補助金制度を熟知していることが多く、補助金申請のサポートや適切な施工プランを提案してくれるケースが多いです。
具体的には、以下の点に注目して業者を選ぶことが重要です。
- 断熱改修の実績が豊富か
- 気密性の高い施工が可能か
- 外断熱リフォームの経験が豊富であるか
まとめ:外断熱リフォームで省エネと快適さを手に入れるために
補助金の活用により、従来はコスパが悪いとされていた外断熱リフォームも、今では費用対効果の高い選択肢となっています。適切な時期に補助金を利用し、断熱と気密の専門知識を持つ業者に相談することで、快適な住環境と省エネ効果を両立した外断熱リフォームが実現できます。
外断熱リフォームを検討している方は、補助金の条件や時期をしっかり確認し、信頼できる業者と相談しながら計画を進めることが成功への第一歩です。
1. 外断熱リフォームの基本的な概要と特徴
外断熱リフォームとは、建物の外側に断熱材を取り付けることで、室内の温度環境を快適に保ち、省エネルギー効果を高めるリフォーム方法です。外壁全体を断熱材で覆うため、建物全体の断熱性能が向上し、夏は外部からの熱を遮断し、冬は室内の暖かさを逃がさない効果が得られます。
外断熱リフォームは、断熱性能の向上に加えて、建物の保護や寿命の延長といったメリットも提供します。特に、屋外からの紫外線や雨風による劣化を防ぐため、建物の外装を長期間にわたって良好な状態に保つことができるのです。これにより、外壁のメンテナンス頻度が減少し、長期的なコスト削減にもつながります。
外断熱リフォームの主な特徴
-
断熱性能の向上
建物全体を外部から断熱材で覆うため、壁や天井、床などから熱が逃げることがなくなります。これにより、室内温度の急激な変化を抑え、年間を通して快適な温度を保つことができます。 -
結露の防止
外断熱は建物全体を包むことで、壁内の温度変化を抑え、結露の発生を防ぐ効果があります。結露はカビやダニの発生原因となり、建物の劣化や健康被害を引き起こすリスクがあるため、この防止効果は非常に重要です。 -
建物の耐久性の向上
外断熱によって、外壁が直接的な外気温の影響を受けにくくなり、外壁の収縮や膨張が抑えられます。その結果、ひび割れや剥離などの劣化を防ぎ、建物全体の耐久性が向上します。 -
エネルギー効率の向上
外断熱リフォームにより、冷暖房の効率が向上し、室内の温度が安定するため、エネルギーの使用量が削減されます。これにより、光熱費の削減が期待でき、省エネ住宅としての価値も高まります。 -
既存住宅でも施工可能
外断熱リフォームは、既存の住宅に対しても容易に施工が可能です。特に、外壁の塗り替えや修繕を行う際に併せて実施することで、工期の短縮やコスト削減にもつながります。
2. 内断熱との違い
内断熱とは、建物の内部(壁の内側)に断熱材を施工する方法です。外断熱とは異なる特徴を持ち、それぞれにメリットとデメリットがあります。外断熱リフォームを検討する際には、内断熱との違いを理解し、自宅に最適な断熱方法を選ぶことが重要です。
内断熱の特徴
-
コストが比較的低い 内断熱は外断熱に比べ、材料費や施工費が低い傾向にあります。特に、室内のリフォームや改修工事を行う際に併せて施工することが多いため、初期費用が抑えられるのがメリットです。
-
施工が簡単 内断熱は、建物の内側に断熱材を設置するため、外壁の修繕を伴わないことが多く、施工が比較的簡単です。そのため、天候の影響を受けにくく、工期も短縮されやすいのが特徴です。
-
結露リスクの増加 内断熱の場合、外気と接触する外壁部分が冷やされやすくなり、壁の内部で結露が発生する可能性が高まります。特に、湿気がこもりやすい環境では、結露がカビや腐食の原因となり、建物の寿命を縮めるリスクがあります。
外断熱と内断熱の違い
| 項目 | 外断熱 | 内断熱 |
|---|---|---|
| 断熱効果 | 高い(建物全体を覆うため効率が良い) | 中程度(壁内部のみのため効果が限定的) |
| 結露リスク | 低い(建物内部の温度変化が少ない) | 高い(壁内での結露リスクが高い) |
| 建物の保護 | 高い(外壁の劣化を防ぎ建物を守る) | 低い(外壁は劣化の影響を受けやすい) |
| 施工の手軽さ | やや手間がかかる | 手軽(内装工事と併せて行いやすい) |
| 費用 | やや高い(高性能断熱材を使用するため) | 低い(材料費・施工費が抑えられる) |
3. 外断熱が選ばれる理由
内断熱よりも外断熱が選ばれることが多い理由として、長期的な効果や建物保護に優れている点が挙げられます。外断熱は、断熱性能を大幅に向上させるだけでなく、建物全体の耐久性を高め、エネルギーコストの削減につながります。初期費用は内断熱より高いものの、長期的な視点で見た場合、省エネ効果とメンテナンスコストの削減により、トータルコストが抑えられる可能性があります。
特に、**次世代省エネ建材支援事業(断熱リフォーム補助金)**など、政府の補助金制度を活用することで、外断熱リフォームにかかる費用負担を軽減できる点も注目すべきポイントです。
結論:外断熱リフォームで快適な住まいと省エネ効果を実現
外断熱リフォームは、建物全体を断熱材で覆うことで、断熱性能を大幅に向上させ、快適な住環境とエネルギー効率の改善を実現する方法です。内断熱と比較して初期コストはやや高いものの、長期的には光熱費の削減や建物の耐久性向上といった利点があるため、多くの住宅オーナーに選ばれています。
また、外断熱リフォームを検討する際には、補助金制度の活用も大きなポイントです。例えば「次世代省エネ建材支援事業」では、外断熱リフォームに適した高性能断熱材が補助対象となっており、コスト負担を大幅に軽減することが可能です。これにより、効率的な省エネ住宅の実現がさらに身近なものとなっています。
外断熱リフォームを通じて、より快適で持続可能な住環境を手に入れましょう。
外断熱リフォームの費用と予算の目安
外断熱リフォームは、建物全体を外側から断熱材で覆うことで、快適な室内環境と省エネ効果を得られるリフォーム方法です。しかし、その施工にはさまざまな要素が絡んでくるため、費用が大きく変動する可能性があります。この記事では、外断熱リフォームにかかる平均的な費用や、費用に影響する要因、そしてコストを抑えるためのポイントについて解説します。
1. 外断熱リフォームにかかる平均的な費用
外断熱リフォームにかかる費用は、建物の規模や使用する断熱材の種類、施工内容により大きく異なります。一般的に、1平方メートルあたりの費用は約15,000円〜30,000円が目安となります。たとえば、延床面積が100平方メートルの住宅では、外断熱リフォーム全体の費用は150万円〜300万円ほどが想定されます。
ただし、これはあくまで目安であり、以下に挙げる要因によって費用が大幅に変動する可能性があります。
2. 費用に影響する要因
(1) 建物の規模と構造
建物の規模が大きいほど、断熱材や施工にかかるコストが増加します。たとえば、平屋の建物よりも2階建てや3階建ての住宅のほうが外壁面積が広いため、費用は高くなります。また、複雑な形状の建物や、デザイン性の高い建物は施工に手間がかかるため、工賃が増加する場合があります。
(2) 使用する断熱材の種類
外断熱リフォームでは、さまざまな断熱材が使用されます。代表的なものにはEPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)、XPS(押出法ポリスチレンフォーム)、発泡ウレタンなどがあり、それぞれに性能や価格が異なります。たとえば、発泡ウレタンは断熱性能が高い一方でコストがかかるため、予算によって最適な材料を選ぶ必要があります。また、近年では高性能で長期的なコストパフォーマンスが優れているアキレス キューワンボードなどが注目され、補助金の対象となることから、総費用を抑える効果も期待できます。
(3) 既存の外壁の構造
外断熱リフォームでは、既存の外壁の構造が通気工法か非通気工法かによって、施工内容や費用が大きく異なります。
-
通気工法の場合
通気工法で施工されている建物は、外壁と断熱材の間に通気層が設けられており、湿気の逃げ道を確保しています。この場合、外断熱リフォームでは、通気層を遮断する施工が必要です。外壁材の種類によっては、この通気層の遮断が難しいため、既存の外壁を一部またはすべて解体しなければならない場合があります。この解体作業が発生すると、解体費用が追加され、全体のコストが増加します。 -
非通気工法の場合
一方、既存の外壁が通気工法でない場合、断熱材を直接張ることが可能です。この場合は、外壁の解体作業が不要なため、工期が短く、費用を抑えることが可能です。
(4) 既存の外壁材を解体するかどうか
既存の外壁材を解体するかどうかは、費用に大きな影響を与える要素です。解体作業を行う場合、追加の人件費や廃材処理費用が発生します。解体を伴うリフォームでは、通常よりも高額な見積もりとなるため、できるだけ既存の外壁を活かせる施工方法を検討することが、費用を抑えるポイントとなります。
また、建物の老朽化具合によっても判断が異なります。外壁が劣化している場合には、断熱リフォームと同時に外壁の補修や交換が必要になるため、その分費用が上乗せされることを理解しておく必要があります。
(5) 補助金の利用
次世代省エネ建材支援事業などの補助金を利用することで、外断熱リフォームの費用を大幅に抑えることができます。この補助金制度では、断熱材や高性能ガラスなど、省エネルギー性能の高い建材を使用したリフォームが対象となり、施工費用の一部が補助されます。これにより、初期投資が軽減され、トータルでのコストパフォーマンスが向上します。
3. 費用を抑えるためのポイント
外断熱リフォームの費用を抑えるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
(1) 既存の外壁の活用を検討する
既存の外壁を解体せずに施工できるかどうかは、費用削減の大きなポイントです。建物が通気工法でない場合や、外壁の状態が良好である場合には、既存の外壁をそのまま活用し、断熱材を直接張る方法を検討しましょう。これにより、解体費用や工期を短縮し、コストを抑えることが可能です。
(2) 断熱材選びはコストパフォーマンスを重視
断熱材は外断熱リフォームの要となるため、性能だけでなくコストパフォーマンスを重視して選ぶことが大切です。例えば、アキレス キューワンボードのような高性能な断熱材は、初期費用が高いものの、補助金の対象であり、長期的な省エネ効果を考慮すると費用対効果が高い選択肢となります。
(3) 補助金制度をフル活用する
外断熱リフォームにかかる費用を抑えるためには、補助金制度を最大限に活用することが有効です。補助金申請の条件や手続き方法をよく確認し、対象となる断熱材や施工方法を採用することで、補助金を利用して費用を大幅に削減できます。また、補助金制度は年度ごとに変動するため、事前にリサーチし、タイミングを逃さず申請することが重要です。
(4) 専門業者への相談で最適な施工プランを選ぶ
外断熱リフォームは、新築とは異なり、既存の建物の状態に合わせたノウハウが必要です。そのため、経験豊富な業者に相談し、最適な施工プランを提案してもらうことが、費用を抑えるための近道となります。特に、断熱改修や外断熱リフォームの専門業者を選ぶことで、効果的かつ無駄のない施工を実現できます。
まとめ
外断熱リフォームは、建物の断熱性能を高め、省エネ効果を実現するための優れたリフォーム方法です。しかし、費用は建物の規模、使用する断熱材、既存の外壁の状態などによって大きく変動します。特に、外壁が通気工法か非通気工法かによって施工内容が異なり、それが費用に大きく影響します。
費用を抑えるためには、既存の外壁を活用するか、適切な断熱材を選ぶこと、さらには補助金制度を利用することが重要です。専門業者に相談し、建物に合った最適なプランを選ぶことで、外断熱リフォームのコストパフォーマンスを最大化しましょう。
外断熱リフォームは、建物の外側に断熱材を施すことで、断熱性能を大幅に向上させ、快適な住環境を作り出すための工事です。特に、冬は室内の暖かさを逃がさず、夏は外からの熱を遮断することで、1年を通じて温度変化の少ない快適な住まいを実現します。また、断熱性能が向上することで、エネルギー効率が上がり、光熱費の削減にもつながります。
この章では、外断熱リフォームによる具体的な断熱性能の改善効果、断熱効率の向上と省エネ効果、そして快適な住環境を実現するためのポイントについて解説します。さらに、外断熱リフォームにおいて考慮すべきサッシの交換や床・天井の断熱についても詳しく説明します。
1. 外断熱リフォームによる断熱性能の改善
外断熱リフォームの最大のメリットは、建物全体を外側から断熱材で包み込むことで、断熱性能を大幅に改善できる点です。これは、建物内部の温度を外気の影響から遮断し、熱の損失や侵入を防ぐ役割を果たします。
外皮計算の重要性
外断熱リフォームの効果を正確に理解するためには、建物全体の**断熱性能(外皮性能)**を計算する必要があります。外皮性能とは、建物の外壁、床、最上階の天井、サッシなど、建物全体の断熱性を数値化したもので、これらの要素をトータルで評価して断熱性能を確認します。
特に、断熱性能に影響を与える要素としては、以下の4つが重要です。
- 外壁の断熱
- 最上階の天井の断熱
- 床の断熱
- サッシの断熱
外断熱リフォームを行う際は、これらの要素をすべて考慮し、外皮計算に基づいた断熱性能の向上を目指すことが重要です。
2. 断熱効率の向上と省エネ効果
断熱性能が向上すると、冷暖房の効率が劇的に改善され、エネルギー消費量が削減されます。外断熱リフォームでは、建物全体を外側から包むことで、室内の熱が逃げにくく、外からの熱も入りにくい環境が作られるため、冷暖房の使用頻度や強度を抑えることができます。これにより、光熱費の削減だけでなく、CO2の排出量も削減され、環境にも優しい住まいが実現します。
外断熱リフォームによるエネルギー効率の改善
例えば、一般的な木造住宅の場合、外壁から約30%、窓から25%、床から10%、天井から15%の熱が逃げていくとされています。これを外断熱リフォームでカバーすることで、冷暖房の効率が上がり、年間を通じて大幅な省エネ効果が期待できます。特に、サッシやガラスの断熱性能を向上させることにより、外壁の断熱だけでなく、建物全体のエネルギー効率を飛躍的に向上させることができます。
3. 冬暖かく、夏涼しい快適な住環境の実現
外断熱リフォームにより、室内の温度が外気温に左右されにくくなるため、冬は暖かく、夏は涼しい快適な住環境が実現します。これは、単に断熱性能が向上するだけでなく、冷暖房の使用頻度が減るため、室内の空気が乾燥しにくくなったり、湿気がこもりにくくなったりする効果もあります。
4. 外断熱リフォーム時のサッシ交換の重要性
外断熱リフォームを行う際、サッシ(窓枠やガラス)の断熱性能にも注目する必要があります。窓は、外壁に比べて熱の出入りが多いため、外断熱リフォームだけでなく、サッシの交換も合わせて検討することが非常に重要です。
高断熱の外壁を作り上げても、サッシが旧式のままだと、そこから熱が逃げてしまい、外断熱の効果が半減してしまいます。そのため、外断熱リフォームと同時に、断熱性能の高い複層ガラスや樹脂サッシに交換することが推奨されます。
サッシ交換が断熱性能に与える影響
窓の断熱性能を高めることで、外断熱と相乗効果が生まれ、さらに断熱性能が向上します。具体的には、複層ガラスやLow-Eガラス、アルゴンガス入りのガラスを使用することで、外気温が厳しい環境下でも室内の温度が安定し、冷暖房効率を高めることができます。
5. 二階建て・三階建て住宅の天井断熱
二階建てや三階建ての住宅では、最上階の天井の断熱が非常に重要です。外断熱リフォームを行う際には、外壁だけでなく、最上階の天井(場合によっては下屋根の天井)の断熱性能を改善することも考慮すべきです。
特に、最上階の天井は外気との接触面積が広く、そこから熱が逃げやすいため、適切な断熱材を使用して断熱性能を向上させることが重要です。断熱材の種類や厚さによっても断熱性能は変わりますが、効果的な断熱を行うことで、夏場の強い日差しや冬場の寒さから室内を守ることができます。
6. 一階の床断熱の考慮
外断熱リフォームを行う際、一階の床の断熱も忘れてはならない要素です。床からの冷えは、特に冬場に大きな問題となりやすく、断熱が不十分な場合、床から冷たい空気が室内に侵入し、暖房の効率を下げてしまいます。
一階の床下に断熱材を追加することで、足元からの冷えを防ぎ、快適な温度環境を維持することができます。床断熱の施工には、床下に断熱材を敷く方法や、床材を変更する方法などがあります。既存の床材をそのまま利用する場合は、床下への施工が主流ですが、リフォームの際には床材自体を高断熱のものに変更することも検討する価値があります。
7. 外皮計算と総合的な断熱性能の向上
最後に、外断熱リフォームの効果を最大限に引き出すためには、建物全体の断熱性能を評価するための外皮計算を行うことが重要です。外皮計算では、外壁、床、最上階の天井、サッシなど、建物の外周部分(外皮)の断熱性能を総合的に計算します。
外皮計算に基づくリフォームの提案
外皮計算によって、どの部分からの熱損失が大きいかが明確になるため、外断熱リフォームを行う際には、その結果を元に最も効果的な施工箇所を決定することができます。特に、外壁だけでなくサッシや天井、床の断熱強化も合わせて検討することで、建物全体の断熱性能を大幅に向上させ、省エネ効果と快適な住環境を実現することが可能です。
結論:外断熱リフォームで建物全体の断熱性能を強化し、快適な住まいを実現
外断熱リフォームは、断熱性能の向上により、夏も冬も快適な室内環境を提供し、省エネ効果を高めるリフォーム方法です。外壁だけでなく、サッシの交換や、最上階の天井、一階の床の断熱強化も重要な要素です。外皮計算に基づいた総合的な断熱性能の向上を目指し、外断熱リフォームを行うことで、長期的な光熱費削減と快適な住環境が実現できます。
外断熱リフォームは、建物の外側に断熱材を設置し、建物全体を包み込むことで断熱性能を向上させるリフォーム方法です。しかし、外断熱を施工する際には、建物の構造や地域の規制、使用する断熱材によって施工方法が異なります。また、使用する断熱材が補助金の対象であるか、準防火地域では防火性能を満たす外壁仕上げ材を使用する必要があるなど、いくつかの注意点があります。
この記事では、代表的な外断熱リフォームの施工方法を紹介し、各施工方法のメリット・デメリット、施工の流れと工期の目安について詳しく解説します。また、補助金の対象となる断熱材や、特殊な施工条件が必要な場合についても触れます。
1. 代表的な外断熱リフォームの施工方法
(1) EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)
EPS(Expanded Polystyrene)は、ビーズ状の発泡ポリスチレンを形成した断熱材です。軽量で施工が容易なため、一般的な外断熱リフォームに広く使用されています。EPSは断熱性能が安定しており、費用対効果が高い断熱材の一つです。
- メリット
- 軽量で扱いやすい
- コストパフォーマンスが良い
- 施工が簡単で短期間で済む
- デメリット
- 耐火性能が低く、準防火地域では使用が制限される場合がある
- 高湿度の環境では吸水性があり、湿気に弱い
(2) 硬質発泡ウレタン
硬質発泡ウレタンは、断熱性能に優れ、経年劣化が少ない高性能断熱材です。硬質発泡ウレタンは、吹き付け型として施工される場合が多く、隙間なく断熱材を充填できるため、外断熱リフォームにおいては非常に優れた素材です。また、準防火地域でも使用できる防火性能を満たす外壁仕上げ材と組み合わせることで、火災リスクを抑えることが可能です。
-
メリット
- 優れた断熱性能(熱伝導率が非常に低い)
- 隙間なく施工できるため、気密性が高まる
- 長期的な断熱性能を保持する
- 防火性能を持つ外壁仕上げ材と組み合わせれば準防火地域でも使用可能
-
デメリット
- EPSよりもコストが高い
- 吹き付け施工には専用機材が必要で、専門技術が求められる
(3) アキレス キューワンボード
アキレス キューワンボードは、硬質ウレタンフォームにガスバリア層を設けることで、長期的に高い断熱性能を維持することができる高性能断熱材です。この断熱材は、次世代省エネ建材支援事業の補助金の対象となるため、外断熱リフォームにおいて非常に有利な選択肢です。また、防火性能も高く、準防火地域での使用にも適しています。
- メリット
- 高い断熱性能を長期間維持できる
- 補助金の対象となる可能性があるため、費用負担を軽減できる
- 軽量で施工が容易
- 防火性能が高く、準防火地域でも対応可能
- デメリット
- EPSや硬質発泡ウレタンよりもコストがやや高い
2. 各施工方法のメリット・デメリット
外断熱リフォームを行う際には、使用する断熱材によって施工方法が異なります。それぞれの施工方法には、メリットとデメリットがありますので、建物の条件やリフォームの目的に応じて最適な方法を選択することが重要です。
通気工法との関係
通気工法とは、外壁と断熱材の間に空気の流れを確保し、湿気を外に逃がすための施工方法です。多くの住宅では、この通気層が設けられていますが、外断熱リフォームを行う際には、この通気層を遮断する必要がある場合があります。例えば、既存の外壁が通気工法の場合、そのまま断熱材を貼ると湿気が滞留し、断熱効果が下がることがあります。この場合、通気層を遮断し、適切に断熱材を施工する必要があります。
一方、通気層がない建物では、断熱材を直接貼ることができ、施工が比較的簡単です。建物の構造によっては、外壁を解体せずに断熱材を施工することも可能で、工期や費用を抑えることができます。
3. 特殊なケースでの施工方法
土壁仕上げの築古住宅への施工
土壁を使用している築古住宅では、通常の外断熱施工とは異なる手法が必要です。土壁は湿度を調整する効果があるため、可能な限りその機能を生かしつつ、外部からの断熱効果を高める必要があります。こうした場合、外部に胴縁を打ち込み、発泡ウレタンを充填する施工方法が有効です。この方法により、土壁の特性を活かしつつ、外部から断熱性能を向上させることができます。
外壁を剥離して硬質発泡ウレタンを充填する工法(内断熱)
建物のロケーションや外壁の状態によっては、外断熱パネルが使えない場合もあります。特に、湿度や風通しが悪い地域では外断熱パネルの効果が期待できないことがあります。この場合、外壁を部分的に剥離して、硬質発泡ウレタンを充填する内断熱工法が有効です。これにより、外壁を解体せずに断熱性能を向上させることが可能です。
4. 施工の流れと工期の目安
外断熱リフォームの施工は、通常以下のような流れで進行します。
-
既存の外壁の確認
- 外壁の状態や通気工法の有無を確認し、解体が必要かどうかを判断します。
-
断熱材の選定
- EPS、硬質発泡ウレタン、アキレス キューワンボードなど、建物の条件に合った断熱材を選定します。
-
外壁の下地処理
- 外壁の剥離や下地の補修を行い、断熱材を取り付けるための準備を行います。
-
断熱材の取り付け
- 選定した断熱材を外壁に取り付けます。パネル式の断熱材はそのまま貼り付けますが、吹き付け型の発泡ウレタンは専用機材で吹き付け施工を行います。
-
外壁仕上げ材の施工
- 外断熱材の上に外壁仕上げ材を施工します。特に準防火地域では、防火性能を満たす外壁仕上げ材を使用する必要があります。
-
仕上げと確認
- 仕上げ処理を行い、断熱効果や気密性を確認して施工完了です。
工期の目安
外断熱リフォームの工期は、建物の規模や外壁の状態、使用する断熱材によって異なります。一般的には2週間から1ヶ月程度が目安となります。既存の外壁を解体する場合や、複雑な構造の建物の場合は、工期が延びることがあります。
5. 実績のある会社選びが成功のカギ
外断熱リフォームは、建物の断熱性能を向上させるために非常に効果的ですが、施工には専門的な知識と技術が必要です。特に、通気工法や防火性能の確認、補助金申請のサポートなど、さまざまな要素を考慮しながら施工を進める必要があります。
そのため、外断熱リフォームを成功させるためには、実績のある専門業者に依頼することが最も重要です。特に、断熱改修に特化した業者は、外断熱の施工ノウハウを持っているため、建物に最適な断熱材を提案し、適切な施工を行うことができます。補助金の申請手続きに詳しい業者に依頼することで、リフォーム費用の負担を軽減できる可能性もあります。
まとめ
外断熱リフォームは、断熱性能を大幅に向上させ、快適な住環境と省エネ効果を実現するための効果的な方法です。しかし、建物の構造や地域の規制に応じた適切な施工方法を選ぶことが重要です。EPS、硬質発泡ウレタン、アキレス キューワンボードなど、さまざまな断熱材を選定し、防火性能や補助金対象であるかの確認を行いながら、信頼できる業者に依頼して計画を進めましょう。
外断熱リフォームは、建物の断熱性能を大幅に向上させ、快適な室内環境と省エネ効果をもたらすリフォーム方法です。しかし、使用する断熱材によって性能やコスト、耐久性に差があるため、適切な断熱材を選ぶことが重要です。この章では、外断熱リフォームで使用される代表的な断熱材であるEPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)、XPS(押出法ポリスチレンフォーム)、発泡ウレタン、そして注目のアキレス キューワンボードについて、それぞれの特徴や性能、コストパフォーマンスを比較しながら、材料選びのポイントを解説します。
1. EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)
**EPS(Expanded Polystyrene)**は、ビーズ状の発泡ポリスチレンを使用した断熱材で、外断熱リフォームでよく使用される素材の一つです。軽量で施工しやすく、コストも比較的安価なため、外断熱リフォームの初期コストを抑えるのに適しています。
-
断熱性能
EPSの断熱性能は、熱伝導率0.034〜0.038 W/m・Kと、一般的な断熱材の中でも中程度の断熱効果を持ちます。外壁全体に取り付けることで、一定の断熱効果を発揮し、冷暖房効率を高めることができます。 -
コスト
EPSは外断熱材の中でも比較的安価で、1平方メートルあたりの価格が低く、初期費用を抑えたい場合に選ばれます。外断熱リフォーム全体の費用を抑えつつ、断熱性能を確保したい場合に適しています。 -
耐久性と経年劣化
EPSは軽量で耐水性が高いため、屋外での使用にも適していますが、湿気の多い環境では経年劣化が進む場合があります。また、防火性能が低いため、準防火地域での使用には制限があることも留意すべきポイントです。
2. XPS(押出法ポリスチレンフォーム)
**XPS(Extruded Polystyrene)**は、EPSよりも高い密度を持ち、断熱性能や耐水性が向上した断熱材です。押出成形により、均一な構造を持ち、断熱性が高く安定した性能を発揮します。
-
断熱性能
XPSの断熱性能は、熱伝導率0.028〜0.034 W/m・Kで、EPSよりも優れた断熱効果を発揮します。特に、寒冷地や湿気の多い地域では、XPSの断熱性能が有効です。 -
コスト
EPSに比べるとややコストが高いですが、断熱性能を重視する場合には効果的です。外断熱リフォームにおいて、高い断熱効果を求めるケースで選択されることが多いです。 -
耐久性と経年劣化
XPSは、EPSよりも高い耐久性を持ち、湿気や経年劣化に強いため、長期間にわたって安定した断熱性能を提供します。また、湿気の多い環境でも、劣化が少ないため、長期的なコストパフォーマンスが優れています。
3. 発泡ウレタン
発泡ウレタンは、現場で直接吹き付けるタイプの断熱材で、隙間なく施工できるため、高い気密性と断熱性能を実現できる素材です。吹き付けることで、凹凸のある場所や狭い空間でもしっかりと断熱材を充填できるため、特に複雑な形状の外壁に適しています。
-
断熱性能
発泡ウレタンの断熱性能は非常に高く、熱伝導率0.020〜0.024 W/m・Kで、最も高い断熱効果を発揮します。隙間なく施工できるため、気密性が重要な外断熱リフォームに最適です。 -
コスト
発泡ウレタンは、吹き付け施工という特性上、EPSやXPSよりもコストが高くなります。また、施工には専用の機材が必要で、施工する業者の技術力によって仕上がりに差が出ることがあります。 -
耐久性と経年劣化
発泡ウレタンは、高い耐久性を持ち、経年劣化が少ないことが特徴です。湿気や温度変化にも強く、長期間にわたって安定した断熱性能を提供します。
4. アキレス キューワンボード(補助金対象商品)
アキレス キューワンボードは、断熱材として優れた性能を持ち、外断熱リフォームで特に推奨される製品です。硬質ウレタンフォームにガスバリア層を持たせることで、長期間にわたり高い断熱性能を維持することができます。このボードは、次世代省エネ建材支援事業の補助金対象商品でもあり、コスト面でも大きなメリットがあります。
-
断熱性能
アキレス キューワンボードは、熱伝導率0.020〜0.021 W/m・Kと、発泡ウレタンに匹敵する非常に高い断熱性能を持っています。特に、ガスバリア層により、経年劣化による性能低下が少なく、長期的に高い断熱効果を維持できる点が特徴です。 -
コスト
発泡ウレタンやXPSと比較して初期費用はやや高めですが、補助金制度の対象となっているため、総コストを抑えることが可能です。また、断熱性能の高さから、冷暖房費の削減効果が大きく、長期的なコストパフォーマンスに優れています。 -
耐久性と経年劣化
アキレス キューワンボードは、硬質ウレタンフォームにガスバリア層が追加されているため、経年劣化が非常に少なく、長期間にわたって安定した断熱性能を提供します。湿気や温度変化にも強く、外断熱リフォームにおいて非常に信頼性の高い選択肢です。
5. 材料選びの際に考慮すべきポイント
外断熱リフォームを成功させるためには、使用する断熱材の選定が重要です。断熱材の選び方には、以下のポイントを考慮する必要があります。
(1) 断熱性能と省エネ効果
断熱材を選ぶ際に最も重要なのは、その断熱性能です。断熱性能が高いほど、冷暖房効率が上がり、光熱費の削減につながります。特に、アキレス キューワンボードのように、熱伝導率が低く、長期にわたって性能を維持できる断熱材は、省エネ効果が高いため、トータルでのコストパフォーマンスも優れています。
(2) コストパフォーマンスと補助金活用
外断熱リフォームでは、初期費用がかかることが一般的です。そのため、断熱材の選定にはコストパフォーマンスも重要な要素となります。アキレス キューワンボードは、補助金の対象であるため、初期費用を抑えることができ、さらに長期的な省エネ効果により、トータルでの費用対効果が非常に高い選択肢です。
(3) 耐久性と経年劣化
断熱材の耐久性や経年劣化の影響も重要なポイントです。外断熱は長期的に使用するものですので、耐久性が高く、劣化しにくい素材を選ぶことで、断熱性能が長く維持され、メンテナンス費用の削減にもつながります。アキレス キューワンボードは、ガスバリア層を持つため、経年劣化による性能低下が少なく、長期にわたって安定した性能を提供する点で非常に優れています。
まとめ
外断熱リフォームに使用される断熱材には、さまざまな種類がありますが、断熱性能、コスト、耐久性のバランスを考慮して選ぶことが重要です。EPSやXPSはコストを抑えたい場合に適していますが、最高の断熱性能と補助金の活用によるコスト削減を考えるなら、アキレス キューワンボードが最も推奨される選択肢です。
外断熱リフォームは、建物の外壁全体に断熱材を取り付けることで、住まい全体の断熱性能を大幅に向上させるリフォーム方法です。外断熱は、住環境を大きく改善し、省エネ効果も高く、近年では多くの家庭で採用されています。しかし、外断熱リフォームにはメリットだけでなく、施工に関する注意点やリスクも存在します。ここでは、外断熱リフォームのメリットとデメリットについて詳しく解説し、施工における重要なポイントについても触れていきます。
外断熱リフォームの主なメリット
1. 断熱効果の向上
外断熱リフォームの最大のメリットは、建物全体の断熱性能が大幅に向上することです。外断熱は、建物の外側に断熱材を施すため、内断熱に比べて熱が逃げにくく、外気の影響を受けにくい構造を作り出します。これにより、冬は暖かく、夏は涼しい住環境を実現し、冷暖房の効率も格段に向上します。
- 冬の暖房効率が向上:外断熱により、建物内の熱が外に逃げにくくなり、暖房の使用頻度やエネルギー消費を抑えることができます。
- 夏の冷房効率も向上:夏は、外断熱材が太陽の熱を遮断し、建物内部の温度が上がるのを防ぎます。その結果、冷房の効率が高まり、快適な室内環境を保つことが可能です。
2. 住環境の改善
外断熱リフォームは、結露の発生を防ぎ、室内の湿度環境を改善する効果もあります。内断熱に比べ、壁内部の温度変化が少ないため、結露が発生しにくくなります。結露が抑えられることで、カビやダニの発生を防ぎ、家の健康面や耐久性が向上します。
- 結露の防止:建物内部の温度差を減らすことで、壁内の結露が発生しにくくなり、カビや腐敗を防止します。
- 健康的な住環境の実現:カビや湿気の問題を解消することで、アレルギーや喘息など、住まいにおける健康リスクを減少させます。
3. エネルギー効率の向上と省エネ効果
外断熱リフォームにより、冷暖房の使用頻度が減少するため、光熱費の削減が期待できます。外気の影響を受けにくくなることで、冷暖房に頼らずに一定の快適な温度を維持でき、エネルギー効率の向上が図れます。これにより、エネルギーコストの削減と環境負荷の軽減が同時に実現します。
4. 建物の耐久性が向上
外断熱材は、建物の外側に設置されるため、外壁を紫外線や雨風から保護する役割も果たします。外壁自体が劣化しにくくなるため、外壁材のメンテナンス頻度が減り、建物全体の耐久性が向上します。特に、寒冷地や湿気の多い地域では、外壁の保護効果が大きなメリットとなります。
5. 補助金制度の利用でコスト負担を軽減
近年では、次世代省エネ建材支援事業などの補助金制度を利用することで、外断熱リフォームの費用を大幅に抑えることが可能です。この補助金制度では、断熱性能の高い建材を使用したリフォームが対象となり、一定の条件を満たすことで費用の一部を補助金として受け取ることができます。特に、アキレス キューワンボードのような高性能断熱材は、補助金対象となるため、初期コストの削減に役立ちます。
- 補助金対象の断熱材を使用:補助金の認定を受けた断熱材を使用することで、リフォームの費用を抑えることができる。
- コスト削減と省エネ効果の両立:補助金の活用により、初期投資を抑えながら長期的な省エネ効果を実現。
外断熱リフォームの注意すべきデメリットとリスク
1. 初期費用が高い
外断熱リフォームの最大のデメリットは、初期費用が高額になることです。外断熱材は内断熱に比べて、施工の手間がかかり、使用する材料のコストも高いため、施工費用が大きく膨らむ場合があります。特に、既存の外壁材を撤去する必要がある場合、解体費用や処分費用が追加されるため、全体の費用が大幅に増加する可能性があります。
- 外壁の解体が必要な場合の費用増加:既存の外壁材が通気工法で施工されている場合、通気層を遮断するために外壁の一部を解体する必要があり、費用が上乗せされる。
- 断熱材の選定も重要:断熱材によってはコストが大きく異なるため、補助金対象の断熱材(アキレス キューワンボードなど)を選ぶことで、費用の軽減を図ることが可能です。
2. 工期が延長するリスク
外断熱リフォームは、建物の外側に断熱材を取り付けるため、工事規模が大きくなる傾向にあります。特に、既存の外壁を剥がす作業や、新たな外壁材を取り付ける作業が必要になる場合、工期が長期化する可能性があります。また、施工中に天候に左右されることも多く、雨や風が強い日には工事が中断されることがあるため、計画通りに進まないリスクがあります。
- 工期の長期化による生活への影響:工期が長くなると、仮住まいが必要になったり、住まいの利用が制限されるため、生活に影響が出ることがあります。
- 天候に左右されやすい:外断熱リフォームは屋外作業が中心のため、天候不順が続くと工期が延びるリスクがあります。
3. 施工精度に依存するリスク
外断熱リフォームの効果は、施工の精度に大きく依存します。断熱材が正しく設置されていなかったり、気密性が確保されていなかった場合、断熱効果が十分に発揮されず、期待通りの省エネ効果が得られないことがあります。そのため、経験豊富で信頼できる施工業者を選ぶことが非常に重要です。
- 施工不良のリスク:施工業者の技術力が低い場合、断熱材の隙間や不適切な取り付けが発生し、断熱効果が下がるリスクがあります。
- 信頼できる業者の選定が重要:補助金を受けられる認定業者や、外断熱の施工実績が豊富な業者に依頼することで、施工品質を確保できます。
4. 準防火地域での防火性能の確認が必要
外断熱リフォームを行う際、準防火地域では防火性能を満たす外壁仕上げ材を使用しなければなりません。これは地域の建築基準法により定められており、防火性能を満たしていない材料を使用した場合、工事が認められないことがあります。外断熱リフォームでは、断熱材だけでなく、使用する外壁仕上げ材の防火性能も確認することが非常に重要です。
- 防火性能の確認:補助金対象の断熱材であっても、外壁仕上げ材が防火基準を満たしていなければ、施工できない可能性があります。
まとめ
外断熱リフォームは、断熱性能の向上や住環境の改善、省エネ効果など、多くのメリットがありますが、同時に初期費用の高さや工期の延長、施工精度に依存するリスクも存在します。特に、補助金制度を活用することで、初期費用を抑えつつ、長期的な省エネ効果を得られる点は大きな利点です。断熱材の選定や施工業者の選び方、防火性能の確認を慎重に行い、成功する外断熱リフォームを実現しましょう。
断熱リフォームは、建物の省エネ性能を向上させ、快適な室内環境を実現するための重要な工事ですが、リフォームの一環として簡単に行えるものではありません。特に、外断熱リフォームは高度な技術と専門知識が求められるため、施工業者の選定が成功の鍵となります。断熱リフォームに失敗しないためには、信頼できる業者を選ぶことが重要であり、そのためには業者の実績や専門知識、契約前の確認事項をしっかりと把握することが必要です。
ここでは、断熱リフォームにおける業者選びのコツや失敗しないためのチェックポイント、そして契約前に確認すべき事項について詳しく解説します。
1. 信頼できる業者を見つけるためのコツ
(1) 断熱改修の専門知識を持つ業者を選ぶ
断熱リフォームは、単なるリフォーム工事とは異なり、断熱性能の確保と気密性の向上が重要です。そのため、業者選びの際には、外断熱リフォームや内断熱リフォームの経験があるだけでなく、断熱改修に関する専門知識を持っているかどうかを確認する必要があります。特に、気密処理が不十分だと断熱効果が低下し、期待していた省エネ効果が得られなくなる可能性があります。
断熱リフォームを行う業者には、以下のような技術力と知識が求められます。
- 気密処理の技術:外断熱リフォームでは、建物の隙間をしっかりと塞ぎ、冷暖房効率を最大限に引き出すための気密処理が重要です。気密性が確保されていないと、冷暖房効果が外部に逃げてしまい、断熱効果が十分に発揮されません。
- 断熱材の選定:断熱材には多くの種類がありますが、それぞれの材料特性を理解し、建物に最適なものを選定することが求められます。特に、次世代省エネ建材支援事業などの補助金を利用する場合、補助金対象の断熱材を熟知している業者を選ぶことが重要です。
(2) 外断熱リフォームの実績だけでは不十分、断熱改修の実績を重視
外断熱リフォームの施工実績が豊富な業者は信頼できますが、断熱改修の実績がどれほどあるかを確認することが大切です。特に、リフォーム工事は新築工事とは異なり、既存の建物の構造や状態に合わせたノウハウが必要です。新築と異なり、戸建て住宅の改修工事では、建物ごとに異なる問題や制約に対応するため、改修実績が豊富な業者を選ぶことが成功への近道です。
具体的には、以下のようなポイントを確認するとよいでしょう。
- 戸建て住宅の断熱改修実績:新築とは異なる既存の建物への断熱改修工事の実績が豊富かどうか。
- リフォーム工事におけるトラブル対応:外壁を剥がした際に出てくる予期せぬ問題(劣化、湿気、カビなど)への対応経験が豊富か。
- 断熱改修に特化した施工ノウハウ:特に外断熱の場合、外壁と断熱材の設置方法や、気密処理の技術が重要です。
(3) 補助金制度に詳しい業者を選ぶ
断熱リフォームを行う際、費用の一部を補助金でまかなえる場合があります。特に、次世代省エネ建材支援事業は、断熱リフォームを行う際に利用できる代表的な補助金制度です。補助金を最大限活用するためには、申請条件を熟知している業者を選ぶことが重要です。
- 補助金申請の経験が豊富な業者:補助金を受け取るためには、申請書類の提出や工事内容の確認など、細かい手続きが必要です。これに詳しい業者は、補助金を確実に受け取れるようサポートしてくれます。
- 補助金対象の断熱材を採用しているか:補助金を利用するには、使用する断熱材が補助金対象のものであるかを確認する必要があります。例えば、アキレス キューワンボードは補助金対象の断熱材であり、コストパフォーマンスが優れているため、これを採用する業者を選ぶことが推奨されます。
2. 業者選びで失敗しないためのチェックポイント
(1) 施工前の現地調査がしっかり行われるか
信頼できる業者は、施工前にしっかりとした現地調査を行うものです。断熱リフォームは、建物の構造や外壁の状態、断熱材の適用可能性などを正確に把握し、それに基づいた施工計画を立てることが不可欠です。現地調査を丁寧に行わない業者は、施工の際にトラブルが発生しやすくなります。
- 外壁の状態を詳細に確認:既存の外壁に劣化や問題がないかを確認し、補修が必要な場合はそれを含めた施工計画を立てる。
- 断熱材の適用可能性を確認:既存の構造に最適な断熱材を選定し、補助金制度の適用可能性も合わせて確認。
(2) 見積もりの詳細を確認する
信頼できる業者は、見積もり内容が透明で詳細な説明があるものです。見積もりの中には、材料費や施工費、予備費用などが含まれますが、特に予備費用や追加費用に関する項目が不明確な業者には注意が必要です。
- 細かい見積もり内容をチェック:材料費、施工費、追加工事が発生した場合の費用など、詳細な項目を確認する。
- 不明瞭な追加費用に注意:見積もりに含まれていない費用が後から請求されることがないよう、契約前にしっかりと確認。
(3) 実際の施工現場や過去の実績を確認する
業者の信頼性を確認するためには、実際の施工現場や過去の実績を確認することが有効です。業者の実績がホームページや資料だけでなく、実際の現場を見学できるか、過去の施工例を紹介してくれるかなどを確認しましょう。
- 現場見学や施工事例の紹介をお願いする:現場での施工方法や品質を確認できるよう、現場見学を依頼することも一つの手です。
- お客様の声や口コミを確認:他の顧客からの評価や口コミを確認し、信頼性を確認することも有効です。
3. 業者との契約前に確認すべきこと
(1) 契約内容の詳細を確認
契約前には、契約書の内容をしっかりと確認することが重要です。契約書に含まれる内容が明確かつ具体的であるかを確認し、不明点があれば必ず質問して解決しておきましょう。
- 契約書に含まれる項目:工事のスケジュール、使用する断熱材の詳細、施工範囲、工期、費用、保証内容などが明記されているか確認する。
- 保証内容を確認:断熱リフォームの施工後、何らかの不具合が発生した場合の保証内容がしっかりしているか確認しましょう。
(2) 工期の確認
断熱リフォームの工期は、建物の状況や施工内容によって異なりますが、工期が明確に設定されているか、また工期が遅れた場合の対応策が契約書に記載されているか確認することが大切です。特に、天候不順などで工期が延びる可能性もあるため、柔軟な対応を取る業者であるかを確認しましょう。
(3) 保証制度の有無
断熱リフォームは長期にわたる効果を期待するものですので、施工後の保証制度がしっかりしている業者を選ぶことが重要です。施工後のトラブルや劣化が発生した際に、保証期間内であれば無償で修繕してくれる業者を選ぶと安心です。
- 保証期間と内容:断熱材や施工に対する保証期間が明確に定められているか、何を保証してくれるのかを確認。
- アフターサービスの充実度:施工後の定期点検や、トラブルが発生した際の迅速な対応があるかどうかもチェックポイントです。
まとめ
断熱リフォームを成功させるためには、施工業者選びが非常に重要です。断熱改修には専門知識と施工技術が必要であり、単なるリフォーム業者では不十分なことが多いです。業者選びでは、断熱改修の実績や気密処理の技術、補助金に詳しいかどうかなどを確認し、信頼できる業者を選びましょう。また、契約前には詳細な見積もり内容や工期、保証制度をしっかり確認し、後悔のないリフォームを実現しましょう。
外断熱リフォームは、建物の断熱性能を大幅に向上させ、快適な住環境と省エネ効果を実現するための効果的な方法です。しかし、施工には高度な専門知識が求められ、経験不足や準備不足が原因でトラブルが発生するケースもあります。特に、軒ゼロの建物や外壁を解体するケースでは、独特のリスクや追加の工事が必要となるため、施工業者選びが非常に重要です。
本章では、よくあるトラブル事例とその回避方法、そしてトラブルを未然に防ぐための工夫について詳しく解説します。
1. 軒ゼロの建物では外断熱リフォームが難しい理由
軒ゼロの建物とは、屋根の軒がほとんどない、または全くない構造の建物を指します。軒がないため、外壁が直接雨に晒されやすく、外断熱リフォームの際には**雨仕舞(雨水が内部に侵入しないようにする工夫)**が非常に難しくなります。軒がない建物では、断熱パネルを外壁に設置しても、適切な雨仕舞を確保できないため、雨水が外壁や断熱材の裏側に侵入し、内部の腐食やカビの発生につながる可能性が高くなります。
軒ゼロ建物での雨仕舞のリスク
- 雨仕舞が困難:軒がないため、外壁に断熱パネルを貼ると、雨水が直接壁に流れ込みやすく、特に断熱材の接合部分から水が侵入するリスクが高まります。結果として、断熱材の劣化や建物内部への水の浸入を招き、長期的な耐久性に悪影響を及ぼします。
- 気密処理が難しい:外断熱リフォームの効果を最大限発揮するためには、気密処理が重要ですが、軒ゼロの構造では適切な気密処理が難しくなり、隙間から冷暖房効率が下がることがあります。
【回避方法】
軒ゼロの建物では、基本的に外断熱リフォームは難しいと考えるべきです。代わりに、内断熱リフォームや外壁の防水・防湿性能を強化する方法を検討することが推奨されます。これにより、雨仕舞の問題を回避しつつ、建物の断熱性能を向上させることができます。
2. 外壁を解体するケースのメリットと注意点
外断熱リフォームを行う際、既存の外壁を解体して新たに断熱材を設置する方法もあります。この方法は費用が高くなりますが、以下のようなメリットもあります。
費用が高くなる理由
外壁を解体する場合、解体費用や廃材処理費用が追加されるため、外断熱リフォーム全体のコストが増加します。また、外壁を剥がした後に、建物の劣化や不具合が見つかることがあり、その修繕費用も発生する可能性があります。
- 解体費用の増加:外壁を剥がすことで、作業工程が増え、人件費や処分費がかかる。
- 追加工事の可能性:解体中に見つかった劣化部分や構造的な問題を修繕するための追加費用が発生することがある。
耐震強化が可能
外壁を解体して外断熱リフォームを行うことで、断熱性能の向上だけでなく、建物の耐震性能を強化することが可能です。耐震改修を同時に行うことで、住まいの安全性を向上させ、地震などの自然災害に対する備えができます。
-
構造計算の実施:解体後、耐震改修を行う際に、構造計算ができる業者に依頼すれば、建物の耐震性を評価し、上部構造評点の向上が可能です。特に、N値計算を実施できる業者であれば、地震時の引き抜き対策も含めた総合的な耐震強化が期待できます。
- 上部構造評点の向上:建物の耐震性を数値化する「上部構造評点」を上げるための改修を行うことで、地震に強い住まいを実現できます。
- 引き抜き対策:柱や梁などの構造材が地震の際に引き抜かれるリスクを減らすため、引き抜き対策を講じることが可能です。
【回避方法】
外壁の解体と耐震強化を組み合わせたリフォームを行う場合、断熱と耐震の両方の実績が豊富な業者に依頼することが重要です。特に、構造計算やN値計算ができる技術力を持つ会社を選ぶことで、断熱と耐震の両面で効果的な改修が実現できます。
3. トラブルを未然に防ぐための工夫
(1) 業者選びの重要性
外断熱リフォームでのトラブルの多くは、施工業者の経験不足や技術力の欠如によって発生します。断熱改修は専門的な工事であり、リフォームの延長でできる簡単な作業ではありません。特に、外断熱の場合は気密処理や雨仕舞が重要で、これらの処理が不十分だと断熱効果が著しく低下するだけでなく、建物に深刻なダメージを与える可能性があります。
- 経験豊富な業者の選定:業者選びの際には、外断熱リフォームの施工実績だけでなく、断熱改修や耐震改修の実績があるかも確認する必要があります。リフォーム後の建物がどのように変わるかを具体的に説明できる業者が理想です。
- 構造計算ができるかどうか:外壁を解体して断熱改修を行う場合、構造計算ができる業者であるかを確認し、耐震強化も併せて行うことを検討しましょう。
(2) 詳細な現場調査と計画が必須
トラブルを防ぐためには、事前の現場調査の精度が非常に重要です。適切な現場調査が行われていないと、施工後に予期せぬ問題が発生し、追加費用や工期の延長が避けられません。調査の際には、建物の状態や構造、外壁の材質などを詳細に確認し、それに基づいて具体的な施工計画を立てることが不可欠です。
- 雨仕舞の確認:特に軒ゼロ建物では、雨仕舞の処理が重要です。雨水が侵入しないための工夫ができているかどうか、事前にしっかり確認しましょう。
- 断熱材の選定:断熱材の選定も重要なポイントです。補助金対象の断熱材を使用することで、費用を抑えることができるため、補助金に詳しい業者を選ぶこともトラブルを回避するための一つの方法です。
(3) 定期的な進捗確認とコミュニケーション
工事が進む中で、トラブルを未然に防ぐためには、定期的に進捗状況を確認し、業者と密なコミュニケーションを取ることが大切です。特に、外断熱リフォームは屋外作業が多いため、天候や施工状況に左右されることがあります。進捗が予定通り進んでいるか、問題がないかを確認しながら進めることで、大きなトラブルを防ぐことができます。
まとめ
外断熱リフォームは断熱性能を大幅に向上させる効果的な方法ですが、軒ゼロの建物や外壁解体を伴う工事では、注意が必要です。軒ゼロの建物では雨仕舞の問題から外断熱リフォームが難しく、外壁解体が必要なケースでは耐震強化も含めた工事が可能です。こうした複雑なリフォームには、断熱改修と耐震改修の両方に精通した実績豊富な業者を選ぶことが不可欠です。施工前の現場調査を徹底し、施工中も適切な進捗確認を行うことで、トラブルを防ぎ、成功するリフォームを実現しましょう。
次世代省エネ建材支援事業は、住宅の断熱性能向上を目的としたリフォームに対して、国から補助金が支給される制度です。この補助金を活用することで、外断熱リフォームや内断熱リフォームの初期費用を大幅に軽減することが可能です。特に高性能な断熱材を使用する場合、補助金の活用は必須の要素となります。
本記事では、この補助金制度の詳細、申請条件や手続きの流れ、アキレス キューワンボードを使用した補助金申請のメリットについて解説します。外断熱リフォームを検討しているなら、補助金の活用についても早めに準備を進めることが成功のカギです。
次世代省エネ建材支援事業とは?
次世代省エネ建材支援事業は、断熱材や窓などの省エネ性能を高める建材を使用したリフォーム工事に対して、国から支援を受けられる制度です。この補助金を活用することで、住宅のエネルギー効率を高め、CO2排出量を削減し、環境負荷を軽減することが期待されています。
この補助金は、断熱性能が一定の基準を満たす建材が使用されたリフォーム工事に対して支給されるため、外断熱リフォームを検討する際には、必ず補助金制度の適用範囲を確認しておくことが重要です。特に、高性能断熱材として知られるアキレス キューワンボードは、この補助金の対象となっており、コストを大幅に削減する効果が期待できます。
補助金の申請条件と手続き方法
補助金を申請するためには、いくつかの重要な条件と手続きをクリアする必要があります。特に外皮計算書の提出やリフォーム後の断熱性能の算定が求められるため、専門的な準備が必要です。
(1) 使用する断熱材が補助対象であること
補助金を申請するためには、リフォームに使用する断熱材が補助金対象建材であることが前提条件です。補助対象となる建材は、断熱性能が一定の基準を満たすものでなければなりません。たとえば、アキレス キューワンボードは、断熱性能が高く、補助金対象の建材として認定されています。
(2) 外皮計算書の提出が必須
補助金を申請するためには、リフォーム後の建物の断熱性能を示す外皮計算書が必須となります。外皮計算書は、リフォーム後に建物全体の断熱性能がどのように改善されるかを数値化した書類です。この書類は、住宅の外壁、屋根、床、窓など、すべての外部に接する部分の断熱性能を評価するために使用されます。
- 窓のリフォーム有無の確認:補助金申請時に、窓やサッシのリフォームを行うかどうかも重要な要素となります。窓をリフォームしない場合、既存のサッシの断熱性能値も外皮計算書に含めて算定する必要があります。
- 断熱性能値の算定:リフォーム後の断熱性能が一定の基準を満たすことを確認するため、正確な計算が求められます。計算には専門知識が必要となるため、補助金申請に精通した業者に依頼することが推奨されます。
(3) 新設が受理されるまでは契約不可
補助金申請に関する重要なルールとして、補助金の受理前にはリフォーム契約ができないという点があります。つまり、補助金申請を提出し、承認が下りるまでの間は、リフォーム工事の契約を結ぶことができません。これを無視して契約を進めてしまうと、補助金が適用されなくなるリスクがあります。
そのため、申請のタイミングや手続きを事前に把握し、補助金の承認を受けてからリフォーム契約を進めることが重要です。
(4) 時期の確認と早めの準備が必要
補助金の申請には時期が決まっており、申請の受付は一定期間に限られます。さらに、申請から承認までには数ヶ月かかることが多いため、早めに準備を進めることが必要です。申請が遅れると、年度内の予算枠が終了してしまい、補助金を受けられなくなることもあります。
- 数ヶ月前からの準備が必要:補助金の申請に必要な書類や外皮計算書の準備には時間がかかるため、数ヶ月前からリフォーム業者と連携して準備を進めることが大切です。
- 申請受付時期の確認:申請が可能な時期を事前に確認し、そのタイミングに合わせてリフォーム計画を立てるようにしましょう。
アキレス キューワンボードを活用した補助金申請のメリット
アキレス キューワンボードは、次世代省エネ建材支援事業の補助金対象断熱材として認定されています。この断熱材を使用することで、補助金を活用しながら、コストパフォーマンスの高い断熱リフォームを実現できます。
(1) 高い断熱性能
アキレス キューワンボードは、熱伝導率0.020〜0.021 W/m・Kという非常に優れた断熱性能を持っており、外断熱リフォームに最適な建材です。これにより、建物全体の断熱性能が向上し、冷暖房効率が大幅に改善されます。また、経年劣化が少ないため、長期にわたって高い断熱効果を維持することができます。
(2) 補助金を活用することで初期費用を抑えられる
アキレス キューワンボードを使用することで、次世代省エネ建材支援事業の補助金を受けられ、外断熱リフォームの初期費用を大幅に軽減できます。たとえば、東京都では最大300万円の補助金が支給されるため、高性能断熱材を使ったリフォームが非常にリーズナブルに行えるようになります。
(3) 長期的な省エネ効果
高い断熱性能を持つアキレス キューワンボードを使用することで、リフォーム後の冷暖房効率が向上し、年間の光熱費を大幅に削減することが可能です。補助金を活用しつつ、省エネ効果によって長期的なコスト削減も実現できます。
効果的に活用するためのポイント
補助金を効果的に活用するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
(1) 補助金に詳しい業者を選ぶ
補助金申請には複雑な手続きが伴うため、補助金に詳しい業者を選ぶことが非常に重要です。申請に必要な外皮計算書の作成や、リフォーム計画の立案をサポートしてくれる業者を選ぶことで、スムーズに補助金を受け取ることができます。
(2) 外皮計算書の準備を早めに行う
外皮計算書の作成には、リフォーム後の断熱性能を正確に評価するため、建物全体の調査が必要です。この作業はリフォーム業者と連携して行い、早めに準備を進めることが補助金申請の成功に繋がります。
(3) 窓やサッシの性能も含めて計算
窓のリフォームを行わない場合でも、既存のサッシや窓の断熱性能を考慮した外皮計算が必要です。既存の窓が断熱性能に劣る場合、その影響が補助金の申請に影響を与えることがあるため、窓の断熱性能も含めて全体の計画を立てることが重要です。
まとめ
次世代省エネ建材支援事業の補助金を活用することで、外断熱リフォームの初期費用を大幅に軽減し、長期的な省エネ効果を実現することが可能です。特に、アキレス キューワンボードのような補助金対象断熱材を使用することで、高性能なリフォームを手頃なコストで実施できる点は大きなメリットです。補助金申請には外皮計算書の作成や申請タイミングが重要で、申請前に契約できないというルールもあります。信頼できる業者と早めに準備を進め、効果的な補助金活用を目指しましょう。
外断熱リフォームは、建物全体を断熱材で覆うことで、断熱性能を大幅に向上させ、省エネ効果と快適な住環境を実現するためのリフォーム方法です。しかし、効果的な断熱リフォームを実現するためには、窓や床、天井など他の要素の断熱強化も合わせて考えることが重要です。また、耐震改修を同時に行うことで、災害に強い住まいにすることも可能です。本章では、省エネ効果を高める外断熱リフォームのプランニング方法、改修後のエネルギー消費量の比較、さらに補助金や助成金の活用方法について詳細に解説します。
1. 省エネ効果を高める外断熱リフォームのプランニング
外断熱リフォームを効果的に行うためには、建物全体の断熱性能をバランスよく強化することが大切です。外壁を断熱するだけではなく、窓や床、天井の断熱、さらに耐震改修も合わせて検討することで、快適で安全な住まいを実現できます。
(1) 窓のリフォームの選択肢
外断熱リフォームを行う際、窓の断熱性能も重要な要素です。窓は壁に比べて断熱性能が低いため、外壁だけを断熱しても、窓から多くの熱が逃げてしまいます。そのため、窓のリフォームも検討する必要がありますが、以下の3つの方法が一般的です。
-
カバー工法
- 既存の窓枠の上に新しいサッシを取り付ける方法で、既存の窓を解体する必要がないため、工期が短く、費用も抑えられます。外断熱リフォームと合わせて施工することで、窓の断熱性能を向上させ、エネルギー効率を高めることができます。
- メリット:工事が比較的簡単で、コストが低い。既存の窓を残しつつ断熱効果を向上。
- デメリット:完全な窓の断熱強化には限界があり、サッシ部分の断熱性能には若干の制限がある。
-
内窓の設置
- 既存の窓の内側に新しい窓を取り付ける二重窓の方式で、窓の断熱性能を飛躍的に高めることが可能です。内窓を追加することで、熱の出入りを防ぎ、騒音や結露も防止できます。
- メリット:高い断熱性能を発揮し、結露や防音効果も期待できる。窓の交換に比べてコストが低い。
- デメリット:窓枠部分が二重になるため、見た目に違和感がある場合がある。
-
新設サッシの入れ替え
- 既存の窓枠をすべて撤去し、新しい高断熱サッシに交換する方法で、断熱性能が大幅に向上します。最新の断熱サッシを採用することで、冷暖房効率を大幅に向上させることができます。
- メリット:窓全体の断熱性能が最高水準になり、省エネ効果が非常に高い。
- デメリット:既存の窓枠を解体するため、工期が長く、コストも高め。
窓の断熱強化は外断熱リフォームの効果を最大限に引き出すために不可欠な要素です。窓の種類や予算に応じて最適な方法を選びましょう。
(2) 床や天井の断熱
外断熱リフォームでは、床や天井の断熱強化も重要なポイントです。建物全体の断熱性能を高めるためには、外壁だけでなく、床や天井にも断熱材を追加する必要があります。
-
床の断熱:1階部分の床は、外気の影響を受けやすく、冷気が床下から上がってくることが多いです。床下に断熱材を追加することで、床からの冷気を防ぎ、足元から暖かい住まいを実現できます。特に寒冷地では、床の断熱が快適さに大きく寄与します。
-
天井の断熱:最上階の天井は外気との接触面が広く、熱が逃げやすい部分です。天井に断熱材を追加することで、室内の温度を一定に保ち、冷暖房効率を大幅に向上させることができます。特に、屋根が直接日光にさらされる夏場は、天井断熱が快適性に大きく貢献します。
(3) 耐震改修を併せて行う
外断熱リフォームを行う際には、耐震改修を同時に行うことも非常に効果的です。特に、外壁を解体して断熱材を設置する場合、建物の構造を補強する耐震改修が可能となります。耐震改修を併せて行うことで、断熱性だけでなく、地震に強い安全な住まいを実現することができます。
-
構造計算による耐震強化:外断熱リフォームと耐震改修を同時に行う場合、構造計算を行い、建物の耐震性能を向上させることができます。特に、上部構造評点を改善することで、地震に強い建物を作り上げることが可能です。また、N値計算を実施することで、地震の際に柱や梁が引き抜かれないようにする引き抜き対策も講じることができます。
-
耐震改修のメリット:外断熱リフォームと同時に耐震改修を行うことで、工期を短縮し、トータルコストを抑えることができます。また、耐震改修も補助金の対象となる場合があり、経済的にもメリットがあります。
2. 改修後のエネルギー消費量の比較
外断熱リフォームを行うことで、冷暖房効率が大幅に向上し、エネルギー消費量が削減されます。断熱性能が向上することで、室内の温度を外気の影響から保護し、冷暖房にかかるエネルギーが削減されるため、光熱費が年間で20〜40%程度削減されることも珍しくありません。
-
冷暖房効率の改善:断熱リフォーム前後で冷暖房の稼働時間を比較すると、断熱リフォーム後は冷暖房の使用頻度が減少します。特に冬場は、暖房を長時間つける必要がなくなり、室内が短時間で暖まります。夏場は、冷房の効果が持続しやすく、快適な室温が保たれます。
-
断熱材の性能による効果の違い:例えば、アキレス キューワンボードのような高性能断熱材を使用した場合、断熱効果が非常に高く、エネルギー消費量をさらに大幅に削減できます。
3. 補助金や助成金の活用方法
外断熱リフォームや耐震改修を行う際には、補助金や助成金を効果的に活用することで、初期費用の負担を軽減することができます。特に、次世代省エネ建材支援事業などの補助金制度を活用することは非常に重要です。
(1) 次世代省エネ建材支援事業
次世代省エネ建材支援事業は、高性能な断熱材や窓を使用したリフォームに対して補助金が支給される制度です。地域によって補助金の額は異なりますが、東京都では最大300万円の補助金が受けられるケースもあります。
-
補助金対象の断熱材を使用:アキレス キューワンボードのような補助金対象断熱材を使用することで、初期費用を大幅に抑えることが可能です。
-
手続きの注意点:補助金申請には事前の準備が必要で、補助金が受理されるまでは契約できません。補助金を活用するためには、数ヶ月前から計画を立て、必要な書類や外皮計算書の作成を行うことが大切です。
(2) 地方自治体の助成金
各地方自治体でも、省エネリフォームや耐震改修に対する助成金が設けられている場合があります。地方自治体の助成金は、リフォーム費用の一部を補助してくれる制度で、地域ごとに金額や条件が異なります。事前に自治体の制度を確認し、適用可能な助成金を活用することで、コストを抑えることができます。
まとめ
外断熱リフォームは、建物全体の断熱性能を向上させ、快適な住環境と大幅な省エネ効果を実現するための有効な手段です。窓のリフォームや床・天井の断熱強化、さらには耐震改修を併せて行うことで、建物の快適性と安全性が格段に向上します。また、次世代省エネ建材支援事業や地方自治体の助成金を活用することで、リフォームの初期費用を大幅に抑えることが可能です。
外断熱リフォームは、断熱性能を大幅に向上させることで、省エネ効果や快適な住環境を実現する効果的なリフォーム方法です。しかし、外断熱リフォームには専門的な知識や技術が必要で、適切な計画を立てずに進めると失敗やトラブルにつながることがあります。この記事では、外断熱リフォームで失敗しないために知っておくべき重要なポイントをおさらいし、成功するためのアクションプランについて解説します。
1. 成功するための重要な要点のおさらい
外断熱リフォームを成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが必要です。これらのポイントをしっかりと理解し、計画段階から実行に移すことで、効果的なリフォームを実現できます。
(1) 建物全体の断熱性能をバランスよく強化する
外断熱リフォームの効果を最大限に引き出すためには、外壁だけでなく窓、床、天井などの断熱性能も同時に改善する必要があります。外壁のみを断熱しても、窓や床から熱が逃げてしまうと、期待した省エネ効果が得られない場合があります。
- 窓の断熱強化:既存の窓をカバー工法で断熱強化するか、内窓の設置や新設サッシへの入れ替えを行うことを検討しましょう。窓の断熱性能を高めることで、外断熱リフォームの効果が最大化します。
- 床や天井の断熱:1階の床や最上階の天井は、外気の影響を大きく受けやすい部分です。これらの部分にも断熱材を追加することで、室内の温度を一定に保ち、省エネ効果を高めることができます。
(2) 雨仕舞や気密処理の重要性
外断熱リフォームにおいて、雨仕舞や気密処理が不十分だと、断熱効果が低下するだけでなく、雨水が建物内部に侵入し、建物の劣化やカビの発生につながる可能性があります。特に軒ゼロの建物では、雨仕舞が非常に重要です。経験豊富な業者に依頼し、適切な施工を行ってもらうことが大切です。
(3) 耐震改修との併用
外断熱リフォームを行う際には、耐震改修を同時に行うことも検討しましょう。外壁を解体する場合は、建物の構造を補強する耐震改修を行うことで、断熱性能だけでなく、地震に強い住まいを実現できます。構造計算やN値計算を行える業者に依頼すれば、上部構造評点の向上や引き抜き対策を含めた総合的な改修が可能です。
(4) 補助金や助成金を活用してコストを削減
外断熱リフォームは高額になることが多いため、次世代省エネ建材支援事業などの補助金制度を活用することで、初期費用を抑えることが重要です。特に、アキレス キューワンボードのような高性能断熱材は補助金対象となるため、これを使用することでリフォームコストを大幅に削減できます。また、地方自治体の助成金制度も活用できる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
(5) 外皮計算書の提出が必須
補助金を申請する際には、外皮計算書の提出が必須です。外皮計算書では、リフォーム後の建物の断熱性能が数値化され、一定の基準を満たしていることが確認されます。窓のリフォームを行わない場合でも、既存のサッシの性能値を含めて計算が必要です。補助金が受理されるまでは契約できないため、早めの準備が求められます。
2. 専門家に相談する重要性
外断熱リフォームは、専門知識と技術が必要な工事であり、リフォームの延長で簡単にできるものではありません。そのため、リフォームを検討する際には、必ず専門家に相談することが成功の鍵となります。
(1) 専門業者選びの重要性
断熱改修には、外断熱の経験だけでなく、気密処理や雨仕舞のノウハウが求められます。また、断熱改修と耐震改修の両方の実績を持つ業者を選ぶことで、断熱性だけでなく安全性も向上させることができます。業者選びの際には、次のポイントを確認しましょう。
- 施工実績:外断熱リフォームや断熱改修の豊富な実績を持つ業者を選ぶことが重要です。また、過去の施工事例を確認し、具体的なアプローチを理解しているかを確認しましょう。
- 補助金申請の経験:補助金申請には専門的な知識が必要なため、補助金申請に詳しい業者を選ぶことが重要です。補助金申請に必要な書類の作成や手続きをサポートしてくれる業者が理想的です。
- 耐震改修の実績:外断熱リフォームと併せて耐震改修を行う場合、構造計算やN値計算ができる業者を選ぶことで、断熱性能と耐震性能の両方を強化できます。
(2) 専門家との綿密なコミュニケーション
リフォームを進める上で、専門家との綿密なコミュニケーションが非常に重要です。工事前の計画段階から施工中まで、しっかりと打ち合わせを行い、進捗状況を確認しましょう。疑問点や不安な点があれば、早めに相談することでトラブルを未然に防ぐことができます。
- 現地調査の徹底:施工前の現地調査が不十分だと、工事が始まってから予期せぬ問題が発生する可能性があります。専門業者が建物の状態をしっかり把握し、問題点を事前に解消できるか確認しましょう。
- 施工計画の確認:リフォームの内容や工期、使用する断熱材、施工の流れについても、専門家と詳細に確認することが重要です。
3. 効果的な外断熱リフォームの実現に向けたアクションプラン
効果的な外断熱リフォームを実現するためには、計画的なアプローチが必要です。以下に、外断熱リフォームを成功させるための具体的なアクションプランを提案します。
(1) 現状の把握と目標の設定
まずは、現在の住まいの断熱性能を評価し、どの部分に断熱強化が必要かを明確にしましょう。その上で、どのような効果を期待するか(冷暖房効率の向上、光熱費の削減、快適性の向上など)を具体的に設定します。
(2) 専門業者に相談してリフォーム計画を立てる
信頼できる専門業者に相談し、現地調査を依頼して具体的なリフォーム計画を立てます。この際、断熱材の選定、窓や床、天井の断熱強化の方法、耐震改修の必要性など、すべての要素を考慮して最適なプランを作成します。
(3) 補助金の確認と申請準備
次世代省エネ建材支援事業などの補助金制度を活用するため、必要な外皮計算書の作成や書類の準備を行います。補助金申請には時間がかかるため、早めに申請手続きを開始し、受理されるまで契約を結ばないように注意します。
(4) 進捗確認と定期的なチェック
リフォームが始まったら、定期的に進捗確認を行い、計画通りに進んでいるかをチェックします。工事の途中で問題が発生した場合は、すぐに業者と相談して修正対応を依頼しましょう。
まとめ
外断熱リフォームは、断熱性能を大幅に向上させ、省エネ効果と快適な住まいを実現するための優れた方法です。しかし、成功するためには、窓や床、天井なども含めたバランスの取れたプランニングや、雨仕舞や気密処理、耐震改修の併用が必要です。さらに、補助金や助成金を活用することで、初期費用を抑えながら効果的なリフォームを行うことができます。信頼できる専門家に相談し、計画的に進めることで、失敗のない外断熱リフォームを実現しましょう。
断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』
500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!
断熱リフォームをする前に必ず読んでください!
何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。
導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。
※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。
< プロフィール >

ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【趣味】
アクアリウム歴30年。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。
その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。
2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。
2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。
2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。
2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。
【現在の活動状況】
ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。
戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・
- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。
耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。
補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)
ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新
※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。
営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)