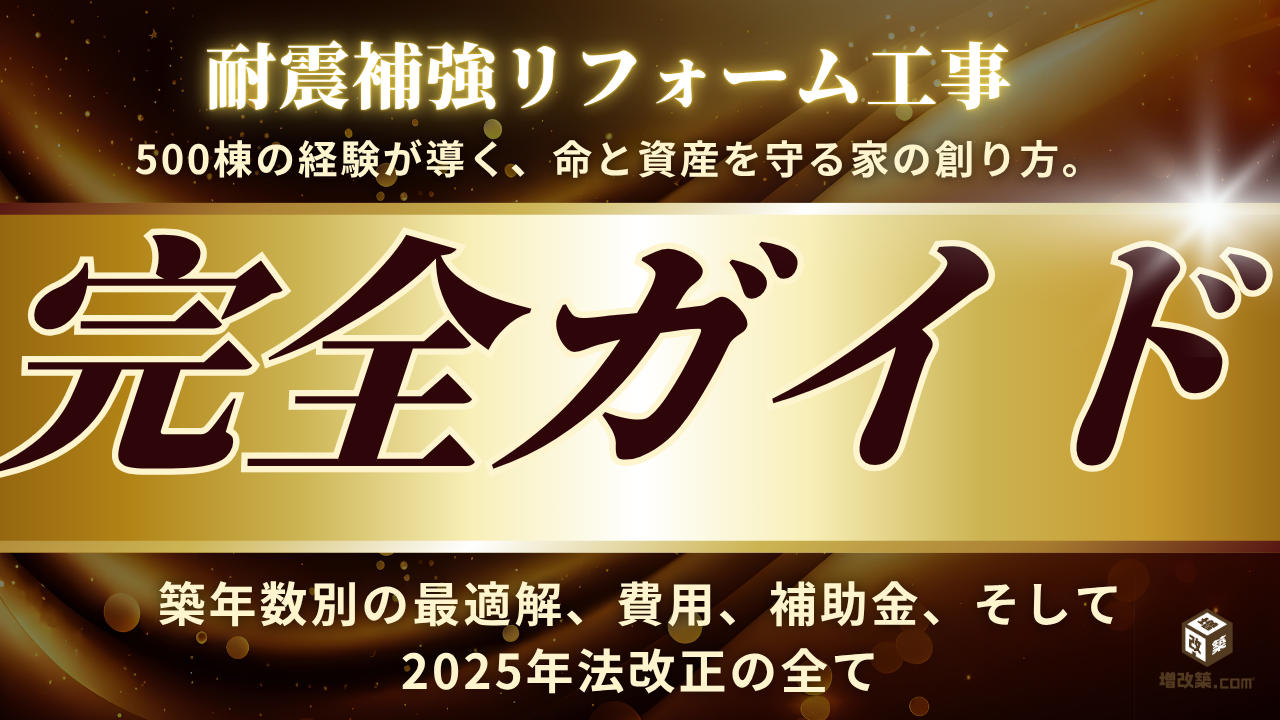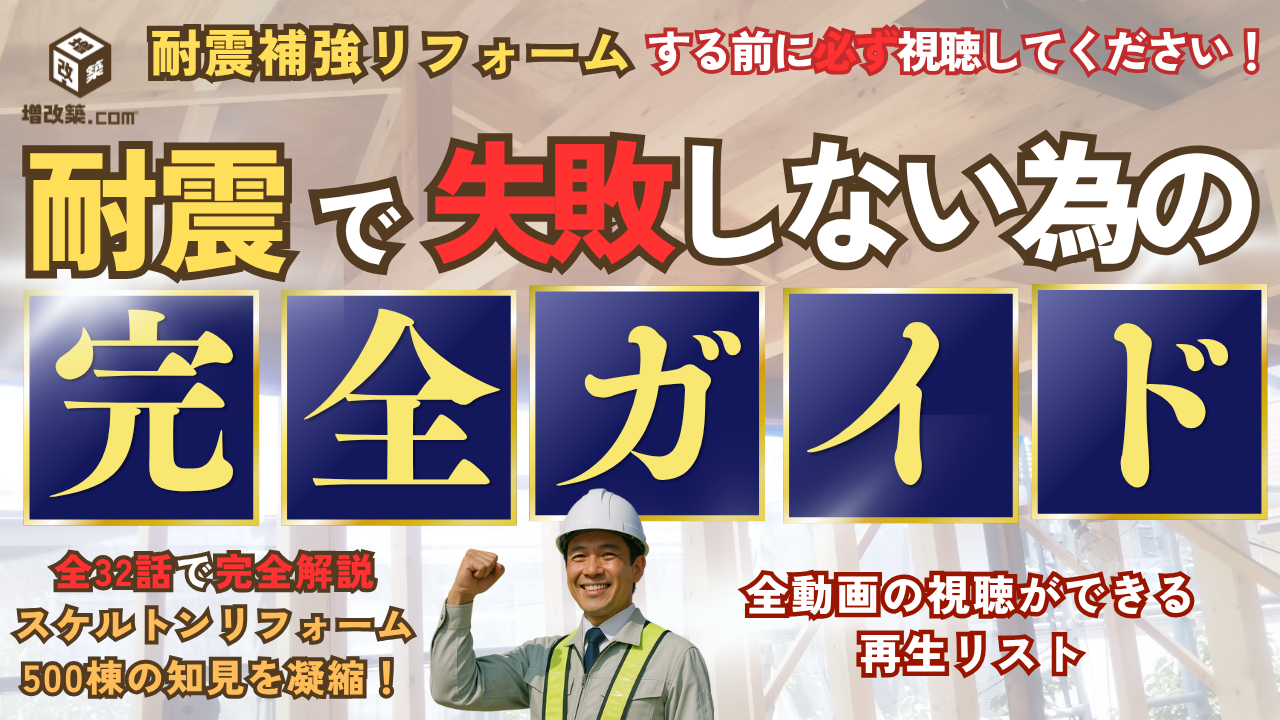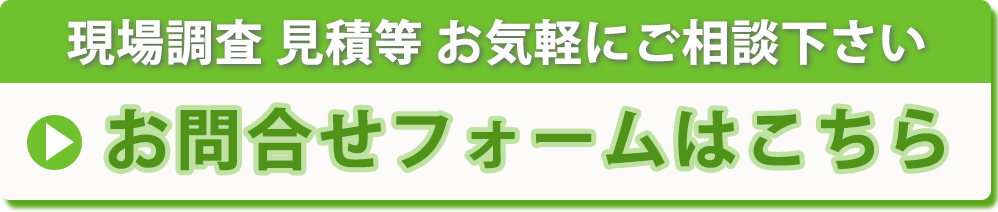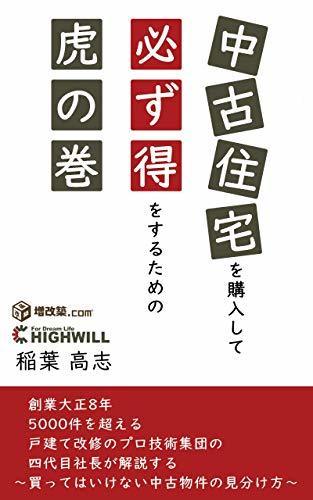戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP> お役立ち情報 > 上部構造評点とは?
2022年07月15日
上部構造評点とは?

中古物件のリフォーム、リノベーションを行う際に耐震診断を行います。耐震診断の結果から現状の状況、目指すべき目標、その目標に向けてやるべきことを判断することになります。その現状の数値、目指すべき目標に関して絶対に欠かすことができないものが「上部構造評点」です。
一般には聞きなじみのない「上部構造評点」とはいったいどういうものなのか。上部構造評点そのものの解説やなぜ必要なのかなどを解説します。

そもそも上部構造とはどのような場所を指すのか、まずは上部構造に関する簡単な基礎知識からご紹介します。
基礎部分よりも上が上部構造
上部構造と聞いて、屋根などを思い浮かべた方がいるかもしれませんが、実際のところ、屋根だけでは上部構造の一部です。ここでの「上部構造」とは基礎よりも上の部分を指します。そして、下部構造は基礎部分。つまり、地上に出ているところが上部構造、地中に入っている部分が下部構造となります。
もちろん基礎がしっかりとしていなければ、建物を支えられないことは誰でもわかります。ただ、上部構造に関して、バランスを欠いていればちょっとした揺れで倒壊しやすいのも事実。上部構造のバランス、強度などをしっかりと踏まえて対策を立てないと、地震に強い家を建設することは難しいのです。
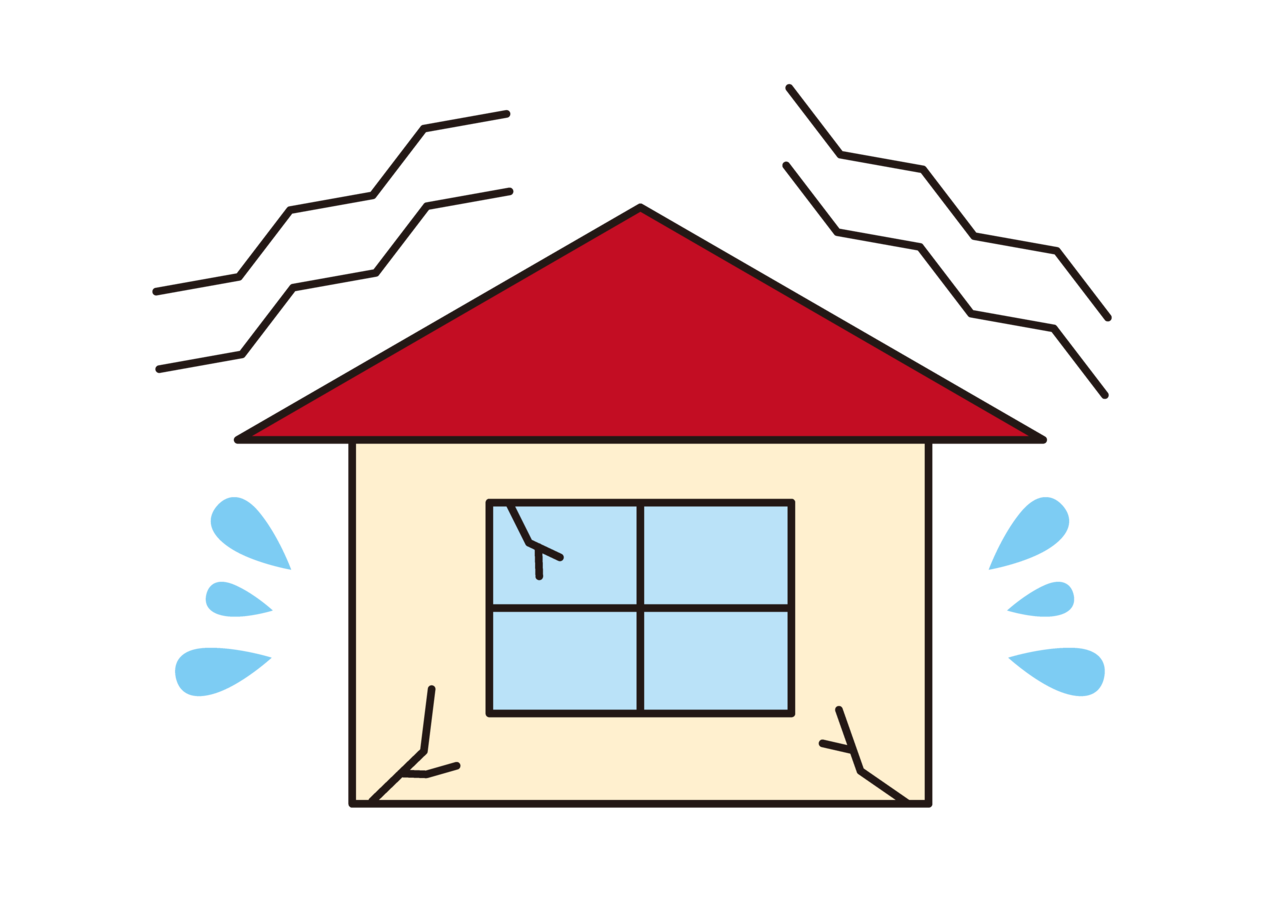
では、本題となる上部構造評点(Iw値)とはいったい何を示す数字なのか、複数の観点から解説していきます。
上部構造評点は建物が持つ耐久力を示す
1981年以前の旧耐震基準で建てられた木造家屋では、2000年の品確法で定められた『耐震等級』という耐震指標保有水平力、耐震等級によって耐震力を測れないため、Iw値という指標で耐震力を測ります。
「Iw値=家の保有耐力/耐震のために必要な耐力」によって数値化されます。
地震が発生した際に想定されるエネルギーが建物に加わる際に、どれくらい建物がそれに耐えられるかを示します。例えば、建物に加わる地震のエネルギーと全く同じ耐久力を持っていた場合、上部構造評点は1.0となります。
1.0をクリアすることで震度6強の地震に対して倒壊、または崩壊する可能性が低いとされており、国の耐震改修の最低基準値となっている指標であります。
この1.0という数字が大きなポイントであり、重要な意味を持ちます。
上部構造評点の数値は震度6強の時のもの
では、上部構造評点の数値を出すために用いられる地震の想定エネルギーは果たしてどれくらいか。現状では震度6強のエネルギーを当てはめて算出しています。つまり、上部構造評点が1.0だった場合、震度6強レベルで加わってくるエネルギーとがっぷり四つで対峙できることを意味します。数値が良ければ良いほど耐久性がある、悪ければ悪いほど危険性が出てくるという認識が持てるはずです。
上部構造評点が低いと少しの地震で被害が出る
上部構造評点での1.0という数字は、別の数値に置き換えると震度6強レベルに耐えるために必要な耐久力が100%であると考えられます。つまり、上部構造評点が0.5だった場合、わずか50%しか耐久力がないことを意味します。ちなみに、上部構造評点が0.5の場合、震度5弱の地震ですら何かしらの被害が出る可能性があり、5強になれば半壊レベルの損傷を受ける可能性が高まります。
命を守るための最低限の数値1.0の誤解
上部構造評点が1.0という数字は、あくまでも震度6強における倒壊を避けるためにあります。
先の熊本地震では震度 7 の地震がわずか 28 時間の間に 2 度発生しました。
建築基準法でいう新築の最低基準の1.25倍の強度を持つ「絶対に倒壊しない」と思われていた耐震等級2の住宅が倒壊した事実を忘れてはなりません。上部構造評点の1.0という指標と新築の指標では計算方法が異なるものの、耐震等級1という数値は国の最低基準です。その絶対にクリアしなければならない最低限の建築基準法基準(耐震等級1)は生命の安全を守る基準であると定められているのにもかかわらず、倒壊してしまったのです。増改築.com®では上部構造評点を1.5以上で提案している理由はこのような背景があります。
建築基準法そのものは、生命の安全を守るための最低限の基準であるということです。
つまり家が損害を受けない!損傷しない!とはどこにも書いてはないのです。
仮に命が助かったとしても、建物が半壊以上しているような状況であればこれらを建て替える費用については、自己負担となってしまうのが現実であるということ。実際にそのようなケースで建て替えを余儀なくされ2重ローンに苦しんでおられる方も多いのです。
つまり、建築基準法をクリアしているから安心、1.0だから安心という勘違い、ここをまず、お施主様自体が理解することが必要なのです。
一定の数値以上なら証明書が出される
上部構造評点は、基本的に耐震診断を行う中で出されるものであり、築年数の経過など耐震性能に不安があるケースで算出されるイメージを持つ人もいるでしょう。しかし、上部構造評点の数値がいい場合、様々な恩恵が得られます。例えば、築20年以上が経過した木造住宅を購入した場合、耐震基準が既に満たされていた場合は住宅ローン控除などが受けられます。いわゆる住宅ローン減税と呼ばれるもので、新築以外でも築年数20年以上の中古物件にも該当します。
住宅ローン減税は、住宅ローンの残高の一部を所得税から差し引いてくれるもので、住宅購入に関する負担を低減できます。また登録免許税や不動産所取得税の軽減、固定資産税の減免、地震保険に関する割引など、上部構造評点が高ければお得なことが多いのです。この上部構造評点の数値を証明するために必要なのが、「耐震基準適合証明書」です。
発行するにはそれなりの費用が発生しますが、中古住宅を購入する際の住宅ローン控除などで必要とされる書類全てを発行してくれるほか、どのように手続きをすればいいかというところまでアドバイスをくれる不動産会社もあります。

上部構造評点が高いといいことばかりということがお分かりいただけたのではないでしょうか。ここからは本当に上部構造評点が1.0以上ないといけないのかについて解説します。
安全性を考えるなら1.5以上が確実か
上部構造評点をどこまで高めればよくて、安全なのかについてですが、結論から言えば、震度6強でも無傷でいられるような数値にするにはかなりのポイントが必要です。
上部構造評点には4段階あり、
0.7未満だと「倒壊する可能性が高い」、
0.7~1.0未満だと「倒壊する可能性がある」、
1.0以上だと「一応倒壊しない」、
1.5以上で「倒壊しない」となっています。
1.0でも「一応」倒壊しないという多少あやふやな表現になっており、安全性を求めるのであれば1.5以上を目指すのが確実です。
先ほど解説した通り、上部構造評点自体が震度6を想定していることからも、現実に起きてしまった震度7への対応も必要ですが国の基準自体が追い付いていないのが実情として挙げられます。
フルリフォームをするケースでは、費用も高額になります。その際に、1.0で計画をするのではなく最低で1.5以上と考えた方が安心です。
後程算出方法などをご紹介しますが、上部構造評点の数値を高くすればするほど、耐力壁が増えるなど居住空間を狭める形になるため、居住性をかなり犠牲になるケースを見ますが、このような耐震改修はノウハウがあり実績がある会社に依頼するのが最も適切でしょう。さまざまな方法を持っているからです。
結局は現実的な地震を想定して設計することに
上部構造評点をできる限り高くすることはできないことではありませんし、それを強く意識しても問題はありません。しかし、現実的にどれくらいの地震が発生し、どれくらいのエネルギーがかかるかはある程度の予想がつきます。例えば、東海地震や南海トラフ地震など想定される大地震が発生した場合、住んでいるエリアはどれくらいの揺れになるかは、自治体から出されているハザードマップなどで明らかになっています。
自治体が想定する揺れよりも大きくなる可能性ももちろんありますが、基本的には専門家が算出したものを用いているので大きく食い違う可能性は低いです。また直下型地震などこれまで起きていなかったような地震が起きる可能性も否定はできませんが、地震の専門家ですらその可能性を模索するのは大変です。
最後は家主の決断にかかっている
とはいえ、上部構造評点の数値をどれくらいにした方がいいかを判断するのは家主の決断であって、自治体や業者が決めることではありません。1.0では「一応」倒壊しないというレベルなのでまだ不安があるというのであれば、1.5以上を目指すべきだと考えております。
熊本地震のデータをみると、2000年以降に建築した木造住宅の倒壊率は2%、大破を加えても6%でした。これをわずか2%と取るかどうかになります。新たな耐震基準として定められた1981年~2000年に建築された木造住宅では、倒壊率は9%、大破を加えれば約20%でした。これもわずかととらえるのかどうか。それ以前となると倒壊率だけで28%、大破率を加えれば46%となっております。(参照:国土交通省)
国土交通省の調査では、無被害だったケースは2000年以降に建てられた耐震等級1の木造住宅で6割、1981年以前の旧耐震基準ではたったの5%。つまり、現状の上部構造評点で「一応」倒壊しないレベルにあったとしても、その確率はかなり低いことを意味します。裏を返せば、上部構造評点0.7や1.0にしておかないと熊本地震で3割近い木造住宅が倒壊したように、耐久性が低いと非常に厳しい結果を招くので、このあたりのデータをしっかりと受け止めましょう。

ここから上部構造評点の算定方法についてです。いったいどのように算定されていくのか、ご紹介します。
建物の重さ
まず1つ目の要素は、建物の重さです。建物の重さには3段階あり、軽い建物、重い建物、非常に重い建物があります。これは建築基準法で屋根材の分類がなされており、昔ながらの瓦の屋根だと重い屋根になります。最近の建てられた家はコロニアルと呼ばれるセメントを加工して作った薄い屋根が主流なので、軽い屋根となります。瓦屋根とコロニアルで1㎡あたりの重さは倍も違います。これが上部構造評点に大きな影響を与えることは明らかです。
特に最近は金属屋根と呼ばれるものもあり、その重さは瓦屋根の8分の1、コロニアルの4分の1と非常に軽いため、耐震性能を高めることに寄与します。他にも壁に関しても重さに影響をするため、建物の重さがかなりの影響を与えることをまずは覚えていただけるといいでしょう。
耐震工事を行う中で屋根を軽量化しただけで1.0をクリアしたケースも結構あります。屋根に関しては風雨に晒されている分、劣化が発生しやすい場所でもあるので、日ごろのメンテナンスを兼ねて屋根の軽量化などを行っておくのがいいかもしれません。
壁の構造
次に注目されるのが壁の構造です。X方向、Y方向それぞれに壁がどのように配置されているのかをチェックしていきます。あまり壁の配置に関して、X方向とY方向の壁のバランスに関して考えたことがある人は多くないかもしれません。チェックしてみると意外な落とし穴が壁の構造で見つかるものです。例えば一定方向に壁がほとんどないケース、壁が一部分に集中的にあるケースなど様々。こうなると耐震性を著しく悪くして、上部構造評点の点数を下げることにつながります。
例えば2階部分の上部構造評点は1.0以上を確保しているものの、1階部分に関しては0.7もない場合があって、そうなると倒壊につながりやすくなります。同じ1階でもX方向とY方向で大きく食い違うので、壁を増やすなどして対策を立てないといけません。
もしも壁の構造で上部構造評点を上げるのであれば、壁の補強を行うことになります。最近では大がかりなリフォームをしなくても、耐震性の高い板のようなものを設置して耐震性を高めるやり方もあります。できればリフォームを行うのが理想的ですが、費用面を考えると、少しでも安くしたいと考えるのが普通であり、なるべく簡易的に済ませたいと考えるのが普通です。
地盤や地形
次にポイントになるのが、地盤や地形に関することです。分譲地が新たに完成するケースがありますが、分譲地になる前は畑や池だったケースが多く、一応対策は立てているものの、元々の地盤的に決して強くない場所は結構あります。特に関東は既に結構開発が進んでいるので、新たな分譲地の多くは地盤に不安を残すところが多いでしょう。この場合、地盤の評価は悪いと判断され、上部構造評点の数値を下げることにつながります。
耐震診断において地盤調査を行う際には、揺れやすい地盤であるか、液状化現象が起こりやすいか、造成地であるかなどを吟味し、該当すればリスクが高いと判断されて必要な耐力を増やすことになります。
地形に関しては平地であれば特に問題はありませんが、ガケや傾斜がきついエリアに建っていた場合も評価を落とすことにつながります。ガケなどにある場合、側面の土が流れ込まないよう、擁壁を作るケースがありますが、この擁壁が崩れると大変です。頑丈なコンクリートであればいいものの、例えば石積みになっているケース、特に何もしないケースであれば、それが評価を下げるきっかけに。地震で擁壁が崩れる可能性もあるため、そこまで考慮しないといけないのです。
基礎工事
最後に基礎工事ですが、ひび割れもなく鉄筋コンクリートを使った基礎であれば健全という判断がなされ、評価は下がりません。しかし、鉄筋の入っていない無筋基礎は地震のエネルギーに耐えられないケースもあるため、評価が約30%下がります。旧耐震基準の建物の多くが無筋基礎となるために1.5以上を目指すケースでは基礎補強を避けて通ることはできません。補修では評価は上がりません。
また玉石基礎の場合も判断が分かれます。玉石基礎は、囲碁の碁石を大きく厚めにしたような石を置いてその上に家を建てる昔ながらのやり方ですが、これだと基礎として弱く、揺れに耐えられないケースが想定されます。
基礎工事に関しては対策が立てやすく、室内もしくは室外から鉄筋コンクリートを使って本来の基礎と抱き合わせ基礎補強する必要があります。玉石基礎に関しては複数の柱をまとめて縛るような形にして固めていくなど、様々な方法があります。この方法であれば、地盤が弱いケースでも対応ができるので、上部構造評点を高めることができます。

上部構造評点を意識し、耐震工事、改修工事を行っていきますが、ここでは具体的な方法についてご紹介します。
基礎からやり直す
古い建物程、基礎の耐久性が低いために、基礎から壊れていくケースも想定できます。現状では鉄筋が入った形で基礎を作るものの、以前は無筋状態だったため、決してしっかりとした基礎とはいえません。そのため、先ほど基礎工事でご紹介したようなやり方で補強を行っていくことになります。
接合部を見直す
築年数が経過した物件における弱点は基礎だけではありません。建築材と建築材の接合部がノーマークになっていることがあります。ノーマークになっているので揺れがくると、その部分にダメージがかかって倒壊につながるので、接合部の補強を行う必要があるのです。この場合の補強は接合部を金属などでしっかりとつなぎ合わせること。これをするだけで耐震性能に大きな違いが生まれます。
屋根を軽くする
屋根の項目でもご紹介した通り、屋根の影響はあまりにも大きく、屋根の重さで倒壊したケースも目立ちます。築年数が経過している木造住宅ほど瓦屋根であり、場合によっては土葺きと呼ばれる、土を乗せてから屋根を乗せるという二重に思いケースもあるので、これだと重さでやられてしまいます。屋根を取り換えるだけで十分な補強工事になりますが、思っている以上に費用がかかってしまうのがネックです。
壁の補強工事
X方向とY方向、それぞれにバランスが悪ければ倒壊しやすくなることはご紹介してきました。実際に壁の補強工事を行う場合は壁の増設、もしくは現在使われている柱などを補強するなどの対策が必要になります。場合によっては壁の解体も必要になるので、その間、ホテル暮らしを余儀なくされることも。こちらも結構費用がかかるので、なかなか手が出ないこともあります。
耐震改修に関する工事費の目安を出す自治体も
実際耐震改修工事新倉の費用がかかるのか、その目安を知らないことには、見積もりの妥当性などがわかりません。そこで自治体によっては一定の耐震補強を行うのに必要な工事費の目安を紹介するケースも。例えば高知県の場合、「一応倒壊しないレベル」まで高めるのに1㎡あたり7000円から2万円とし、倒壊しないレベルまで高めるのに1㎡あたり1万3000円から3万円かかると掲載。この幅の大きさは現状の上部構造評点によって大きく変化します。
この場合の面積は延べ床面積になるので、延べ床面積に1㎡あたりの単価をかければ、おおよその目安がわかります。延べ床面積が80㎡ぐらいであれば最低でも56万円、最大240万円が1つの目安に。もちろん、基礎の状況などで変わりますが、目安を知るだけでも見積もりを取る際に、良心的なところ、そうでないところを見極めるのに役に立ちます。
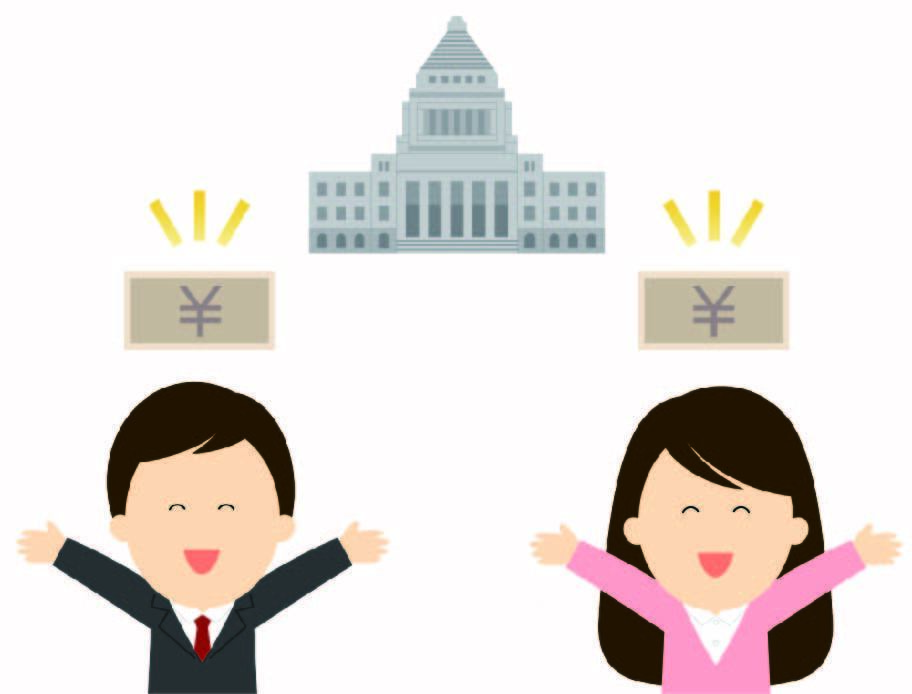
耐震工事は結構なお金がかかることは明らかで、それを理由に耐震工事を諦める人も。とはいえ、それでは万が一の時に危機を乗り切ることができません。そんな時におすすめなのが自治体の補助金です。
耐震診断から補助金申請の流れ
補助金申請までの流れは自治体によって異なる部分もありますが、あくまでも一例としてご紹介します。耐震診断の費用も補助される場合は、まず自治体で活動する耐震診断士を選び、申請書類を出します。それが通れば、契約を行って耐震診断を行ってもらいます。領収書をもらい、必要書類を自治体に送ったら補助金が出る流れです。
ここで上部構造評点が算出され、築年数や上部構造評点の数値によって耐震工事の補助が出るかどうか決まります。もし対象だった場合は、先に耐震工事の見積もりをとって、交付申請を行います。審査が通れば契約を結ぶ、工事を行って支払いを済ませて領収書を受け取り、必要書類をまとめて提出し、2週間以内に補助金が振り込まれるという、同じような流れです。
この流れはあくまでも一例で、細かいところで違いはあるでしょう。ただこの形式がほとんどであるとともに、地元の業者はこのあたりのルール、条件に長けているケースが多いので、見積もり段階で詳しく聞いてみることをおすすめします。
補助金以外の支援制度も少なからず存在する
補助金以外の支援制度では、専門家の派遣が挙げられます。耐震診断も本格的にやろうとすると10万円以上の費用がかかり、なかなか手が出せません。そこで自治体が費用を大幅に負担することで耐震診断を利用しやすくさせています。例えば秋田県男鹿市の場合は耐震診断費用13万円のうち、12万円を市が負担して、家主は1万円のみの負担となります。
またリフォームを行う際にローンを組むケースがありますが、このローンで発生する利子を補給する自治体もあります。山形県遊佐町では、耐震補強を行う際、年2.5%の利子を補給します。これにより、事実上無利子でローンを借りられるため、返済期間によってはかなりの負担軽減になります。
ユニークなところでは、北海道江差町では「江差町住宅リフォームプレミアム商品券発行事業」を行っています。リフォームで使える商品券5万円分を4万円で購入できるというもので、最大100万円分の商品券を80万円で購入できるため、20万円が補助されるような形です。
補助金などが一番多く、どこも力を入れていますが、自治体によっては補助金以外で支援を行うケースもあるので、「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」を見ながら探していきましょう。
耐震で失敗しない為の
『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』
500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!
耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!
耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。
読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。
※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。
【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】
第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う
診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。
記事(全6本):
➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」
➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か
➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方
➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか
➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている
第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術
治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。
記事(全11本):
➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか
➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画
➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠
➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事
➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実
➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値
➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌
第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術
計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。
記事(全5本):
➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較
➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”
➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強
➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技
➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値
第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術
計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。
記事(全4本):
➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術
➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解
➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術
➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル
第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない
実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。
記事(全5本):
➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択
➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは
➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画
➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事
➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化
第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択
最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。
記事(全4本):
➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか
➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実
➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください
➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ
終章:エピローグ ~100年先も、この家で~
終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。
記事(全1本):
➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。
< 著者情報 >
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。
戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・
- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。
耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。
補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)
ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新
※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。
営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)