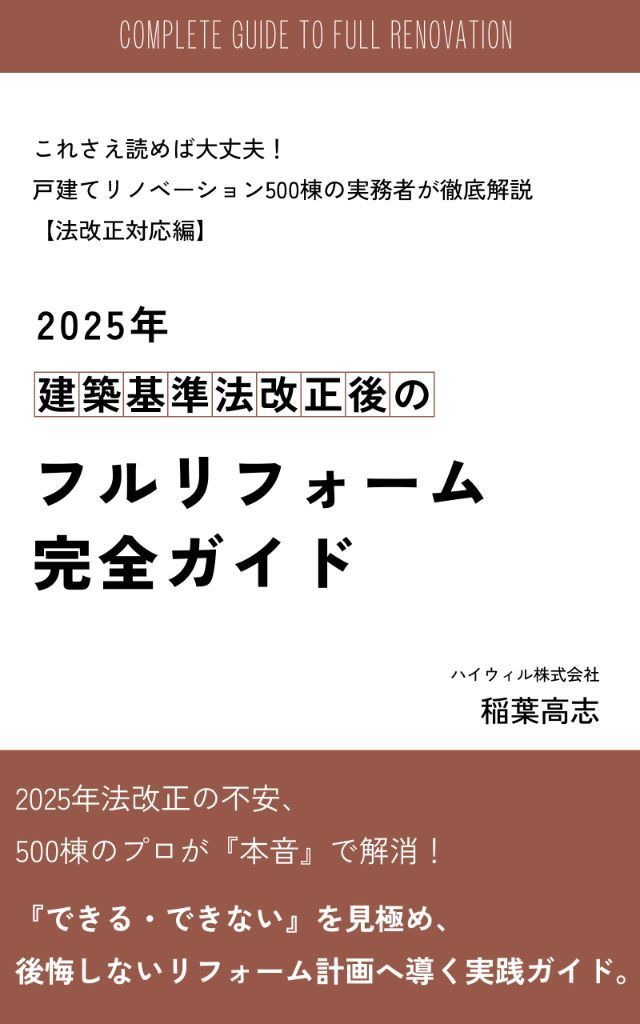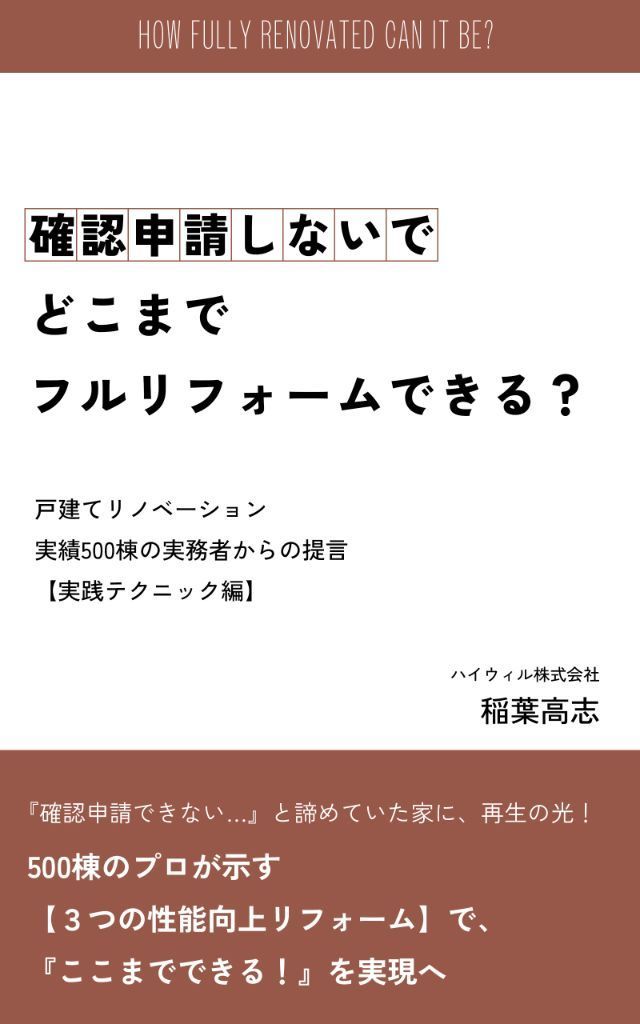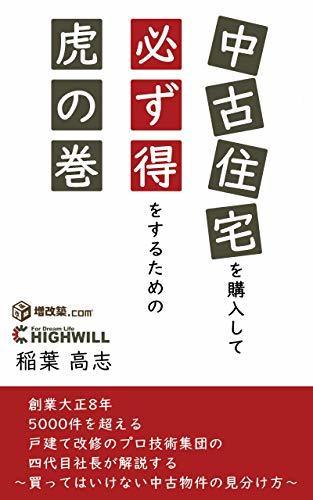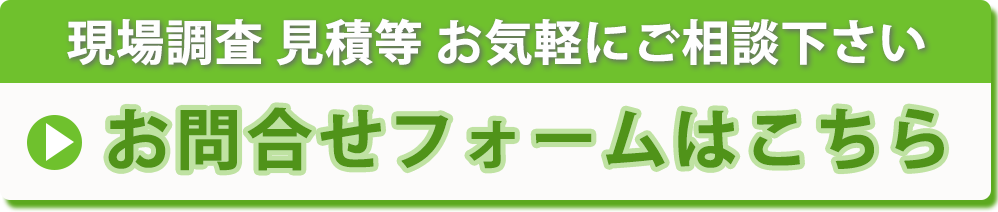戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル
更新日:2025/08/21
【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル
【耐震ガイド22/32】国の補助金+減税+贈与税非課税…使える制度“全部乗せ”徹底解説
✔ここでの概要:
これまでの章で、私たちは、家の性能を高めるための様々な技術と、そのリアルな費用について学んできました。その中で、「理想の性能を実現するには、やはり相応の費用がかかるのだな」と、感じられた方も、少なくないでしょう。
しかし、もし、その費用の全てを、皆様ご自身が、負担する必要はないとしたら、どうでしょうか。
国や自治体は、質の高いリフォームを、税金や補助金で、力強く応援してくれます。
この章では、その、いわば「第三の予算」とも言える、補助金・減税制度の全体像を解説します。
これは、単なる「お得情報」ではありません。知っている者だけが、その恩恵を最大限に享受できる、賢い資金計画を立てるための、極めて重要な「航海術」なのです。
序章.1 なぜ、国や自治体は、あなたのリフォームを応援してくれるのか
✔ここでのポイント:
まず、多くの方が、最初に抱くであろう素朴な疑問、「なぜ、国や自治体は、税金を使ってまで、個人のリフォームを、応援してくれるのだろうか?」という問いに、お答えします。
その背景にある、社会全体にとっての、大きなメリットを理解することが、これらの制度を、自信を持って、そして、積極的に活用するための、第一歩となります。
序章.1.1 それは「施し」ではなく、「未来への投資」である
「耐震補強工事に補助金が出る」「耐震改修で減税される」。
このような話を聞くと、「なんだか、うまい話すぎて、少し怪しい…」「何か、裏があるのではないか?」と、感じられる方も、いらっしゃるかもしれません。
しかし、ご安心ください。国や自治体が、皆様のリフォームを支援するのは、決して、気まぐれや、単なる「施し」では、ありません。
それは、皆様の家が、安全で、そして、高性能になることが、社会全体にとって、計り知れないほど、大きな「利益」をもたらすからです。
皆様のリフォームは、皆様ご自身のためだけでなく、社会の未来に対する、極めて、価値の高い「投資」であると、国は、考えているのです。
序章.1.2 あなたの家の性能が、社会を強くする
では、具体的に、どのような「利益」が、あるのでしょうか。
-
① 防災力の向上 皆様の家が、一軒、また一軒と、地震に強い家へと、生まれ変わっていく。それは、来るべき、巨大地震の際に、倒壊する家が、一軒、また一軒と、減っていく、ということを意味します。これにより、街全体の、火災の延焼リスクが低減し、そして何よりも、救われるべき、多くの「命」が、守られます。皆様の家の耐震リフォームは、ご家族を守ると同時に、社会全体の、防災力を、向上させる、極めて、公共性の高い、行為なのです。
-
② 環境負荷の低減 皆様の家が、高い断熱性能を持つ、省エネ住宅へと、生まれ変わる。それは、家庭で消費される、冷暖房のエネルギーが、削減される、ということです。その、一軒一軒の、小さな努力の積み重ねが、国全体の、エネルギー消費量を抑制し、地球温暖化という、大きな課題に、立ち向かう力となります。
-
③ 良質な住宅ストックの形成 古い家を、ただ、壊しては、建てる、という「スクラップ&ビルド」の時代は、終わりを告げました。これからは、今ある、良質な建物を、適切に、メンテナンスし、性能を向上させ、長く、大切に、住み継いでいく、「ストック活用型社会」への転換が、求められています。長期優良住宅化リフォーム推進事業などの制度は、まさに、そのための、国の、強い意志の表れです。
このように、皆様の、質の高いリフォームは、社会全体にとって、数多くの、プラスの効果をもたらします。だからこそ、国や自治体は、耐震補助金などの制度を設け、皆様の、その、尊い「投資」を、力強く、後押ししてくれるのです。
序章.2 「補助金」と「減税」― 似て非なる、二つの恩恵
✔ここでのポイント:
次に、皆様が、これから活用していくことになる、二つの、主要な支援制度、「補助金」と「減税」の、根本的な違いについて、解説します。「もらうお金」である補助金と、「支払う税金が、安くなる」減税。この二つの、性質の異なる恩恵を、正しく理解し、そして、時には、戦略的に組み合わせることが、資金計画の、成否を分けます。
序章.2.1 「補助金(助成金)」とは、“もらう”お金
まず、「補助金」、あるいは、「助成金」と呼ばれるものです。 これは、非常にシンプルです。
皆様が行う、リフォーム工事の費用の一部を、国や自治体が、現金で、直接、補助してくれる、という制度です。
一般的には、工事の「前」に、計画書などを提出して、申請を行い、その審査が通った上で、工事に着手。
そして、工事が完了した後に、実績報告書などを提出し、指定された、銀行口座に、補助金が、振り込まれる、という流れになります。 これは、皆様の、リフォーム資金計画において、直接的な「収入」となる、極めて、パワフルな支援です。
序章.2.2 「減税(税制優遇)」とは、“支払わなくて済む”お金
一方で、「減税」、あるいは、「税制優遇」と呼ばれるものです。 これは、皆様が、本来、国や自治体に、納めるべき「税金」の一部を、免除、あるいは、軽減してくれる、という制度です。 これには、いくつかの種類があります。
リフォームのために、支払った費用の一部が、その年の、所得税から、直接、差し引かれる「税額控除」。
あるいは、リフォーム後に、毎年、支払う「固定資産税」が、一定期間、減額される、といったものです。
また、親御様などから、資金援助を受ける場合に、莫大な「贈与税」が、非課税になる、贈与税非課税措置も、この、リフォームにおける、減税制度の、一種と、言えるでしょう。
これらは、直接、現金が振り込まれるわけではありませんが、皆様の、手元に残るお金を、結果として、増やしてくれる、という点で、補助金と、同じく、非常に、大きな恩恵です。
序章.2.3 最強の戦略 ― 「合わせ技」で、恩恵を最大化する
そして、ここからが、最も重要な、戦略的な視点です。
これらの、「補助金」と「減税」は、多くの場合、「併用」することが、可能です。
例えば、耐震補強工事に対して、自治体の耐震補助金を受け取り、さらに、国に対して、耐震改修の減税を、申請する。
あるいは、長期優良住宅化リフォーム推進事業という、国の補助金を、2025年度の予算で活用し、さらに、その質の高いリフォームに対して、住宅ローン減税の、最大限の控除を受ける。
このように、複数の制度を、巧みに、組み合わせる「合わせ技」を、知っているかどうか。
それこそが、皆様の、資金計画に、「数百万円」という、大きな差を生み出す、プロの「航海術」なのです。
序章.3 この章であなたが手に入れる、制度を使いこなし、賢く資金計画を立てるための全知識
✔ここでのポイント:
最後に、この記事を通じて、皆様が、どのような「力」を、手に入れることができるのか。その、ゴールを、明確に、お示しします。それは、単なる、制度の、カタログ情報ではありません。
皆様ご自身が、ご自宅のリフォーム計画において、これらの、複雑な制度を、完全に、使いこなし、賢明な、資金計画を、立案するための、実践的な「全知識」です。
序章.3.1 あなたを、賢明な「戦略家」へと、導くロードマップ
この、一見、複雑で、そして、毎年、目まぐるしく、変化する、補助金・減税制度という、大海原。
それを、皆様が、自信を持って、航海するために。
この記事は、そのための、完璧な「ロードマップ」として、皆様を、ゴールまで、安全に、導くために、書き下ろされました。 この先の章で、私たちは、以下の、全ての航路を、皆様と共に、辿っていきます。
-
Step 1.【国の大型補助金】: まず、最も影響の大きい、国の、二大補助金制度、「長期優良住宅化リフォーム」と、最高峰の「省CO2先導型」の、全貌を、解き明かします。
-
Step 2.【3つの減税制度】: 次に、所得税と、固定資産税という、二つの税金に対する、3つの、主要な減税制度を、その、仕組みと、申請方法の、全てを、解説します。
-
Step 3.【世代間の資産継承】: そして、親から子へ、賢く、資産を引き継ぐための、最強の武器、「贈与税の非課税措置」の、活用シナリオを、ご提案します。
-
Step 4.【結論と、アクションプラン】: 最後に、これらの、全ての制度を、確実に、そして、最大限に、活用するための、絶対的な「鉄則」と、皆様が、明日から、できる、具体的な「アクションプラン」を、お渡しします。
序章.3.2 もう、「知らなかった」では、済まされない
この旅を終える頃には、あなたは、もはや、ただ、業者から、提示された見積もりを、眺めるだけの、無力な、存在ではありません。 ご自身の、リフォーム計画が、どの制度に、合致する可能性があるのか。
そのためには、どのような、性能レベルを、目指すべきなのか。
そして、いつ、どのタイミングで、誰に、相談し、何を、準備すべきなのか。 その、全ての、戦略を、自らの意志で、描き出し、そして、実行することができる、賢明な「戦略家」へと、生まれ変わっているはずです。
さあ、それでは、皆様の、リフォーム費用に対する、漠然とした「不安」を、未来への、揺るぎない「希望」へと、変えるための、最後の、そして、最も、価値ある、学びの旅へと、出発しましょう。
章の概要:
序章で、私たちは、補助金・減税制度が、リフォームにおける「第三の予算」となり得る、という、希望に満ちた可能性についてお話ししました。
この第1章では、いよいよ、その中でも、最も代表的で、そして、金額も大きい、国が主導する二つの大型補助金制度について、その全貌を解き明かしていきます。
多くの性能向上リノベーションが、まず、その活用を目標とする、いわば“王道”とも言える「長期優良住宅化リフォーム推進事業」。そして、その、さらに先、ZEH水準を超える、最高峰の性能を目指す、一握りのチャレンジャーだけが、その栄誉を手にすることができる「サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)」。
それぞれの目的、補助額、そして、その厳しい基準をクリアし、採択されるための、重要なポイントを、私たちの豊富な経験に基づいて、解説します。
1.1 基本の「き」:長期優良住宅化リフォーム推進事業
✔ここでのポイント:
まず、質の高い、耐震リフォームを行う、ほとんどの方が、その活用の対象となり得る、最も重要で、そして、最もポピュラーな、国の補助金制度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」について、その全てを解説します。
どのような目的の制度で、いくら補助金がもらえ、そして、そのためには、どのような性能レベルを、クリアする必要があるのか。その、基本の「き」を、完全にマスターしていただきます。
1.1.1 「長く、快適で、安全な家」を、国が応援する理由
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」。
少し、長い名前ですが、ぜひ、皆様に、覚えていただきたい、国の、最も代表的な補助金制度です。
その名の通り、この事業の目的は、「既存の住宅(中古住宅)を、適切なリフォームによって、長く(長期にわたって)、安心して、快適に住み続けられる、質の高い(優良な)住宅へと、生まれ変わらせる(化)ことを、国として、力強く、推進する」というものです。
序章で、お話ししたように、国は、古い家を、次々と壊しては、建てる、という、これまでの社会から、今ある、良質なストックを、大切に、手入れしながら、長く使い続けていく、循環型の社会への転換を、目指しています。
この補助金は、まさに、その、国の、大きな意志を、体現した制度なのです。 そして、その「質の高さ」を、測るための、具体的な物差しとして、主に、以下の、3つの性能を、向上させることが、求められます。
-
① 構造躯体の劣化対策(柱や土台の、腐食や、シロアリ対策など)
-
② 耐震性(最低でも、耐震等級1(評点1.0)以上への、性能向上)
-
③ 省エネルギー対策(断熱材や窓の、性能向上など)
これらは、まさに、私たちが、このガイド全体を通じて、皆様に、その重要性を、お伝えしてきた、性能向上リノベーションの「三位一体」そのものです。
つまり、皆様が、このガイドで学ばれた、本質的なリフォームを、実践しようとするのであれば、この補助金は、極めて、親和性が高く、そして、力強い、味方となってくれるのです。
1.1.2 具体的に、いくら、補助金がもらえるのか?
では、この長期優良住宅化リフォーム推進事業を活用することで、具体的に、いくらの補助金が、受け取れるのでしょうか。
その金額は、皆様が、どのような性能向上工事を行うか、そして、どこまで、高いレベルを目指すかによって、変動します。 補助金の額は、それぞれの工事にかかる費用の「3分の1」が、上限とされており、さらに、その性能レベルに応じて、全体の補助上限額が、定められています。
【補助上限額の目安(2025年度の例)】
-
評価基準型(基本的な性能向上):100万円/戸
-
劣化対策、耐震性、省エネ対策など、定められた、最低限の性能基準を、クリアした場合。
-
-
認定長期優良住宅型(より高い性能向上):200万円/戸
-
上記に加えて、リフォーム後の住宅が、法律に基づく「長期優良住宅」としての、認定を取得した場合。
-
-
高度省エネ・省CO2型(最高レベルの性能向上):250万円/戸
-
さらに、ZEHレベルの高い省エネ性能などを、実現した場合。
-
このように、皆様が、より高いレベルの、性能向上を目指せば、目指すほど、国からの、支援も、より手厚くなる、という、非常に、よくできた仕組みになっています。 私たち、増改築どっとコムが、手掛ける、耐震リフォームの多くは、この「認定長期優良住宅型」あるいは「高度省エネ・省CO2型」を、目標として、計画を進めていきます。
100万円、200万円という補助金は、リフォーム全体の費用 相場から見れば、決して、小さな金額では、ありません。
この制度を、賢く活用できるかどうかは、皆様の、資金計画の、成否を、大きく、左右するのです。
1.2 最高峰への挑戦:サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)
✔ここでのポイント:
次に、補助金制度の、いわば「最高峰」とも言える、特別な事業について、ご紹介します。
それは、単に、質の高いリフォーム、というレベルを超え、日本の、未来の家づくりの「手本」となるような、先進的なプロジェクトだけが、採択される、極めて、名誉ある補助金です。
私たちの、仕事に対する、哲学と、技術力の、象徴とも言える、この事業の、全貌を、お話しします。
1.2.1 「手本」となる、家づくりへの、特別な支援
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」が、全ての、質の高いリフォームを、広く応援するための、制度であるとすれば、次にご紹介する「サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)」は、その、遥か、先を行く、いわば「オリンピック選手」を、育成・選抜するための、特別なプログラムです。
この事業の目的は、「住宅の、脱炭素化を、強力に、推し進めるための、先導的な、技術や、設計手法を、導入した、極めて、模範的な建築物を、国が、事業として採択し、その実現を、強力に、支援する」というものです。 つまり、「良い家」を作る、というレベルではなく、「日本の、未来の家づくりの、手本(モデル)となる、特別な家」**を作ること。それが、この事業に、採択されるための、絶対的な、条件となります。
1.2.2 ZEHを超える、圧倒的な性能と、破格の補助額
当然ながら、その、求められる性能レベルは、極めて、高いものとなります。 断熱性能においては、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準を、遥かに超える、G2、G3レベルの、超高断熱仕様が、求められます。耐震性能においても、耐震等級3の確保は、当然の、スタートラインです。
その上で、LCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅に、代表されるような、建設時から、解体時までの、全生涯にわたる、CO2排出量を、マイナスにする、というような、先進的な、設計思想が、盛り込まれているか、といった点が、厳しく、審査されます。
これは、まさに、私たち、増改築どっとコムが、理想とする、性能向上リノベーションの、究極の姿です。
そして、この、極めて、高いハードルを、乗り越えた、一握りのプロジェクトに対して、国は、破格の、支援を用意しています。 その補助額は、「その、先導的な、性能向上のために、追加で、必要となった費用の、2分の1」という、極めて、手厚いものです。
プロジェクトの規模にもよりますが、補助額が、200万円を、超えることも、決して、珍しくありません。 この事業に、採択されることは、単に、経済的なメリットが、大きい、というだけではありません。
それは、皆様の家が、そして、私たちの仕事が、国の、未来の家づくりの、手本として、公式に、認められた、という、何物にも代えがたい「名誉」の証となるのです。
私たち、増改築どっとコムは、この、極めて、難易度の高い、先導事業においても、お客様を、採択へと導いた、豊富な実績と、経験を持っています。
1.3【自治体との連携】国の補助金と、自治体 耐震補助金の上乗せ・併用は可能か?
✔ここでのポイント:
国の、大きな補助金制度だけでなく、皆様が、お住まいの、最も身近な行政パートナーである「市区町村」が、独自に用意している、補助金制度の、重要性について、解説します。そして、プロならではの、最も、重要な戦略、「国の制度」と「自治体の制度」を、賢く、組み合わせる「合わせ技」の、可能性と、注意点について、お話しします。
1.3.1 あなたの街にも、必ずある「宝の山」
国の、大きな制度に、つい、目が行きがちですが、皆様が、絶対に、見逃してはならない、もう一つの、補助金の源泉。
それが、皆様が、今、お住まいの、あるいは、リフォームをご検討中の、市区町村といった、「自治体」が、独自に、用意している、補助金制度です。
全国の、ほとんど全ての自治体が、それぞれ、独自の耐震補助金や、省エネリフォームに関する、助成制度を、設けています。
特に、耐震補強工事に対する補助金は、多くの自治体で、非常に、手厚く、整備されています。 これは、国の制度とは、全く、別枠の、自治体独自の、支援です。この、身近な「宝の山」を、活用しない手は、ありません。
1.3.2 プロの腕の見せ所 ― 補助金の「合わせ技」
では、ここで、最も、重要な、戦略的な問いです。
「国の、長期優良住宅化リフォーム推進事業と、自治体の、耐震補助金。この二つを、同時に、両方とも、受け取ることは、できるのか?」 この問いに対する、答えこそが、プロと、そうでない業者とを分ける、一つの、大きな分水嶺となります。
答えは、「条件付きで、イエス」です。 多くの場合、国と自治体は、「同じ工事内容に対して、補助金を、二重に、受け取ることは、認めない」という、ルールを、設けています。
しかし、ここで、プロの「知恵」が、活きてきます。
私たちは、リフォーム全体の工事を、いくつかの「パッケージ」に、分解して、考えます。
-
パッケージA:純粋な「耐震補強」に関する工事(基礎補強、壁補強、金物設置など)
-
パッケージB:「省エネ性能の向上」に関する工事(断熱材の充填、サッシ交換など)
-
パッケージC:「劣化対策」や「バリアフリー」に関する工事
そして、パッケージA(耐震)に対しては、「自治体の、耐震補助金」を、申請する。
パッケージB、C(省エネ、劣化対策)に対しては、「国の、長期優良住宅化リフォーム推進事業」を、申請する。
このように、申請する工事内容を、それぞれの制度の、目的に合わせて、巧みに、切り分けることで、二つの補助金を、合法的に「併用」し、お客様が、受け取れる、補助金の総額を、最大化する。
この、極めて、高度な、申請戦略の立案と、そのための、緻密な、書類作成。
これこそが、制度を、知り尽くした、専門家だけが、ご提供できる、本当の価値なのです。
次の章では、この「もらうお金」である、補助金に加えて、皆様の、負担を、さらに、軽減してくれる、「減税」の世界について、詳しく、見ていくことにしましょう。
章の概要:
前章では、国や自治体から、直接、現金が支給される「補助金」という、力強い支援について解説しました。
しかし、皆様が受けられる恩恵は、それだけではありません。
この第2章では、補助金という「もらうお金」だけでなく、皆様が、本来、国や自治体に納めるべき税金が、安くなる「減税・控除」という、もう一つの、極めて大きなメリットについて、お話しします。
リフォームの資金計画は、この「減税」までを、視野に入れてこそ、完璧なものとなります。
多くの方が混同しがちな、複雑な税制優遇を、「①自己資金向けの所得税控除」「②固定資産税の減額」「③住宅ローン向けの所得税控除」という、3つの、明確な柱に分け、それぞれの仕組みと、賢い活用法を、国土交通省の最新情報に基づき、正確に、そして、分かりやすく、解説していきます。
2.1【所得税①】投資型減税:耐震改修促進税制による、税額の直接控除
✔ここでのポイント:
まず、主に、自己資金(現金)や、期間の短いリフォームローンで、工事費用を支払われる方向けの、最も直接的で、パワフルな所得税の減税制度、「耐震改修促進税制」について解説します。「所得控除」ではなく、納めるべき税金そのものから、直接、差し引かれる「税額控除」という、その、強力な仕組みと、適用を受けるための、具体的な条件を、マスターしていただきます。
2.1.1 納めるべき「税金」が、そのまま、安くなる
皆様が、耐震リフォームを行う際に、活用できる、所得税の減税制度には、大きく分けて、二つの種類があります。
まず、最初にご紹介するのが、主に、自己資金でリフォームをされる方向けの、「投資型減税」と呼ばれるものです。
これは、所得税法に定められた、「住宅耐震改修特別控除」という制度で、その最大の魅力は、「税額控除」である、という点にあります。
「税額控除」とは、皆様が、一年間の所得に基づいて計算された、納めるべき所得税の金額、そのものから、直接、一定額を、差し引くことができる、という、極めて、強力な減税措置です。皆様の、手取り収入を増やす、というよりも、むしろ、出ていくお金(税金)を、直接的に、減らしてくれる。
まさに、国が、皆様の「安全への投資」を、税金の面から、力強く、応援してくれる制度なのです。
2.1.2 具体的な控除額と、その適用条件
では、具体的に、どのくらいの金額が、控除されるのでしょうか。
2025年現在、この制度では、耐震改修工事にかかった、標準的な費用の10%を、その年の所得税額から、控除することができます。控除対象となる工事費用には、250万円という上限額が設けられているため、最大で25万円が、皆様の、その年の所得税から、直接、差し引かれることになります。
もちろん、この、パワフルな減税措置を受けるためには、いくつかの、重要な条件を、クリアする必要があります。
-
対象となる住宅: ご自身が、所有し、そして、居住している住宅であること。
-
対象となる工事: 1981年5月31日以前に建築された、いわゆる「旧耐震基準」の住宅を、現行の耐震基準(新耐震基準)に、適合させるための耐震補強工事であること。
-
必要な証明書類: 工事が完了した後、その工事が、確かに、耐震基準を満たすものであることを、建築士や、指定確認検査機関などが証明した「増改築等工事証明書」を、取得すること。
これらの条件を満たした上で、工事が完了した、翌年の、確定申告の際に、税務署に、必要書類を提出することで、この税額控除を、受けることができます。これは、耐震改修の減税制度の中でも、最も基本的で、そして、直接的な恩恵の一つです。
2.2【固定資産税】工事翌年度分が減額に。自治体への申告で受けられる恩恵
✔ここでのポイント:
次に、所得税とは全く別に、全ての持ち家所有者が、毎年、支払っている「固定資産税」が、安くなる、という、もう一つの、見逃せない減税制度について、解説します。工事が完了した、翌年度分の、固定資産税が、最大で、2分の1まで、減額される、という、この制度。その、適用条件と、絶対に忘れてはならない「申請先」について、ご説明します。
2.2.1 毎年、支払う「固定資産税」も、安くなる
所得税の減税に加えて、質の高い耐震リフォームを行った皆様には、もう一つ、嬉しいご褒美が、用意されています。
それが、「固定資産税の減額措置」です。
固定資産税とは、皆様が、所有されている、土地と、家屋に対して、その価値に応じて、毎年、課税される、地方税です。
この、毎年、必ず、支払わなければならない、固定資産税が、一定の条件を満たす、耐震改修工事を行った場合、工事が完了した、翌年度の1年分に限り、その税額が、最大で、2分の1まで、減額されるのです。
2.2.2 減額を受けるための条件と、「申告先」の注意点
この、固定資産税の減額措置を受けるための条件は、所得税の場合と、ほぼ、同じです。
-
対象となる住宅: 1981年5月31日以前に建築された住宅であること。
-
対象となる工事: 現行の耐震基準に適合させるための、耐震補強工事で、その費用が、一定額(多くの自治体で50万円)以上であること。
そして、ここからが、最も、重要な注意点です。 所得税の減税は、国の機関である「税務署」に、確定申告をすることで、手続きを行いますが、この、固定資産税の減額は、皆様の、お住まいの地域を、管轄する、「市区町村の、税務課(資産税課など)」に、直接、申告しなければならないのです。
この、「申告先が、国と、市で、違う」という事実を、ご存じない方が、非常に多く、せっかく、減税の権利があるにも関わらず、申請を、忘れてしまい、その恩恵を、受けられていない、というケースが、後を絶ちません。
申告の期限は、工事完了後、3ヶ月以内、と定められていることが、ほとんどです。
私たちのような、専門家は、工事の完了が、近づいてきた段階で、必ず、お客様に、この、固定資産税の減額申告について、アナウンスをさせていただきますが、皆様ご自身も、この、もう一つの、重要な減税制度の存在を、ぜひ、覚えておいてください。
2.3【所得税②】ローン型減税:性能向上リフォームで「住宅ローン減税」を最大化する
✔ここでのポイント:
最後に、リフォーム費用を、10年以上の「住宅ローン」で、賄われる方向けの、もう一つの、そして、極めて影響の大きい、所得税の減税制度、「住宅ローン減税」について、解説します。そして、なぜ、私たちが、一貫して、お勧めしている「性能向上リノベーション」が、この、住宅ローン減税の恩恵を、最大限に、引き出すための、最強の「鍵」となるのか。その、戦略的な、関係性を、明らかにします。
2.3.1 「ローンで、リフォームする人」のための、特別な減税制度
ここまで、主に、自己資金で、リフォームをされる方向けの、減税制度について、お話ししてきました。
では、10年以上の、長期の「住宅ローン」を組んで、リフォームをされる方は、どうなるのでしょうか。
その方々のために、国は、「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」という、また、別の、極めて、手厚い、減税制度を、用意しています。 (※原則として、先ほど、2.1でご紹介した「投資型減税」と、この「ローン型減税」は、併用することはできません)
この制度は、毎年の、年末時点での、住宅ローンの残高の、一定割合(2025年現在は0.7%)を、所得税額から、直接、控除(税額控除)してくれる、というものです。
そして、その控除が、最長で10年間、継続します。 例えば、年末のローン残高が、2,000万円あったとすれば、その0.7%、すなわち、14万円が、その年の所得税から、直接、差し引かれる。これが、10年間続くわけですから、その、トータルの減税額は、極めて、大きなものとなります。
2.3.2 「家の質」が、「減税額」を決める
そして、ここからが、私たち、性能向上リノベーション専門業の、腕の見せ所であり、皆様の、賢明な、判断が、問われる、最も重要なポイントです。 実は、この、住宅ローン減税で、控除の対象となる、借入金の「上限額」が、皆様が、行うリフォームの「質」によって、大きく、変わってくるのです。
【リフォームにおける、住宅ローン減税の、借入限度額(2025年現在)】
-
一般的なリフォーム:2,000万円
-
質の高いリフォーム(長期優良住宅、ZEH水準など):3,000万円
お分かりでしょうか。もし、皆様が、私たちと、共に、長期優良住宅化リフォーム推進事業の認定を取得するような、質の高い、性能向上リノベーションを、実現した場合。
皆様は、一般のリフォームに比べて、1,000万円も多い、最大3,000万円までの、借入金を、減税の対象とすることが、できるのです。
これは、10年間で、最大70万円(1,000万円 × 0.7% × 10年)もの、減税額の「差」となって、現れます。 質の高い家づくりへの、挑戦は、皆様の、未来の、税負担までをも、軽くしてくれる。
この、「性能」と「税制」の、幸福な、連動関係。この、有利なルールを、知っているか、知らないか。
それが、皆様の、資金計画に、どれほど、大きな影響を、与えるか、ご想像に、難くないでしょう。
次の章では、いよいよ、世代を超えた、資産の継承に、絶大な効果を発揮する、「贈与税」の、特別な世界へと、ご案内します。
章の概要:
ここからは、補助金・減税制度の中でも、特に、ご家族の在り方、そして、世代を超えた資産の継承という、より大きなテーマに関わる、極めてパワフルな税制優遇について、深く、掘り下げていきます。それは、ご両親や、祖父母様から、住宅取得やリフォームのための資金援助を受ける際に、通常であれば、高額な負担となり得る「贈与税」が、最大1,000万円まで、非課税となる「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」です。この、最強とも言える制度を、性能向上リノベーションで、いかにして、賢く、そして、最大限に活用するのか。ご家族の想いを、非課税で、次世代へと繋ぐための、具体的なシナリオを、皆様にご提示します。
3.1 最大1,000万円が非課税に:「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」とは
✔ここでのポイント:
まず、この、少し名前の長い、しかし、絶大な効果を持つ、税制優遇制度の、基本的な仕組みについて、解説します。なぜ、通常であれば、高額な税金がかかる、親から子への「贈与」が、質の高い家づくりという目的のためであれば、特別に、非課税となるのか。その制度の趣旨と、具体的な非課税の上限額について、正確に、理解していただきます。
3.1.1 世代を超えた「想い」に、立ちはだかる贈与税の壁
「子供たちが、安全で、快適な家で、暮らせるように、親として、少しでも、資金の援助をしてあげたい」。
「実家を、二世帯住宅にリフォームするにあたり、親世帯から、資金を出してもらう予定です」。
性能向上リノベーションは、時に、このように、世代を超えた、ご家族の協力と、愛情によって、実現する、一大プロジェクトとなります。
しかし、その、温かい想いの前に、日本の税法は、時に、冷徹な「壁」として、立ちはだかります。
それが、「贈与税」です。 現在の、日本の法律では、個人から、年間110万円を超える、財産の贈与を受けた場合、その、超えた部分に対して、受け取った側が、贈与税を、納めなければなりません。
そして、その税率は、非常に高く、例えば、1,000万円の贈与を受けた場合、実に、数百万円という、莫大な税金を、支払わなければならないケースも、あるのです。
この、高い贈与税の壁が、親から子へ、という、スムーズな資産の継承を、阻む、大きな要因となっていることは、言うまでもありません。
3.1.2 質の高い家づくりを、国が、税制で後押しする
しかし、国は、この、高い贈与税の壁に、一つだけ、大きな「扉」を、用意してくれています。
それが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」です。
これは、「ご両親や、祖父母様から、ご自身が住むための家の、新築、取得、あるいは、“リフォーム”のために、資金の贈与を受けた場合には、一定の金額まで、贈与税を、非課税(ゼロ円)にしますよ」という、極めて、強力な、時限的な、特例措置です。
国としても、質の高い住宅が、一軒でも多く、市場に供給され、そして、国民が、安全で、快適な家に住むことは、社会全体にとって、大きな利益となります。
そのための、世代を超えた資金の移動(贈与)を、税制の面から、力強く、後押ししよう。それが、この制度の、根底にある、思想なのです。
では、その、非課税となる「上限額」は、いくらなのでしょうか。 この金額は、社会経済の状況に応じて、数年ごとに、見直されますが、2025年(令和7年)現在においては、最大で1,000万円と、なっています。
つまり、この制度を、賢く活用すれば、皆様は、ご両親から、1,000万円という、大金を受け取っても、そこに、贈与税は、一切、かからないのです。これは、通常の贈与と比較すれば、数百万円単位での、節税効果を、生み出します。耐震リフォームの、大きな資金源として、これほど、心強い制度は、他にありません。
3.2 非課税枠を最大化する「質の高い住宅」の条件
✔ここでのポイント:
ここからが、私たち、性能向上リノベーション専門業の、腕の見せ所です。実は、この1,000万円という、最大の非課税枠は、どんなリフォームでも、適用されるわけではありません。それを、手に入れるためには、そのリフォームが、国の定める「質の高い住宅」の、厳しい基準を、クリアしていることを、証明しなければならないのです。その、具体的な「条件」について、解説します。
3.2.1 「一般の住宅」と「質の高い住宅」で、異なる非課税枠
この贈与税非課税措置の、最も、巧妙で、そして、重要なポイント。それは、非課税となる、上限額が、皆様が、リフォームする家の「質」によって、二段階に、設定されている、という点です。
【住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額(2025年現在)】
-
① 一般の住宅の場合:500万円
-
② 質の高い住宅の場合:1,000万円
ご覧の通り、その差は、実に500万円。
この、あまりにも大きな差が、皆様のリフォーム計画の、質そのものを、そして、ご家族の、未来の安全を、大きく、左右することになるのです。
3.2.2 「質の高い住宅」として、認められるための“証明書”
では、どのようなリフォームが、「質の高い住宅」として、認められ、1,000万円の、最大の非課税枠を、手にすることができるのでしょうか。 その条件は、国税庁によって、明確に、定められています。
それは、以下の、3つの基準のうち、いずれか一つを、満たしていることを、第三者機関が発行する、「証明書」によって、客観的に、証明することです。
-
条件A:断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上
-
これは、いわゆる「ZEH水準」と呼ばれる、極めて高い「省エネ性能」を、証明するものです。
-
-
条件B:耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3
-
これは、言うまでもなく、国の定める、最高レベルの「耐震性能」を、証明するものです。
-
-
条件C:高齢者等配慮対策等級(共同住宅等は等級3)4以上
-
これは、高度な「バリアフリー性能」を、証明するものです。
-
もう、お分かりですね。
私たちが、このガイド全体を通じて、皆様に、その重要性を、訴え続けてきた、「耐震等級3」の取得。
あるいは、高いレベルの「断熱性能」の実現。
それらの、性能向上への挑戦が、皆様の家の、物理的な安全性を高めるだけでなく、同時に、この、贈与税非課税措置という、絶大な、経済的メリットを、最大限に、引き出すための、最強の「鍵」となるのです。
3.3 賢い活用シナリオ ― 親世代の資金援助で、子世代の家の性能を最高レベルに
✔ここでのポイント:
最後に、この、複雑に見える制度を、皆様の、リアルな人生の物語の中で、どのように、活用していくことができるのか。一つの、具体的な「賢い活用シナリオ」を、ご紹介します。親世代の、愛情ある資金援助が、子世代の家の、性能を、最高レベルへと引き上げ、そして、その、高い性能が、再び、贈与税の、非課税メリットを、最大化する。その、幸福な、循環の、物語です。
3.3.1 ある、ご家族の、リフォーム物語
ここに、一つの、ごく一般的な、ご家族がいます。 子育てを、終えられた、60代の、ご両親。
そして、そのご実家を、受け継ぎ、小学生のお子様と、共に、暮らす、40代の、ご夫婦。
ご夫婦は、築45年の、ご実家を、耐震リフォームし、これからも、安心して、暮らせる家にしたい、と願っています。
しかし、木造の、本格的な耐震補強と、断熱改修には、2,000万円近い費用が、かかることが分かり、その、資金計画に、頭を悩ませています。
一方、ご両親は、これまで、コツコツと、貯めてこられた、老後の資金の中から、「孫たちの、安全のために」と、1,000万円を、援助したい、と、考えています。
しかし、そこに、高額な「贈与税」の壁が、立ちはだかります。
3.3.2 私たちが、ご提案する「幸福な、方程式」
この、ご家族の、それぞれの想いを、一つの、幸福な未来へと、結びつける。それこそが、私たち、プロの、仕事です。私たちは、このご家族に、次のような「方程式」を、ご提案します。
①【贈与】
まず、ご両親から、ご夫婦へ、「住宅取得等資金」として、1,000万円が、贈与されます。
②【性能向上リノベーション】
私たちは、その、貴重な1,000万円を、最大限に、活かし、ただ、家を、綺麗にするだけでなく、その費用の、多くを、「骨格」の強化、すなわち、「耐震等級3」と「断熱等級6」を、同時に達成するための、性能向上工事に、投資します。
③【証明書の取得】
そして、工事完了後、私たちは、第三者機関の、厳格な審査を経て、その家が、「質の高い住宅」の基準を、満たしていることを証明する、公式なリフォーム 耐震等級証明等を、取得します。
④【非課税の実現】
翌年の、確定申告で、この「証明書」を、税務署に提出することで、ご両親から、受け取った、1,000万円の贈与は、全額が、非課税となります。
いかがでしょうか。
ご両親の、孫を想う、温かい気持ちは、一円の、税金を、支払うことなく、そのまま、家の、最高の「安全性」と「快適性」へと、姿を変えました。
そして、その、最高の性能が、再び、税制上の、最大のメリットを、引き出したのです。
これは、まさに、家族の愛情と、国の制度、そして、私たちプロの、専門的な知識が、三位一体となって、初めて、実現できる、最高の「価値創造」の、シナリオです。
次の、最終章では、これらの、全ての議論を踏まえ、皆様が、最高の未来を、手に入れるための、最後の、メッセージを、お届けします。
章の概要:
この長く、そして、皆様の資金計画にとって、極めて重要となる「補助金・減税制度」を巡る物語も、いよいよ最終章を迎えました。最後に、この、複雑で、多岐にわたる制度を、確実に、そして、最大限に活用するための、最も重要な「鉄則」と、具体的な「アクションプラン」を、皆様にお伝えします。これらの制度を、味方につけられるかどうか。その成否は、突き詰めれば、「タイミング」と「パートナー選び」という、二つの要素で、その9割が決まります。この記事で得た知識を、皆様の、賢い資金計画へと、確実に結びつけるための、最後の、そして、最も重要なメッセージです。
終章.1 全ての成否を分ける、たった一つの鉄則 ―「契約・着工前の申請」を、絶対に忘れない
✔ここでのポイント:
これまで、数多くの、魅力的な補助金や、減税制度について、解説してきました。しかし、それら、全ての恩恵を、手に入れる権利を、たった一つの、タイミングの間違いで、失ってしまう、という、最も悲しい事態を避けるために。このセクションでは、全ての制度に共通する、絶対的な、そして、最も重要な「鉄則」を、皆様の心に、深く、刻み込んでいただきます。
終章.1.1 全ての補助金は、「未来」への投資である
長期優良住宅化リフォーム推進事業、自治体の耐震補助金、そして、様々な耐震改修 減税制度。
もし、このガイドを通じて、皆様が、学ばれた、数々の制度の中から、たった一つだけ、絶対に、忘れないでいただきたい、黄金律(ゴールデンルール)を、お伝えするとするならば。
それは、「全ての補助金・助成金の申請は、必ず、工事業社との“契約前”、そして、“着工前”に行わなければならない」という、動かすことのできない、大原則です。
なぜ、これほどまでに、「着工前の申請」が、重要なのでしょうか。
その理由を、国や、自治体の、立場に立って、考えてみてください。
彼らが、税金という、貴重な財源を使って、皆様のリフォームを、支援する目的。
それは、序章でお話しした通り、「質の高いリフォームを“これから”行うことを“促す”ため」です。
もし、皆様が、すでに、工事契約を、済ませてしまっていたり、あるいは、すでに、工事が、始まってしまっていたり、としたら。それは、もはや、国や自治体が「促す」までもなく、皆様ご自身の意志で、そのリフォームを、実行することを、決めている、ということです。
つまり、補助金制度の、本来の目的である「誘導・促進」の、対象からは、外れてしまうのです。過去や、現在、進行形の工事に対して、後から、補助金が、支給されることは、原則として、絶対に、ありません。
終章.1.2 最も、悲しく、そして、最も、よくある失敗
私が、これまでのキャリアの中で、幾度となく、目の当たりにしてきた、最も、悲しいご相談。
それは、他のリフォーム会社で、すでに、工事を始めてしまった、お客様からの、「今からでも、補助金は、使えませんか?」という、お問い合わせです。
その、お電話の向こう側にある、お客様の、落胆された、お声を、聞くたびに、私は、胸が、締め付けられるような、思いがします。 「知らなかった」という、ただ、それだけの理由で、本来、受け取れるはずだった、数十万円、あるいは、数百万円という、大きな恩恵を、永遠に、失ってしまう。
これほど、もったいない、そして、悲しいことはありません。 この、あまりにも、多く見られる、悲劇を、防ぐために。 皆様には、ぜひ、この「契約・着工前の申請」という、鉄の掟を、リフォーム計画における、全ての議論の、大前提として、心に、刻んでいただきたいのです。
業者との、最初の打ち合わせで、皆様が、尋ねるべきは、キッチンの色の話では、ありません。
「私たちの、この計画で、活用できる可能性のある、補助金は、ありますか?
そして、その申請は、いつまでに、行う必要がありますか?」という、この、戦略的な、一言なのです。
終章.2 あなたに必要なのは、技術と制度の両方に精通したパートナー
✔ここでのポイント:
この、複雑な制度を、確実に、そして、最大限に、活用するためには、皆様の、パートナーとなる、リフォーム会社の、もう一つの「能力」が、問われます。それは、家を、建てる「技術力」だけではない、これらの、行政制度を、知り尽くした「制度活用力」です。その、二つの力を、兼ね備えた、本物のプロを、いかにして、見極めるか。その、具体的な、判断基準を、お伝えします。
終章.2.1 「技術力」と「制度活用力」という、車の両輪
皆様の、性能向上リノベーションという、壮大な航海を、成功へと導くためには、その船長となる、パートナーには、二つの、全く異なる、しかし、どちらも、欠かすことのできない、能力が、求められます。
一つは、言うまでもなく、「技術力」です。
それは、皆様の家を、地震や、寒さ、暑さから守るための、構造や、断熱に関する、深い知識と、それを、現場で、完璧に、実現させる、確かな施工能力です。
そして、もう一つが、「制度活用力」です。
それは、このガイドで、解説してきたような、国や、自治体が、用意する、無数の、補助金や、減税制度の、最新情報を、常に把握し、どの制度と、どの制度が、組み合わせられるのか。
そのために、どのような、書類を、いつまでに、どこへ、提出しなければならないのか。
その、複雑な、行政手続きの、全てを、知り尽くした、知識と、経験です。
この、「技術力」と「制度活用力」は、まさに、車の両輪です。
どんなに、素晴らしい技術力を持つ会社も、制度を知らなければ、お客様に、数百万円の、経済的な、損失を、与えてしまうかもしれません。
逆に、どんなに、制度に詳しい会社も、それを、実現するための、技術力がなければ、それは、ただの、絵に描いた餅に、終わってしまいます。
この、二つの力を、高いレベルで、兼ね備え、お客様の利益を、最大化するための、最適な「資金計画」と「工事計画」を、一体のものとして、ご提案できること。
それこそが、皆様が、パートナーとして、選ぶべき、本物の、プロフェッショナルの、姿なのです。
3.2.2 そのプロを、見極めるための「問い」
では、どうすれば、その、二つの力を、兼ね備えた、パートナーを、見つけ出すことが、できるのでしょうか。
それは、具体的な「問い」を、投げかけることです。
-
「私たちの、この耐震リフォーム計画では、国の長期優良住宅化リフォーム推進事業と、葛飾区の自治体 耐震補助金は、併用することが、可能でしょうか?その場合、どのように、申請を、切り分けるのが、最も、有利ですか?」
-
「親からの、資金援助を、受ける予定なのですが、贈与税非課税措置 リフォームの、1,000万円の枠を、活用するためには、どのような、性能証明が、必要となりますか?そのための、リフォーム 耐震等級証明の取得サポートも、お願いできますか?」
これらの、具体的で、専門的な問いに対して、自信を持って、そして、よどみなく、明確な答えと、戦略を、示してくれる。
そして、時には、確認申請を回避する、といった、法的な航海術までをも、含めた、総合的なアドバイスをしてくれる。
そのような、業者こそが、皆様が、信頼するに、値するパートナーです。
終章.3 明日からできる、最初の一歩 ― 自治体の窓口と、専門家への相談
✔ここでのポイント:
最後に、この、素晴らしい、しかし、複雑な制度を、活用するための、皆様が、「明日からでも、できる」、具体的で、そして、簡単な、「最初の一歩」を、お伝えします。この、小さな一歩が、皆様の、リフォーム計画を、より、豊かで、そして、確実なものへと、変える、大きな原動力となります。
終章.3.1 まずは、あなたの街の「宝の地図」を、手に入れよう
「何から、手をつけて良いか、分からない」。
この、長いガイドを、読み終えられ、皆様は、今、膨大な知識と共に、少しだけ、途方に暮れている、かもしれません。
しかし、ご安心ください。皆様が、踏み出すべき、「最初の一歩」は、極めて、シンプルです。
第一歩:お住まいの、市区町村の「役所」へ、行ってみる(あるいは、電話してみる)。 まず、皆様が、お住まいの、あるいは、リフォームをご検討中の、市区町村の、建築指導課や、住宅課といった、担当窓口を、訪ねてみてください。そして、窓口の担当者に、ただ、こう、伝えるだけで、良いのです。 「今度、自宅の、耐震と、断熱のリフォームを、考えているのですが、何か、市で、使える、補助金や、助成金の制度は、ありますか?」と。
きっと、担当者は、皆様に、関連する制度の、パンフレットを、渡してくれるはずです。それが、皆様の、リフォーム計画における、最初の「宝の地図」です。
終章.3.2 「地図」と「夢」を持って、専門家(ふね)のもとへ
そして、その、宝の地図を、手に入れたら。 第二歩:その「地図」と、皆様の「夢」を持って、私たちのような、専門家(プロ)に、相談する。
「私たちの街には、こんな、補助金制度が、あるようです」
「私たちは、この家で、こんな、安全で、快適な、暮らしを、実現したいのです」
その、二つを、私たちに、お見せください。 私たち、プロの仕事は、その、皆様の「夢」と、制度という「現実」を、結びつけ、そして、皆様の、限られた予算の中で、最高の価値を、生み出すための、最適な「航路」を、描き出すことです。
この、二つの、簡単な、アクション。それが、皆様の、漠然としていた、リフォーム計画を、具体的な、資金計画に裏打ちされた、揺るぎない「プロジェクト」へと、変える、魔法の呪文です。
私たち、増改築ドットコムは、その、皆様の、最初の一歩を、いつでも、心より、お待ちしております。
この、複雑で、しかし、知れば、知るほど、面白い、補助金と、減税の、世界。ぜひ、私たちと、一緒に、冒険に、出かけましょう。
次の記事➡️ 記事『23. 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択』へ進む
【最新】2026年『リフォーム補助金 完全ガイド』
2026年のリフォーム補助金をどこよりも詳しく網羅解説しています。
これさえ読めば2026年のリフォーム補助金は大丈夫です!
2026年にリフォームされる方はリフォーム前に必ず読んでください!
2026年リフォーム補助金の全体像をまずは確認しましょう。
環境省・国土交通省・経済産業省の3つの省庁が連携して、4つの制度がワンストップで利用できる補助金制度
住宅省エネ2026キャンペーンの4つの補助金を個別解説
耐震で失敗しない為の
『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』
500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!
耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!
耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。
読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。
※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。
【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】
第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う
診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。
記事(全6本):
➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」
➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か
➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方
➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか
➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている
第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術
治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。
記事(全11本):
➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか
➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画
➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠
➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事
➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実
➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値
➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌
第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術
計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。
記事(全5本):
➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較
➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”
➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強
➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技
➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値
第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術
計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。
記事(全4本):
➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術
➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解
➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術
➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル
第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない
実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。
記事(全5本):
➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択
➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは
➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画
➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事
➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化
第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択
最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。
記事(全4本):
➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか
➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実
➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください
➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ
終章:エピローグ ~100年先も、この家で~
終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。
記事(全1本):
➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。
断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』
500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!
断熱リフォームをする前に必ず読んでください!
何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。
導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。
※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。
< この記事の著者情報 >
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。
2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。
250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

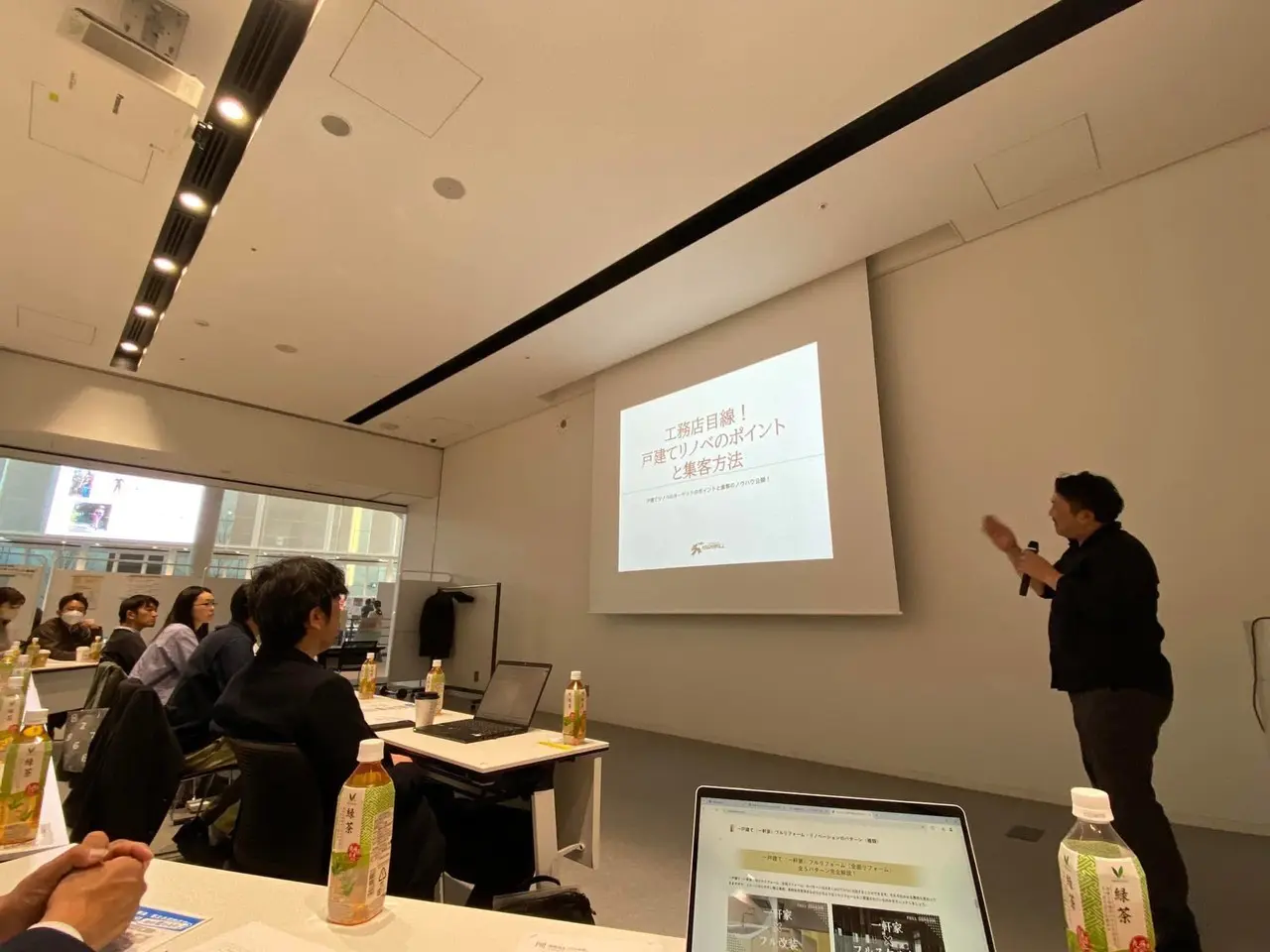
このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。
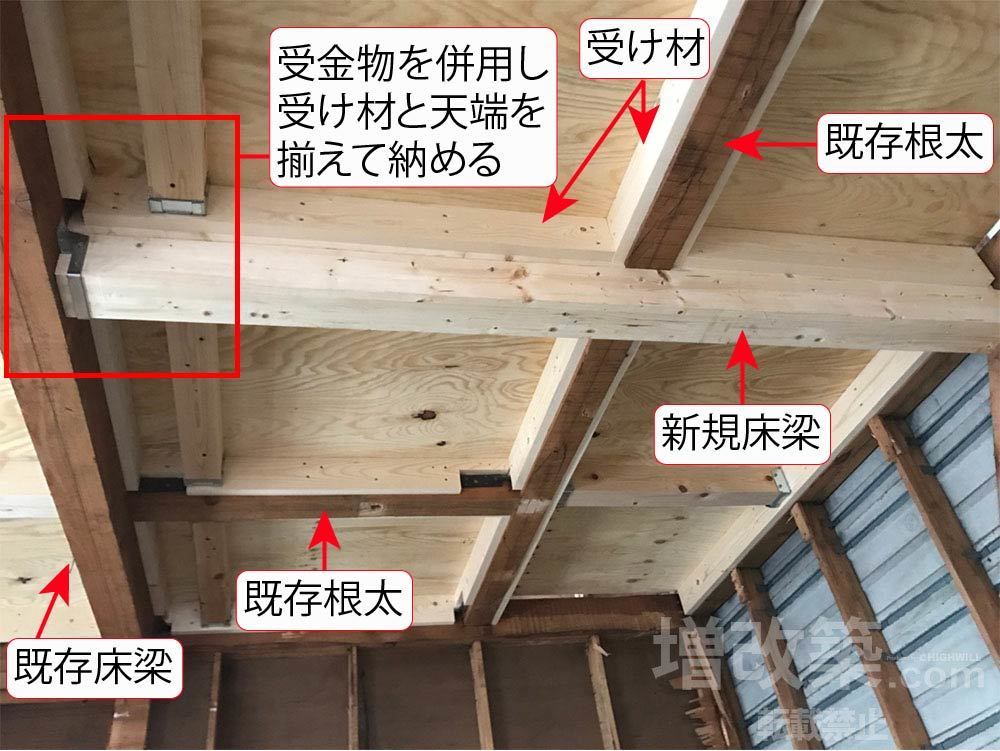
フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。
戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・
- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。
営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)